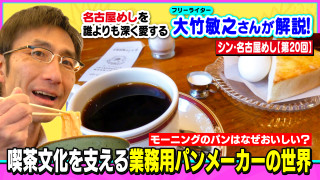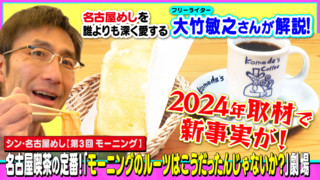お月見団子=丸・・・ではなく「芋」形が名古屋の常識?~大竹敏之のシン・名古屋めし

芋名月の伝統にちなんだ名古屋のお月見団子
今年の十五夜=中秋の名月は10月6日(旧暦の8月15日)。お月見を楽しむ習慣が古くからあり、そこで欠かせないのがお月見団子です。ピラミッド形に積まれた丸いお団子を思い浮かべる人も多いと思いますが、名古屋のお月見団子はこれとはずい分様子が違います。
「名古屋では芋をかたどったお月見団子が主流です。町の和菓子店でつくられている大半はこのタイプじゃないでしょうか」というのは明治28年(1895)創業の「福田屋」(名古屋市千種区)5代目の澤口允(まこと)さん。店によってはもう少し細長い“しずく”形とも呼ばれるタイプも見られますが、こちらも芋形をアレンジしたもののようです。
芋の形のお団子なんて変わっている・・・と思うなかれ。十五夜はもともと芋名月とも呼ばれ、里芋の収穫時期にもあたることから豊作を祝って芋をお供えしていたと伝えられます。それがやがて餅や団子に替わったと考えられ、だとすると芋形の団子はより芋名月の原点に近いとも解釈できます。
広くイメージされる丸いお月見団子は関東を中心に見られ、関西では団子に餡をまとわせたものも。材料はおおむねどこでも米粉(うるち米が原料の新粉も含む)が使われます。福田屋のお月見団子は米粉に砂糖または黒糖を加えてあり、食感はもっちり柔らかくもコシがあり、素朴な甘みが広がります。
また、伝統的な和菓子である薯蕷饅頭(じょうようまんじゅう ※上用饅頭とも)は山芋を原料とする皮であんこを包みます。薯蕷饅頭は生菓子を扱う和菓子店なら大体どこでもつくっている基本的な一品ですから、芋と和菓子店はもともと親和性が高いといえます。加えて、鶴亀松竹梅など縁起物をかたどるのも和菓子の伝統なので、収穫を祝う芋を団子でつくるのもむしろ自然なことといえそうです。
お月見団子は米と芋の食文化の分岐点?
「古代に大陸から稲作が伝来して米が日本人の主食となりましたが、山地や斜面など稲作に不向きな土地も多く、芋作も並行して息づいていました。名古屋のお月見団子は、日本の芋食文化と米食文化の分岐点を表しているといえるかもしれません」。そう語る澤口さんは、大学で民俗学を専攻。卒論のテーマはまさにこのお月見団子だったそうです。
「なぜ名古屋だけ芋形のお月見団子なのか? いろいろ調べましたがその理由までは分かりませんでした。尾張は古くから東西の文化が入り交じり、独特の風習がつくられたり残っているちょっと不思議な土地柄。お月見団子も、そういうこの地域らしい文化のひとつといえるんじゃないでしょうか」(澤口さん)
名古屋めしの肝ともいえる豆味噌も、原始的な製法の味噌がこの地域でだけ守り続けられ、地域固有の食文化の基盤となりました。芋形のお月見団子を名古屋めしと呼ぶのはちょっと無理があるかもしれませんが、名古屋めしに通じる地域の伝統や独自性を背景とするもの、といえるのではないでしょうか。
この秋は、名古屋の文化伝統にまで思いをはせながら、芋形のお月見団子で十五夜を楽しんでみてはいかがでしょう。
※記事内容は配信時点の情報です
#名古屋めしデララバ
番組紹介
東海地方の皆が知っているつもりである「ド定番」のスポット・話題・人などの知られざるポイントを太田光が独自の目線で徹底深掘り!深い情報を知り尽くしたマニアたちと共に知られざる魅力と驚きの事実を徹底取材で掘り起こしていく地元が大好きになる1時間!毎週水曜午後7:00~放送。