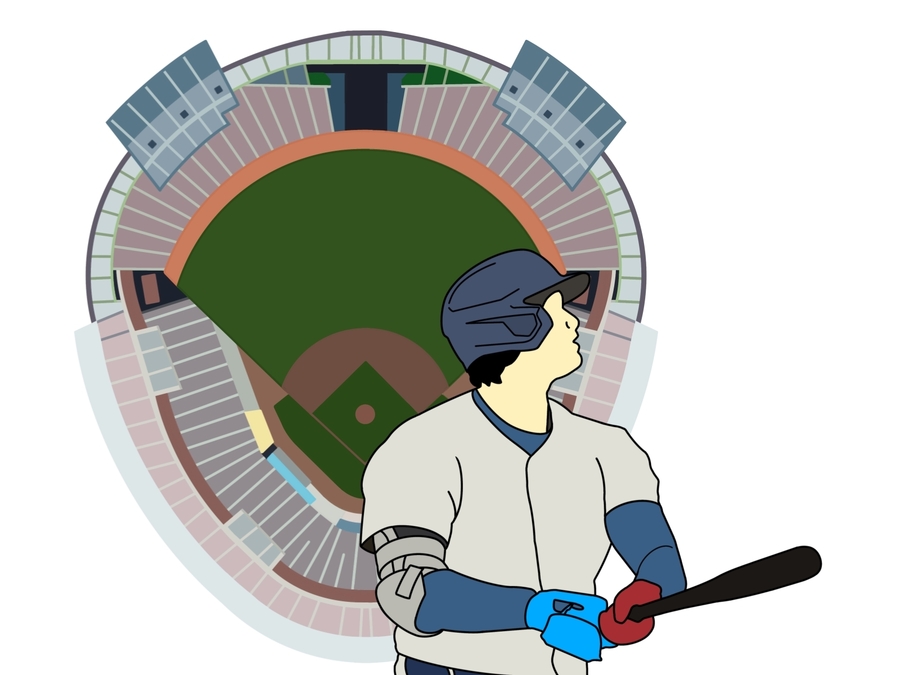共働き・共育ての救いになるか?「育児・介護休業法」の改正

10月1日、育児、介護と仕事が両立できる環境整備を目指した改正育児・介護休業法が施行されました。今回の法改正では柔軟な働き方を実現するための措置が企業に義務付けられ、小学校就学前のこどもがいる労働者がフルタイムでも働き続けられるように両立支援策が強化されています。7日放送の『CBCラジオ #プラス!』では、光山雄一朗アナウンサーが「改正育児・介護休業法」について、アディーレ法律事務所弁護士の正木裕美先生に尋ねます。
関連リンク
この記事をradiko(ラジコ)で聴く育児や介護がある労働者の法
「育児・介護休業法」とはどのようなものでしょうか。
正木「1992年に施行され、多数の改正を繰り返してきています。
例えば、育児や介護がある労働者の方が小さいこどもを育てるための育児休業、出産時の産後パパ育休、病気になったこどもを看護するための看護休暇、介護をするための介護休業や休暇、残業時間を制限したり、労働時間を短縮するといった制度、会社が取るべき措置などを定めている法律になります」
なぜ非正規になるのか?
このタイミングで改正された背景はなんでしょう?
正木「日本の状況が一番大きいです。少子高齢化が急激に進んでいます。働いている生産年齢人口はどんどん減少していて、2070年頃には人口9000万人を割り込んで、高齢化率も39%に達すると推計されています。
その中でも7割の女性は、ひとり目のこどもを産んだ後仕事自体は継続していますが、なかなか正社員としての働き方が定着しない。女性の正社員の率は20代後半をピークにどんどん減少していて、ちょうど子育ての時期はパートとかアルバイトとか、非正規雇用で働く人が増加しています。
なぜそうなったかと国がアンケートを取った結果、『仕事は続けたい、だけど、仕事と育児の両立が難しかったから、正社員として続けられなかった。会社にはなかなか育児と家庭を両立するための制度が整備されてないからどうしても難しい。だから融通がききやすい非正規雇用を選んだ』という方がすごく多かったんです」
どういう社会がいい?
正木「では、制度としてはないが、どういう働き方があったら仕事を続けられたか。
こどもが生まれてまもなく休業します。1歳を過ぎてから短時間勤務だったり、残業しないとか、出退勤の時刻を変えたり、シフト調整したり、テレワークをしたり、それぞれの状況にあわせた柔軟な働き方が欲しいという声が上がってきています。
さらに夫の家事、育児の時間が長いほど、妻の就業の割合が増えていきます。ということで夫が家事育児に参加する。それによって、妻も仕事を続けながらこどもを多数産むことができる、という社会が望ましいのではないか。
それで2023年に『こども未来戦略』というものが閣議決定されました。それによって、少子高齢化対策として、若い世代が希望どおり結婚し、希望する人は安心して子育てできる社会の実現を目指していこうという形の戦略が発せられました。
これに基づいて、共働き、共育てを推進しようということで今回の改正につながりました」
5つの措置
企業にはどのようなことが義務付けていますか?
正木「今回の改正に関しては、フルタイムで働き方をなるべくしてもらおうということで、3歳から小学校入学前のお子さんを育てる労働者が利用できる制度を作ってください、と会社に指示をしています。
法律が求めている5つの措置の中から会社が複数選んでください、となっています。その5つの選択肢とは…
・始業時刻の変更など
・月10日以上のテレワーク
・保育施設の設置、運営
・年10日以上の養育両立支援休暇の付与
・短時間勤務制度
そして、どういう制度をとったのかを、3歳未満のこどもを育てる従業員に対して適切な時期に制度を周知して使えるようにしてください。どういうことをしたいか意向確認をしっかりしてください。という形の義務付けがなされました」
今後を注目
今後子育て世代の労働環境を改善して経過をしっかり確認していかないといけませんね。
正木「この法律だけではなくて、経済問題だったり、地域の問題だったり、すべて横につながる問題としてあるので、そこに関してもどのような動きがあるか注目していいただきたいと思います」
身近で大切な法改正ですので、注目して見守っていきたいです。
(みず)
番組紹介
読んで聴く、新しい習慣。番組内容を編集した記事からラジオ番組を聴いていただける”RadiChubu”。名古屋を拠点とするCBCラジオの番組と連動した、中部地方ならではの記事を配信する情報サイトです。