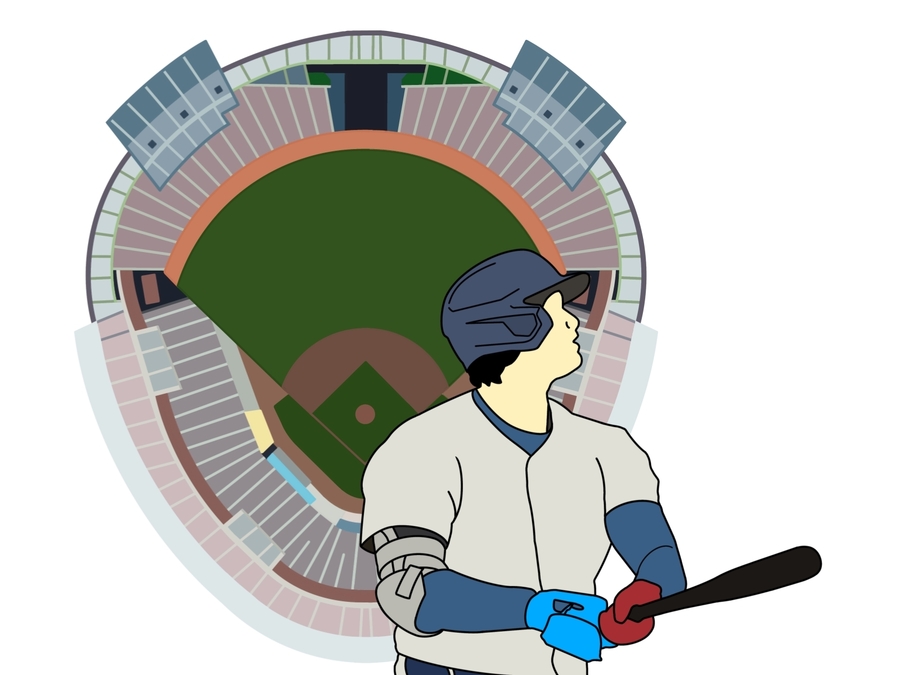食中毒発生1位は10月!その理由と予防法とは

10月に入り、やっと秋らしい気候が訪れるようになりました。秋の行楽や味覚を楽しむ人が増えますが、実は10月が1年で最も食中毒の発生が多い月とも言われています。7日に放送された『CBCラジオ #プラス!』では、山本衿奈が秋に増える食中毒の原因と、日常でできる対策について紹介しました。
関連リンク
この記事をradiko(ラジコ)で聴くなぜ秋が一番多い?
食中毒と聞くと、梅雨や真夏のイメージを持つ人も多いかもしれません。
しかし、山本は「そのイメージ自体が秋の食中毒を招いてしまっている」と指摘します。
夏場は、保冷剤の使用や食材の衛生管理など、食中毒への意識が高まりますが、秋は気温が下がることで注意が緩みがち。
ところが、近年は10月でも気温が30度近くになる日があり、弁当やバーベキューの食材に付着した細菌が繁殖しやすい環境が整ってしまうといいます。
また、サンマや秋サバなど旬の魚を食べる機会が増えることで、「アニサキス」などの寄生虫を口にするリスクも高まります。
さらに、秋のレジャーとして人気のキノコ狩りでは、食用と間違えて有毒なキノコを口にしてしまうケースもあるとのこと。
山本は、秋の食中毒は「細菌」「寄生虫」「自然毒」という3つのリスクが重なる時期だとし、特に注意が必要だと呼びかけました。
3つの予防方法
山本は、それぞれの予防方法を紹介しました。
まず「細菌」については、食材を触る前の手洗いや、弁当箱、調理器具は洗剤でよく洗い乾燥をさせるといった基本的なことは徹底する必要があります。
また、水分が出やすい野菜を弁当に入れるのは避け、弁当箱には冷ましてから詰めましょう。
「寄生虫(アニサキス)」の予防には冷凍加熱が効果的ですが、冷凍はマイナス20度で24時間以上、加熱は真ん中の温度が60度を1分以上維持させる必要があります。
また、目視でもアニサキスがついてないかを確認するのも大事なポイントです。
最後に「自然毒」は、キノコの場合、食用か不明なキノコは取らない、食べない人にあげない、ということを徹底しましょう。
安全に秋の味覚を楽しもう
山本「秋は本当においしいもの満載なので、ちゃんと対策をした上で、ここからまた秋の味覚もしっかりと楽しんでいきたいですね」
“食欲の秋”が苦い思い出にならないように、日々のちょっとした意識と対策が、自分や家族の健康を守る第一歩となります。
秋の味覚を楽しむ前に、いま一度、食中毒への注意を思い出してみてはいかがでしょうか。
(ランチョンマット先輩)
番組紹介
読んで聴く、新しい習慣。番組内容を編集した記事からラジオ番組を聴いていただける”RadiChubu”。名古屋を拠点とするCBCラジオの番組と連動した、中部地方ならではの記事を配信する情報サイトです。