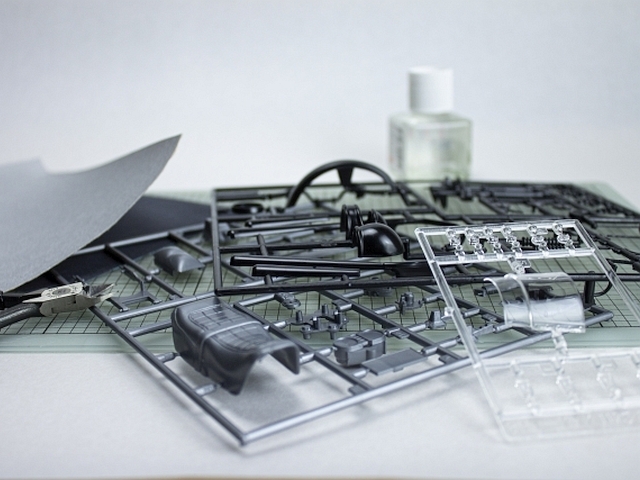相次ぐダイビング船の事故。実は事業の申請が不要だったことも一因か

今まさにマリンレジャーの季節真っただ中、ダイビング船で事故が相次いでいます。朝日新聞によれば、国土交通省が安全対策に乗り出しているとのことです。事故が相次いでいる理由には、意外と知られていない法律上のダイビング船の扱いが関係しているようです。『北野誠のズバリ』(CBCラジオ)では、この記事を基に、パーソナリティの北野誠と大橋麻美子、かみじょうたけしがトークを展開しました。
関連リンク
この記事をradiko(ラジコ)で聴くダイビング船は許可が不要?
記事によれば、ダイビングの船は、実は海上運送法における「人の運送をする事業」に当たらないため、事業として国への届出は不要とのこと。
遊漁船やトレジャーボートを転用する場合や、ダイビングツアーを行う業者と船を運航する業者が別々のケースもあり、全国で誰が何隻運行しているのかはまったくわからない状態となっているそうです。
国に代わって小型船を検査する特別民間法人・日本小型船舶検査機構(JCI)では、船の所有者に対して、船舶安全法に基づき検査時に申告する項目に、「ダイビング目的での船の使用の有無」を追加することとしました。
「使う」と答えた場合は、ダイビングに使う機材などを考慮して検査するとのことです。
ダイビングツアーに使用される船は、法制下では特に許認可を受けることなく業務を遂行していることになります。
届出不要な問題点
大橋「届出が不要ということは、いろんな義務も負わなくていいということになってしまいますよね」
北野「事故った時にどういうことなんっていうのが結構あるんですよね。中にはSNSで客を募集して、ひとりで船を持って営業している業者もいると。
インストラクターは資格を持ってると思うんですけど、船舶免許も持って、そこまで行ってダイビングをやって、ちゃんとみなさんを安全に上にあげてきてっていうのもひとりでやってたら怖いですよ」
大橋「船のメンテナンスもこういうことしてますって、たぶん事業者だったら出さなきゃいけないとかあるじゃないですか。
それが出さなくても良いってことだと、お客さんの方としては不安ですね」
不特定多数の人を何回も乗せるという点では、より厳しい検査が必要なように感じられます。
コストは下がるが安全性に疑問
申請制ではないため、事故がどれぐらい起きているのかなど、実態がつかみにくく、事故を未然に防ぐ対策も立てにくいなどといった問題があります。
また、ひとりで営業することでコストを下げて安い価格でダイビングができると人気が出る一方で、安全面に問題を抱えるということにもなりかねません。
それはダイビングだけではなく観光バスなどさまざまな乗り物で起こりうることでもあります。
北野は「マリンスポーツについて、僕も初めてこの記事を読んでこれが実態やったんかと思うと、ちょっと気をつけていただきたいなと思います」とまとめました。
(岡本)
番組紹介
読んで聴く、新しい習慣。番組内容を編集した記事からラジオ番組を聴いていただける”RadiChubu”。名古屋を拠点とするCBCラジオの番組と連動した、中部地方ならではの記事を配信する情報サイトです。