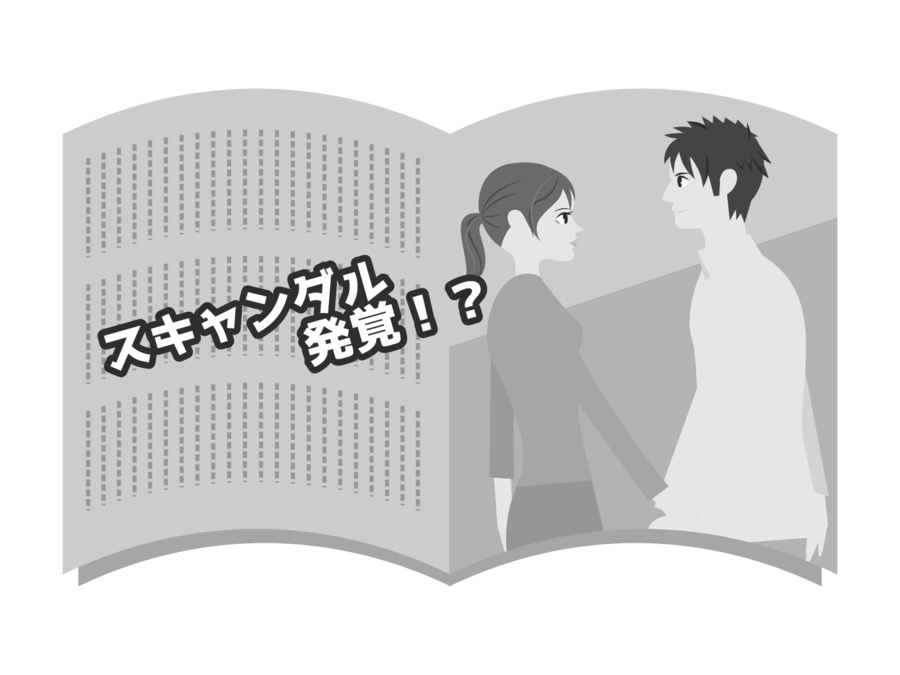今年からサービス向上?伝統の長良川鵜飼がスタート

飼い慣らした鵜を使って鮎などの魚を取る伝統的な漁法、鵜飼。その歴史は古く、平安時代から行なわれていたという記録があります。とくに有名なのは岐阜県の長良川鵜飼。今年もそのシーズンの幕が明け、今年度初めてとなる鵜飼が行なわれました。5月12日放送のCBCラジオ『つボイノリオの聞けば聞くほど』では、つボイノリオと小高直子アナウンサーが鵜飼について話題にします。
関連リンク
この記事をradiko(ラジコ)で聴く人と鵜との絆の技
岐阜県の長良川鵜飼は、1300年以上の長い歴史を持つ伝統の漁です。
鵜を操る鵜匠の巧みな技とよく訓練された鵜とのコンビネーションが見どころで、特に夜の川面にかがり火が浮かぶ中での鵜飼の様子は非常に幻想的。夏の風物詩として毎年人々を魅了しており、国の重要無形民俗文化財にも指定されています。
今年も例年同様、5月11日を皮切りに鵜飼がスタート。初日は午後8時頃から6隻の鵜舟による鵜飼が行なわれ、小雨が降る中でも多くの見物客が訪れたようです。
鳥帽子に腰蓑の伝統装束姿で手縄を華麗に操る鵜匠と、清流に潜る鵜が息を合わせて鮎を取るたびに、観覧客からは歓声が上がりました。
また、今年は靴を履いたまま乗船できる「椅子席」の観覧船を増やすなどして、外国人客への対応を図ったとのこと。
従来の鵜飼の観覧船には畳敷きの屋形舟が用いられてきましたが、近年は多様なニーズに応えるべく、椅子やソファで観覧できるようになっているようです。
長良川鵜飼は川の増水時などを除いて、10月15日まで毎日開催される予定です。
どんな人でも楽しめるよう
このニュースを聞いて、つボイはとあることに思い至ります。
つボイ「やっぱりどの伝統も同じような辿り方をするんだなと思ったんです。というのも、お茶の世界もよく似ていて」
同じく歴史の長い茶道の世界では、お茶室の畳の上で正座をした状態でお茶をいただくというのが長らく伝統的なスタイルでした。
つボイ「しかし明治以降になって外国人がたくさん来るようになった時に、『このままでは外国人が飲めないのでは?』ということで、靴を履いたまま椅子に腰かけてお茶をいただくという作法ができたんです」
明治時代に考案された立礼(りゅうれい)と呼ばれるこのお点前は、椅子に座ってテーブルでお茶を点てるというもの。
正座が苦手な人や初心者でも気軽に茶道を体験することができるので、より多くの人に伝統文化を楽しんでもらうことができるという点で近年あらためて注目されているのです。
つボイ「お茶の世界も鵜飼の世界も同じやなって」
伝統も柔軟に
正座が難しいのは、なにも外国人だけではありません。
小高「椅子席って外国人のお客さんを意識してってことなんでしょうけど、膝が悪くなった高齢の人にとってもいいですよね」
つボイ「それなんやわ」
茶道教室に通っているつボイですが、この頃はお茶の稽古へ行っても長時間の正座がきつくなってきたそう。
つボイ「『先生すみません、胡坐かいててもよろしいですか』って(笑)」
幸いお茶の先生は快く許容してくれるとのことで、つボイも身体に負担をかけることなく教室を続けることができているようです。
つボイ「高齢になってくるとなかなか正座できない人も多いんですよ」
小高「だからお寺さんにも、よく椅子とか座椅子とか置いてあるもんね」
鵜飼の椅子席も茶道の立礼も、外国人だけでなくさまざまな人にとっての配慮でもあるのでしょう。
伝統をあるべき形のまま受け継ぐことも、美しい文化を残すという観点では大切です。しかし今を生きる人たちが各々の時代に合った楽しみ方ができるよう、少しずつ手を加えていく過程もまた、歴史の変遷を感じて趣深いのではないでしょうか。
(吉村)
番組紹介
読んで聴く、新しい習慣。番組内容を編集した記事からラジオ番組を聴いていただける”RadiChubu”。名古屋を拠点とするCBCラジオの番組と連動した、中部地方ならではの記事を配信する情報サイトです。