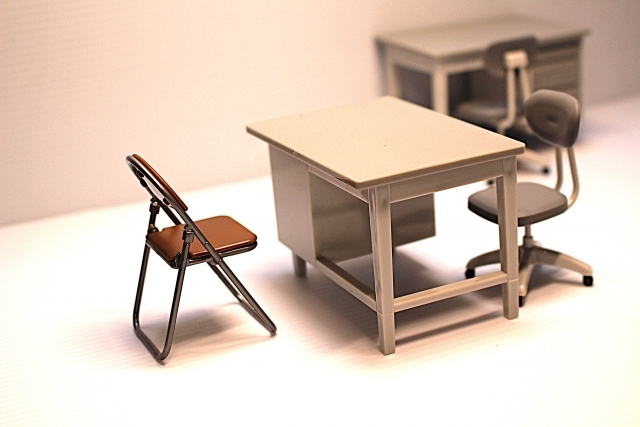泊原発3号機、審査11年で再稼働へ前進。防潮堤対策に5150億円

原子力規制委員会は4月30日、北海道の泊原発3号機について、再稼働に向けた安全対策が新規制基準に適合すると認める審査書案を了承しました。敷地内の断層が活断層ではないことなどの証明に時間がかかり、審査期間は過去最長となる11年9ヶ月に及びました。この長期間の審査により、当初の想定から状況が変化しています。5月1日放送の『CBCラジオ #プラス!』では、永岡歩アナウンサーとCBC論説室の石塚元章特別解説委員が泊原発3号機の審査合格とその背景について詳しく解説しました。
関連リンク
この記事をradiko(ラジコ)で聴く防潮堤費用が17倍に膨張
防潮堤に関しては、当初の安全対策工事費用が200億円から300億円程度と見積もられていましたが、現在の見積もりは5,150億円に膨れあがっています。これは当初の見積もりの17倍にあたり、3号機の建設費2,900億円を大きく上回る金額となっています。
さらに今後は、テロ対策施設などの設備も必要となるため、費用はさらに増加する見通しです。それでも今回の審査合格を受けて、2027年の再稼働を目指す動きが進んでいくことになります。
国内の原発は、建設中の3機を含めると36機存在しますが、そのうち実際に再稼働したのは8原発14基にとどまっています。
一方で、不許可となった例もあります。昨年11月には敦賀原発2号機が、直下に活断層がある可能性が否定できないという理由で、新規制基準を満たせず不許可となりました。
2月に閣議決定された「エネルギー基本計画」では、原発依存度を可能な限り低減する文言を削りました。廃炉を決めた原発の建て替えを進める方針に変わってきている状況です。
これはいわゆる「原発回帰」の動き。現在、日本の電力に占める原発の割合は約8.5%ですが、15年後には20%程度まで引き上げ、太陽光や風力の再生エネルギーを40~50%にしたい考えです。
地震・津波リスクと電力需要の増加
東日本大震災以前は原発の安全対策基準が現在ほど厳しくなかったため、福島第一原発事故の教訓を踏まえて現在は地震、断層、津波、テロなどの対策が強化されています。泊原発の審査で断層調査に多くの時間が費やされたのも、こうした背景があります。
原発が稼働すれば電気代抑制というメリットはありますが、地震大国である日本においては、目先の電気料金だけでなく長期的な安全性の視点が重要です。
今後審査を控える中部電力の浜岡原発は南海トラフ地震の震源域に位置するため、より厳しい審査が予想されます。原発建設当時の基準が現在より緩かったため、新規制基準の適用によって多くの問題点が明らかになってきています。
北海道千歳市では4月からラピダスの工場が稼働を開始し、さらにソフトバンクのデータセンターも計画されています。
ラピダスの工場は量産開始時に約10万キロワットの電力を消費し、ソフトバンクのデータセンターは将来的に国内最大級の100万キロワットを消費する見込みです。
泊原発3号機の出力は91万2,000キロワットで、これらの施設の電力需要をある程度補完することができます。
AI時代の電力需要と原発の安全性
AIの発展に伴い、データセンターなどの電力需要は今後さらに増加すると予想されています。便利な暮らしを維持しながら、十分な電力を確保するためには、原発の活用も選択肢のひとつとなります。ただし、リスクと未来のバランスを取ることが必要であり、次世代の安全をないがしろにすることはできません。
11年以上かけた審査が長かったのか短かったのかは一概に言えません。適合判断において地震の想定が過小ではないかという意見も一部ではあります。北海道積丹半島沖の海底で約22.6キロの活断層を想定していますが、一部の専門家からは「この活断層は60キロから70キロ以上にわたって動く可能性がある」と指摘されています。
北海道胆振東部地震のような「想定外」の事態を考慮すると、さらなる安全対策の必要性も議論されています。しかし、原発を停止し続けると電力不足に陥るリスクもあり、安全性と電力供給のバランスを取ることが求められています。
(minto)
番組紹介
読んで聴く、新しい習慣。番組内容を編集した記事からラジオ番組を聴いていただける”RadiChubu”。名古屋を拠点とするCBCラジオの番組と連動した、中部地方ならではの記事を配信する情報サイトです。