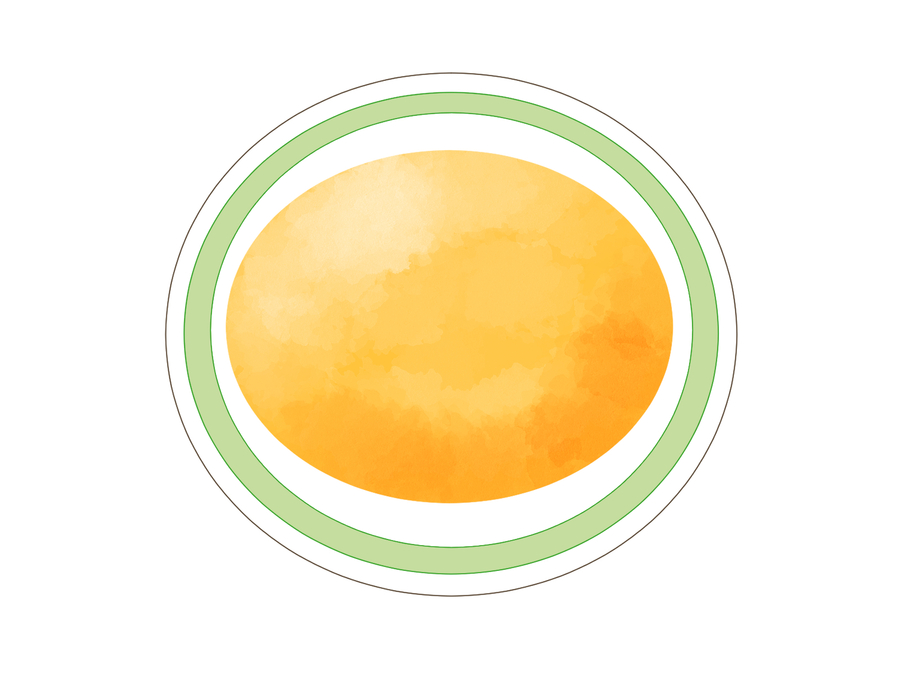茶道の道具、茶筅(ちゃせん)は9割以上が生駒市で作られていた!

いま世界的にブームになっているもののひとつが「抹茶」。その広がりをうけて海外から注文が殺到している伝統工芸品があります。「高山茶筅(たかやまちゃせん)」です。日本の茶筅はその9割以上が奈良県生駒市で作られています。なかでも高山地区は「茶筅の里」と呼ばれていて、室町時代から500年以上の歴史があるそうです。9月2日放送の『CBCラジオ #プラス!』では、光山雄一朗アナウンサーが奈良県生駒市の茶筅師・谷村丹後(たにむらたんご)さんに高山茶筅について尋ねます。
関連リンク
この記事をradiko(ラジコ)で聴く秘密の高山茶筅
谷村さんは20代続く茶筅師です。徳川幕府より名を与えられた茶筅師が13軒あって、そのうちのひとつが谷村さんだそうです。
高山茶筅はどういったものでしょうか?
谷村さん「生駒市の高山町で500年にわたって作り続けられている茶筅、高山で作る茶筅なので高山茶筅という名前です。
日本中で茶筅を作っているところは特にありません。それはなぜかというと、作り方を外部に漏らさないように秘密を守ってきたからです」
日本で作られている茶筅の9割以上が生駒市で作られているそうです。
世界に気付かれた
世界的にブームになった高山茶筅には、注文が殺到しているそうです。
谷村さん「そうですね、ここ10~15年前からです。それ以前は抹茶は日本でしか飲まれてなかったですし、同時に茶筅という道具も日本人だけが使っていたものでした。
ここへきて急に世界の方が抹茶の良さに気付かれて、ブームというより完全に定着して、それにともなって注文もすごく増えてきています」
特に注文が多いエリアはヨーロッパと東南アジアだそうです。
1日20~30本の生産
茶筅の種類について尋ねる光山。
谷村さん「茶筅は茶道と結びついて生まれた道具ですから、茶道の流派が数多く存在していて、その流派ごとに特徴のある茶筅…、素材、形、糸の色が違ったり、同じ流派の中でも使用する用途によって違ったりしますので、細かく数えると100種類以上になります」
日本国内でも茶筅が手に入らない状態だそうです。
谷村さん「残念ですが、とにかく500年間製法もほぼ変わっていませんし、100%手作りという製品なので、数が思うように作れません。
職人を育てるところから始めないといけないので、なかなかみなさんの需要にお応えするくらいの量が作り切れないというのが現状です」
現在高山には茶筅を作る家が16軒あるそうです。つまり「ほぼイコール日本で16軒です」と谷村さん。
谷村さん「それぞれの家で規模があります。茶筅づくりは分業で、工程ごとに分かれていて、それぞれに専門の職人さんがいて、職人さんを何人抱えているかでその家の生産する本数が変わってきます。
うちの家ではすべての職人さんが10人ほどいまして、だいたい平均して1日20~30本くらい作ります」
秘密から公開へ
谷村さんが作っている茶筅には特徴がありますか?
谷村さん「茶筅は種類は決まっていて、それは何百年も前からこの流派はこの形と決まっていて、それを16軒の家で同じものを作っています。多少作る家によって特徴、個性があります。
理想的な茶筅は丈夫でしなやかな茶筅となりますが、それを目指して、日々自分でも使い心地を試しながら作っています」
茶筅の作り方は昭和30年代までは秘密だったそうですが、その後、作り方自体は公開されているそうです。
谷村さん「ですからYouTubeでも作業工程が説明されていたりします」
公開された背景を尋ねると…
谷村さん「われわれの両親の時代ですが、いろいろ葛藤はあったと思いますが、茶筅という道具は、最近まで茶道をする人だけの道具でした。しない人には関係のない道具だし、使ったこともない人がほとんどでした。
茶道という道具の中では、値段でいうと一番下くらいで消耗品でした。ポジションとしては非常に低い位置にあったので、それを公開することで、少しでも値段を高く買っていただけるように、いかに手間がかかっているかということをアピールしたかったのだと思います」
しなやかさと丈夫さと
谷村さん「もちろんそれぞれの工程、全部難しいですが、特に真ん中くらいの工程で味削りという工程があり、これは竹を薄く削ることによってしなり、ばねを生むための作業です。
茶筅は消耗品ですから長持ちする方がいいですが、そうすると竹を削る量をちょっとにして穂先を厚めにしておいたほうが折れにくい。
ところが厚すぎるとしならない。茶筅は穂先がしなることによって泡がたちます。薄いとよくしなりますが、薄すぎると今度は耐久性が落ちます。
しなやかさと丈夫さは相反しますが、そのバランスをどこでとるかが非常に大事になってきます」
最後に、この世界的な人気についての感慨を尋ねました。
谷村さん「現在、世界中の方々が抹茶を飲まれ、茶筅を使っていただいているという非常にありがたい状態が続いています。今まで使ったことのない人、抹茶を飲んだことがない人が、また新しくその世界に入っていただけるように情報を発信していきたいですし、奈良の高山町で実際に作業の様子をご覧いただけたらうれしいです」
(みず)
番組紹介
読んで聴く、新しい習慣。番組内容を編集した記事からラジオ番組を聴いていただける”RadiChubu”。名古屋を拠点とするCBCラジオの番組と連動した、中部地方ならではの記事を配信する情報サイトです。