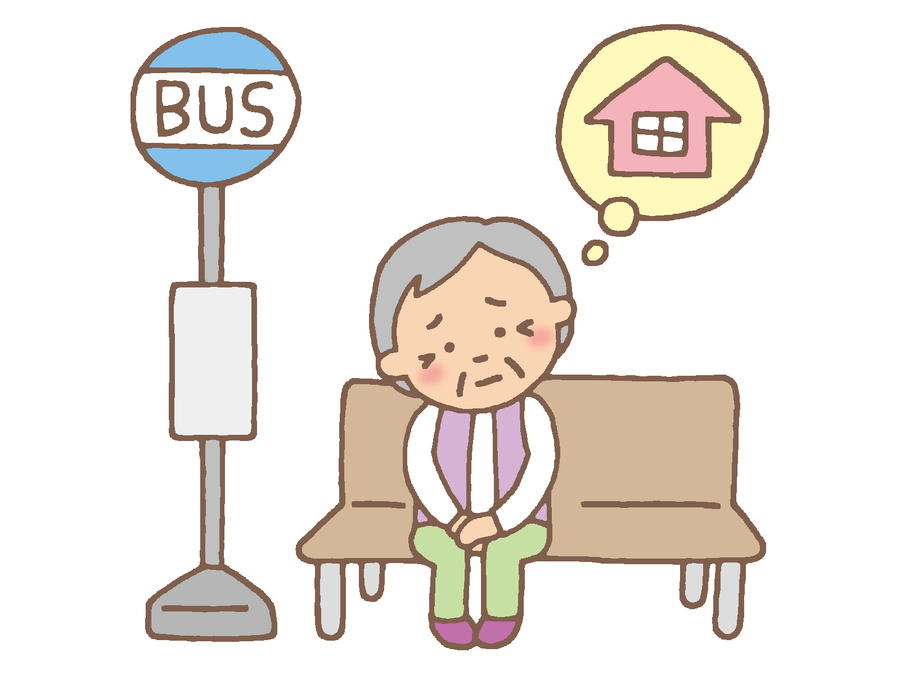なぜ女性は髪を染める?ホーユーヘアカラーミュージアムに見る髪色と社会進出の歴史

8月27日放送のCBCラジオ『北野誠のズバリ』。「松岡亜矢子の地元に聞いちゃうぞ」のコーナーでは、日本で唯一のヘアカラーに特化した企業美術館「ホーユーヘアカラーミュージアム」(名古屋市東区)で開催中の企画展を紹介しました。髪を染める文化の変遷から見える、日本人の美意識と女性の社会進出の歴史とは。
関連リンク
この記事をradiko(ラジコ)で聴く日本唯一のヘアカラー専門美術館
ホーユーヘアカラーミュージアムは、「ビゲン」や「シエロ」などのブランドで知られるホーユー株式会社が運営する、ヘアカラーの歴史や文化を発信する施設。2023年5月に徳川美術館の南隣にオープンしました。
8月31日まで開催中の企画展「ヘアカラー展 なぜ染める、なぜ染まる。」では、ヘアカラーの時代による変化や、ヘアカラーの染まり方といった科学的な側面など、多角的な視点で解説しています。
黒髪神話から茶髪ブームへ
松岡が特に注目したのは、「大衆文化としてのヘアカラー」という展示。日本では長い間、髪を染めることは黒く染めることを意味し、その文化が昭和初期まで続いていました。
古代から、自然に伸びる髪の毛は神秘的で生命の象徴とされ、逆に白髪は老いの象徴として避けられてきました。そのため昭和初期まで、髪を染めることはイコール黒く染めることを指していたのです。
転換期となったのは戦後の生活様式の変化でした。女性の服装がモンペから活動しやすい洋服に変わると、重たい黒髪が洋服に合わないと感じるようになります。
女性たちが髪を短くし始めるとともに、真っ黒な髪色から自然な栗毛色が注目されるようになっていったのです。
芸能界が牽引したヘアカラー革命
戦後のトレンドは芸能界とテレビで、ここからたくさんのものが生まれました。
展示では、芸能界と髪色の歴史を表す「若者カルチャーと髪色にまつわる年表」が大きく掲げられていました。特に大きなターニングポイントとなったのが、昭和44年に「新宿の女」でデビューした藤圭子さんでした。
当時では珍しい、明るい髪色に白いギターを抱えた姿でLPジャケットに登場したことが、美容業界にとってターニングポイントに。その後、C-C-BやX JAPAN、聖飢魔Ⅱなど、黒以外のカラーリングをしたアーティストが続々と登場し、それに憧れる若者たちが増えていきました。
1990年代に入ると、松岡にとっても外せない存在の安室奈美恵さんが登場。ミニスカートに厚底ブーツそして、明るい髪色の長い髪がトレードマークの「アムラーブーム」がやってきます。
それまで金髪は「不良のアイコン」とされていましたが、安室奈美恵さんの存在により、「おしゃれな女の子の象徴」へと変化していったのです。
時代を映す髪型トレンド
企画展では髪色だけでなく、流行の髪型もマネキンで展示されていました。
80年代を代表するのは「聖子ちゃんカット」、90年代は「前髪立ち上げバブリーヘア」、2000年代には「PUFFY風ワッフルパーマ」が流行。
また、元サッカー選手のデビッド・ベッカムの「ベッカムヘア」、藤原紀香さんの「紀香ヘア」も人気でした。
髪染めと女性の社会進出
企画展のタイトルにもなっている「なぜ人は髪を染めるのか」という問いに対し、展示では興味深い視点が示されていました。近代における髪を染める歴史は、「女性の社会進出の歴史」といっても過言ではありません。
2021年~2024年の統計(中学生~80代半ば)によると、「これまで髪を染めたことがある」と答えた女性は全体の8割に対し、男性は2割しかいないことがわかりました。
この違いの背景には、日本における美容師の先駆者である山野愛子さんが海外で学んだ美容技術を日本の女性たちに向けて新たな美の価値観を発信していたことや、男女雇用機会均等法の施行が大きく影響しているといいます。
ヘアカラーは「老いを遠ざけるもの」から、「自己表現のツール」へと変化していったのです。
ホーユーヘアカラーミュージアムの「ヘアカラー展 なぜ染める、なぜ染まる。」は、8月31日まで開催中。開館時間は午前10時から夕方5時まで。休館日は月曜・祝日と年末年始で、入場料は無料です。
常設展示にはAIシミュレーターで自分に似合う髪型と髪色の疑似体験ができるコーナーもあり、6パターンの髪型・髪色をAIが判断してくれるそうです。
(minto)
番組紹介
読んで聴く、新しい習慣。番組内容を編集した記事からラジオ番組を聴いていただける”RadiChubu”。名古屋を拠点とするCBCラジオの番組と連動した、中部地方ならではの記事を配信する情報サイトです。