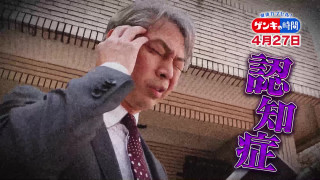“治らない口内炎”放置で「舌がん」に!?…危険な病気の可能性も!「口トラブル」原因と対策

身近な健康問題とその改善法を、様々なテーマで紹介する番組『健康カプセル!ゲンキの時間』。
メインMCに石丸幹二さん、サブMCは坂下千里子さんです。
ドクターは、新横浜歯科衛生士・歯科技工士専門学校 学校長 歯学博士 中川洋一先生です。
今回のテーマは「〜身近な異変に意外な病気が〜災いの元・口トラブル」
口内炎、口の中を噛む、口の中が乾く、など多くの人が悩んでいる「口トラブル」。番組で20〜80代の男女60人に調査したところ、気になる症状があると答えた人は実に9割以上にものぼりました。口のトラブルは、危険な病気が隠れている場合もあり、がんが見つかるケースもあるそうです。そこで今回は、さまざまな口トラブルの原因と対策を専門医に教えてもらいました。
口トラブル(1)日本人の約800万人「ドライマウス」

<ドライマウスとは?>
ドライマウスとは、唾液の分泌量が減り、口の中が乾燥した状態のこと。日本人の約800万人がドライマウスと言われており、口臭・食べ物が飲み込みにくい・舌の痛み・味覚変化・声が出しにくいなどの症状を引き起こすそうです。
<ドライマウスのセルフチェック>
下記の項目に3つ以上当てはまる場合は注意が必要だそうです。
□ 乾いた物(パンなど)が食べにくい
□ 口の中やのどが乾燥する
□ 口の中が痛い
□ 夜、口の乾きで目が覚める
□ 味覚がおかしい
□ 口の中がネバネバする
<ドライマウスの健康リスク>
口は、ウィルスや細菌をブロックする第一関門。さらに、そうした外敵だけでなく、口の中にはレンサ球菌・黄色ブドウ球菌・カンジダ菌など、700種類以上の常在菌が存在しています。唾液には、それらから口や舌を守る役割があるため、唾液が減り傷つきやすくなると、防御機能が落ち、さまざまな感染症のリスクが高まるのだとか。逆に唾液が正常に分泌されることで健康を守ることにもつながるそうです。
<唾液が減る原因は?>
唾液腺は自律神経が刺激しており、自律神経のバランスで唾液の量は変化するそうです。緊張して口が乾くのは、交感神経が過度に優位になることで起こる身体的症状。休日は大丈夫でも、仕事のある平日は口が乾くという人もいるそうです。
<ドライマウスの対策>
唾液の分泌は味覚・咀しゃく・粘膜の3つの反射で行われているそうです。「味覚反射」は味を感じることで唾液が出る作用。どんな味でも良いですが、レモンなどの酸味は特に分泌を促すそうです。「咀しゃく反射」は、物を噛むことで唾液が分泌される作用。そして「粘膜反射」は、口腔内への刺激で唾液を出す作用。頬のマッサージや歯磨きなどでも効果が得られるそうです。
<先生オススメの唾液分泌法>
先生のオススメは、ガムやグミなどを食べること。味があるので「味覚刺激」になり、噛み応えがあるので「咀しゃく刺激」にもなります。さらに、口の中で頬に当たるので「粘膜刺激」も加わり、唾液が増えてくるそうです。
口トラブル(2)危険な病気の可能性も!?「口内炎」
<口内炎とは?>
口内炎は色々なところにできます。歯茎にできると「歯肉炎」、舌にできると「舌炎」、唇にできると「口唇炎」、口角は「口角炎」。口の中や周辺の粘膜で起きる炎症は、全てまとめて「口内炎」と呼ばれるそうです。
<口内炎の種類>
口内炎には、「アフタ性口内炎」「ウイルス性口内炎」「潰瘍性口内炎」「カンジダ性口内炎」と大きく分けて4つの種類があるそうです。できやすい場所によって原因も異なり、それぞれの原因にあった対処をすることが大切だそうです。
<最も一般的「アフタ性口内炎」の原因と対策>
アフタ性口内炎は最も一般的な口内炎で、見た目は主に楕円形で白いのが特徴。皮膚の上の皮が炎症を起こし、中の組織が露出した状態のため凹んだ見た目になるそうです。できやすい場所は舌・頬・歯茎。原因はハッキリと分かっていないそうですが、ストレスや疲れによる免疫力の低下、睡眠不足が引き金と考えられているのだとか。できた時の対処法は「刺激のある食事を避ける」「口腔内を清潔に保つ」ことで2週間程度で自然に治るそうです。
<小さな水疱に要注意「ウイルス性口内炎」の原因と対策>
ウイルス性口内炎(水疱性口内炎)は、ヘルペスウイルスなどの粘膜感染が原因で、水疱のような見た目をしています。できやすい場所は、喉の奥や唇。高熱・リンパの腫れ・強い痛みなどの症状が出る場合もあるそうです。口の中はいつも動いているので、水疱が出てもすぐ潰れてしまい、アフタ性口内炎のように見えるのだとか。ウイルス性口内炎は同時にたくさんできるのが特徴なので、アフタ性口内炎がたくさんできた場合は、ウイルス性口内炎が疑われるそうです。先生によると、自分で水疱を潰すのはNG。うがいや歯磨きで口腔内を清潔に保つことが予防につながるそうです。また、薬での治療が有効とのことなので、できた時は歯科・口腔外科を受診しましょう。
<常在菌が原因に「カンジダ性口内炎」の原因と対策>
カンジダ性口内炎は、口腔内の常在菌であるカンジダ菌が過剰に増殖して発症する口内炎。白い苔状のものや赤くただれたような見た目で、強い痛みを伴うこともあるのだとか。免疫力が下がった時などに発症しやすいため、睡眠や食事など、正しい生活習慣で予防できるそうです。もしできてしまった場合は、薬での治療が有効のため歯科・口腔外科を受診しましょう。
<「潰瘍性口内炎」の原因>
口の中を噛むことが原因でできるのが「潰瘍性口内炎」。できやすい場所は唇の内側や舌。噛む以外にも、火傷など物理的な刺激によって上皮が剥がれて発症するそうです。口の中を噛む原因の1つが筋肉の衰え。加齢によって口の筋肉が弱まってくると噛みやすくなってしまうそうです。
サインは「白板症」舌がん

白板症とは、口腔粘膜にできる白い病変。一見すると口内炎に見えますが、痛みはほとんどなく、日にちが経っても治らないという特徴があるそうです。先生によると、白板症は放っておくと舌がんになる恐れがあり、命にも関わる危険な症状。口内炎が2週間治らない場合は、病院を受診した方が良いそうです。
放っておくと命の危険も?口の機能低下「オーラルフレイル」
口の中を噛む原因は筋力の衰えですが、医学的には「オーラルフレイル」と呼ぶそうです。オーラルフレイルとは、加齢により口の機能が低下した状態のこと。嚥下障害やむせなどを引き起こし、放っておくと全身に影響することもあるのだとか。誤嚥などを引き起こす可能性もあり、命にも関わる危険な症状だそうです。
<オーラルフレイルのサイン>
・以前より硬い物が噛みにくくなった
・食べ物を飲み込むのが難しくなった
・口の中が乾燥する
・舌がもつれる
・食べこぼしが増えた
・むせやすくなった
オーラルフレイル改善の最前線
<口から身体を元気に!「声磨き(R)」>
声磨きとは、オーラルフレイルなどを改善するトレーニングのこと。口内環境の改善や嚥下機能の向上、さらには免疫力アップも期待される今大注目のシニア向け講座です。地方自治体をはじめ、カルチャースクール、老人クラブ連合など、日本全国で年間1000講座以上行われています。(※「声磨き」は一般社団法人日本声磨き普及協会の登録商標です)
<おうちでできる!簡単声磨き>
≪発声の基本「呼吸法」≫
▼腰の幅に足を開き 身体が一直線になるように立つ
▼まずは息を吐き切る
▼鼻から息を吸って口から吐き出す
ポイントは、「前に向かって」「一定量で」「息を出し切る」ことだそうです。
≪発声法≫
▼目の前に壁があるイメージで 両手で押しながら「あー」と声を出す
ポイントは、口は大きく開き、声を押し出すイメージで発声することだそうです。
≪口の動かし方≫
あ:指が縦に3本入るくらい広げる
い:口角を真横にグッと広げる
う:上唇の前の口輪筋を前に突き出す
え:頬の下を斜め上にあげる
お:頬が付くくらいすぼめる
▼口を大きく開き声を押し出すイメージで「あ・い・う・え・お」と発声する
ポイントは、顔全部が口だと思って発声すること。1日1回でもOK!隙間時間などに無理なく継続することが重要だそうです。
(2025年5月11日(日)放送 CBCテレビ『健康カプセル!ゲンキの時間』より)
番組紹介
ニッポンの皆様に健康生活を!この言葉をキーワードにすぐに役立つ健康情報をお伝えします。「人」「家族」の未来を創り出す、CBCテレビの健康情報番組。