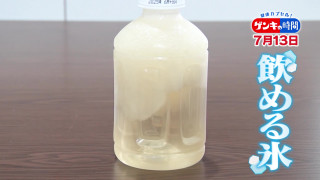現役世代も注意!サイレントキラー「心臓弁膜症」…息切れ・動悸がなくても危険!?心臓弁膜症の恐怖

身近な健康問題とその改善法を、様々なテーマで紹介する番組『健康カプセル!ゲンキの時間』。
メインMCに石丸幹二さん、サブMCは坂下千里子さんです。
ドクターは、ニューハート・ワタナベ国際病院
総長 医学博士 渡邊剛先生
副院長 医学博士 石川紀彦先生です。
今回のテーマは「〜息切れ・動悸がなくても危険!?〜サイレントキラー!心臓弁膜症」
最近よく耳にする心臓の病気「心臓弁膜症」は、血流をコントロールする心臓の弁が閉じなくなったり、逆に開かなくなったりする病気。心臓に関わる手術の中で、高齢化に伴い患者数が増えていることで今注目されています。放置すると徐々に心臓の機能が衰え、死につながることもあるそうです。心臓弁膜症の最も恐ろしいところは、自覚症状が無く突然亡くなり、後に原因が心臓弁膜症だったと判明することもあること。音もなく忍び寄り、命を奪っていくこともあるこの病は「サイレントキラー」とも呼ばれているそうです。そこで今回は、心臓弁膜症の手術に密着し、その恐怖について専門医に教えてもらいました。
心臓弁膜症の基礎知識

<心臓の弁の役割>
心臓は「右心房」「右心室」「左心房」「左心室」の4つの部屋に分かれており、各部屋の出口には4つの扉、弁があります。心臓は、弁があることで酸素を含んだ血液を全身へ送り、二酸化炭素を含んだ血液を肺へ送る、という一連の動作を一方向に効率よく行うことができるそうです。
<65歳以上の10人に1人に心臓弁膜症のリスク>
心臓弁膜症の有病率は年齢とともに上がる傾向にあります。潜在患者数は、65〜74歳では約140万人、75歳以上では約260万人。実に65歳以上の10人に1人に心臓弁膜症の潜在的なリスクがあると言われているのだとか。心臓弁膜症の中でも患者数が多いのは「僧帽弁閉鎖不全症」と「大動脈弁狭窄症」の2つだそうです。
<虫歯が弁を壊す!?「感染性心内膜炎」>
心臓弁膜症は、加齢だけが原因ではないそうです。例えば、「感染性心内膜炎」は血液の中に虫歯の原因菌などが入り、心臓の弁に感染することで発症。弁を壊し、心臓弁膜症を引き起こすこともあるのだとか。そのため、虫歯にも注意が必要だそうです。
現役世代も注意!「僧帽弁閉鎖不全症」
<僧帽弁閉鎖不全症とは?>
僧帽弁は、血液が逆流しないようにしっかり閉じるようになっていますが、「僧帽弁閉鎖不全症」は、何らかの理由で僧帽弁が閉じにくくなり血液が逆流してしまう病気だそうです。
<健康診断で見つかる人が約8割>
僧帽弁閉鎖不全症が見つかるきっかけの1つが「心雑音」。心雑音とは、心臓から聞こえる異音のことで、血液が逆流することで雑音が発生するのだとか。先生によると、健康診断で「心雑音がある」と言われ僧帽弁閉鎖不全症が見つかる人が約8割だそうです。
<疲れ・息切れ 歳のせいにしていませんか?>
僧帽弁閉鎖不全症は徐々に進行するため身体の異変に気づきにくいそうです。なかには、「疲れやすい」「息切れする」などで異変に気づく人もいるそうですが、症状を感じていても年齢のせいにしている人が多いそうです。
<現役世代も注意!僧帽弁が閉まりにくくなる原因>
ポイントは「腱索」。腱索とは、僧帽弁とその下にある乳頭筋をつなぐ紐状の組織。心臓の拍動に合わせて腱索が引っ張られることで僧帽弁は開閉していますが、僧帽弁閉鎖不全症は腱索が切れたり緩んだりすることで起きているのだとか。原因は、事故などの外的ショック・細菌感染・先天性など様々。そのため、年齢にかかわらず誰にでも起きる可能性があるそうです。
<僧帽弁閉鎖不全症の治療法「僧帽弁形成術」>
僧帽弁閉鎖不全症の治療法の1つが、手術支援ロボット「ダヴィンチ」を用いた「僧帽弁形成術」。一般的な手術は「正中切開」と言って胸骨を縦に切開するため、胸の正面に約15〜20cmの傷痕がつきますが、この手術では約1cmの穴を3か所あけて行われます。身体への負担が少なく、回復も早いのが最大のメリット。この手術の主な目的は、弁を取り替えるのではなく、特殊な糸を使った弁の修復。手術支援ロボットを用いることで緻密で正確な手術を行うことができるそうです。
突然死の危険も!大動脈弁狭窄症

<大動脈弁狭窄症とは?>
大動脈弁狭窄症とは、血液の圧力で開閉する3枚で構成された大動脈弁が、石灰化や動脈硬化などの影響でうまく開かなくなり血流が滞る疾患。この病気の怖いところは、無症状が長く続き症状が出た時には失神、最悪の場合突然死など、急に死亡リスクが上がることだそうです。
<大動脈弁狭窄症の治療法(1)「大動脈弁形成術」>
大動脈弁狭窄症の治療法の1つが手術支援ロボット「ダヴィンチ」を用いた「大動脈弁形成術」。心臓が見えるよう胸の下を約5cm切開し、硬くなった弁をとり、新たに作ります。心膜という心臓を覆う膜をはがし、新しい3枚の弁の素材として使用するのだとか。自分の組織を使うため拒絶反応がほとんどなく、術後に抗凝固薬を飲み続ける必要がないそうです。
<大動脈弁狭窄症の治療法(2)「大動脈弁置換術」>
一般的な大動脈弁狭窄症の治療法が「大動脈弁置換術」。機能が衰えた大動脈弁を人工弁に置き換えます。置き換える弁はカーボン製などの「機械弁」や豚や牛の心膜を使用した「生体弁」の2種類があり、それぞれにメリットとデメリットがあるのだとか。また、2024年からダヴィンチを使った人工弁置換術も保険適用になったそうです。詳しく知りたい場合は、専門の医療機関にお問い合わせください。
<「機械弁」と「生体弁」のメリット・デメリット>
・機械弁 メリット:一生持つ
デメリット:抗凝固薬を飲み続ける必要がある
・生体弁 メリット:抗凝固薬を飲み続けなくていい
デメリット:耐用年数10〜20年程度
1年に1回健康診断を受けましょう
心臓弁膜症は自分では気づきにくい病気ですが、健診に行けば心雑音ですぐに分かるそうです。治療可能な病気なので、ぜひ1年に1回は健康診断を受けましょう。
(2025年8月10日(日)放送 CBCテレビ『健康カプセル!ゲンキの時間』より)
番組紹介
ニッポンの皆様に健康生活を!この言葉をキーワードにすぐに役立つ健康情報をお伝えします。「人」「家族」の未来を創り出す、CBCテレビの健康情報番組。