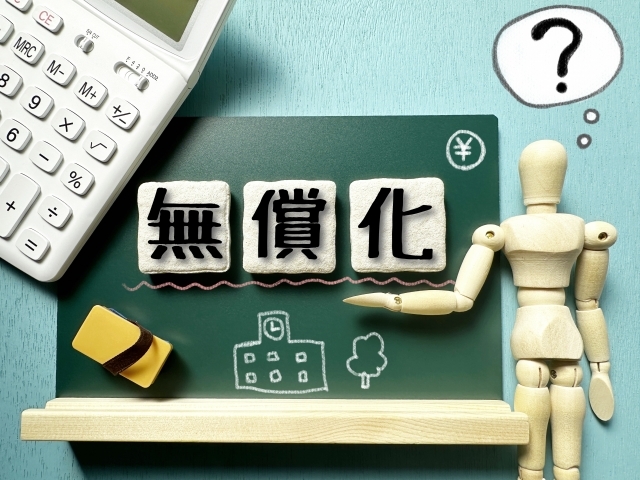「盛大な葬式」の遺言、守る必要ある?法的効力を弁護士が解説
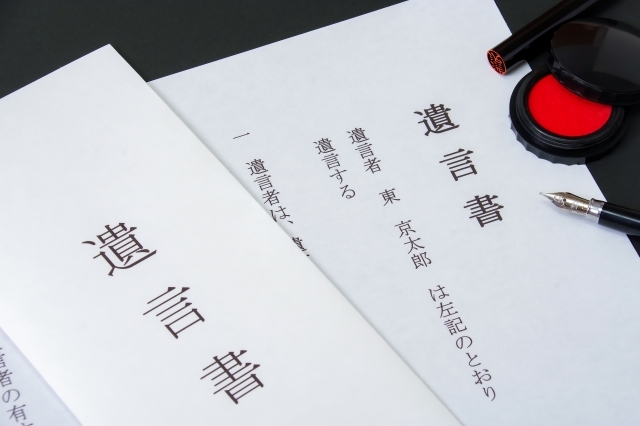
4月9日放送の『北野誠のズバリ』。法律に関する疑問・質問・お悩みを解決する「ズバリ法律相談室」のコーナーには、「家族が遺言で“盛大な葬式”を希望しているが、家族葬にしても法的に問題はないのでしょうか」という質問が寄せられました。遺言通りにしなかった場合、何か問題はあるのでしょうか?遺言と葬儀の関係について、オリンピア法律事務所の原武之弁護士が解説しました。
関連リンク
この記事をradiko(ラジコ)で聴く遺言で葬儀の形式を指定できる?
「私の義理の父が、『もし自分が亡くなったら盛大な葬式で送ってほしい』」と言っています。私の妻が喪主になると思います」(Aさん)
Aさんと妻は費用面から「簡単な家族葬」を考えているそうですが、義理の姉たちは義父の思いを汲んで、「たぶん無責任に反対すると思う」というのです。
故人の遺志が遺言的な形で残されていた場合、そこを無視して簡単に済ませたら、問題になることはあるのでしょうか?」(Aさん)
この質問に、原弁護士は「遺言には2種類ある」と説明します。
遺言事項と付記事項の違い
ひとつは「遺言事項(いごんじこう)」と呼ばれるもので、誰に相続分を渡すかなど法的に守らなければならない部分。
もうひとつは「付記事項(ふきじこう)」と呼ばれるもので、故人の思いや希望を伝えるだけの、法的な拘束力のない部分です。
葬儀のやり方は「遺言事項」ではなく「付記事項」に該当します。原弁護士によると「盛大に」という表現は抽象的でもあり、「尊重すればいいぐらい」とのこと。
つまり、故人が遺言で盛大な葬式を希望されていても、家族葬にしても法的には問題ないということです。
遺言の効力と限界
「葬儀に関して遺言に書かれていても、影響力はあまり気にしなくていいんですか?」という北野誠の問いに、原弁護士は「祭祀承継(さいししょうけい)」という言葉を挙げました。
「墓守(はかもり)や法事などを誰がやるか」という指定は遺言事項なので守る必要がありますが、葬儀の規模や内容については遺族の判断に委ねられるとのことです。
原弁護士は「葬式は結局、誰のためなのかということにもなる」と指摘し、どのように葬儀を行なうかは遺族にも影響することであり、費用面も考慮すれば拘束力はないと説明しました。
「葬式なし」でも火葬は必須
遺言に「葬式をしないでほしい」と書かれていた場合、葬儀を行なわなくても法的には問題ないそうです。
ただし、遺体の扱いについては別の法律で規定されており、基本的には火葬を行なう必要があります。現代の日本では99パーセントが火葬だそうです。火葬と埋葬許可は行政の問題です。
北野「『山の上において鳥葬(ちょうそう)してくれ!』って書いてあっても…」
原弁護士「鳥葬は今ダメなので(笑)」
北野「死体遺棄問題?」
一部の地域では土葬が認められているものの、日本では基本的に火葬が義務づけられています。
お骨の管理と代替策
お骨の管理については意外にも決まりが少なく、お墓に入れたくない方や、自宅で保管したいという方も少なくありません。
「すぐにお墓に入れるのに抵抗があるため、自宅の仏壇に飾る方もいます」と現代の多様な選択肢について説明しました。
Aさんのケースについて、原弁護士は葬儀の形式に法的拘束力がないことを踏まえ、よく話し合って家族葬への理解を求めることを提案します。また、「盛大に」という希望の意図が多くの人を呼びたいということなら、後日「お別れ会」を開催するという代替案も示しました。
お葬式は急な開催で参列者を集めにくいという現実的な問題もありますが、お別れ会であれば準備の時間も取れるため、思い出も語れるという利点があるとのことです。
遺骨の希望は拘束力があるのか
「自分の骨はどこそこの場所に入れてほしい」という希望は、法的には微妙な問題があるようです。
原弁護士は「祭祀の一部としてみれば、お墓に入れてくれと言われたら入れなければいけないと思うが、お骨の管理は誰が所有者かという点が難しくて、議論がある。バラバラにされてしまう方もいる」と説明しました。
北野「俺も一部骨はCBCの片隅に埋めてもらおう。みんな『どうすんねんこれ!』って(笑)」
遺言で葬儀の形式を指定されても、それは遺族の意向で変更可能だということがわかりました。「盛大にして欲しい」という希望には「お別れ会」という別の形で応えるのもひとつの解決策かもしれません。
(minto)
番組紹介
読んで聴く、新しい習慣。番組内容を編集した記事からラジオ番組を聴いていただける”RadiChubu”。名古屋を拠点とするCBCラジオの番組と連動した、中部地方ならではの記事を配信する情報サイトです。