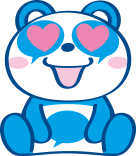国は「備蓄米」の放出方針を決定、“令和の米騒動”半年たっても収束せず

米を取り巻く環境は依然として厳しい。2024年(令和6年)夏に、店頭から米が姿を消して、さらに価格も高騰したため、「令和の米騒動」などという言葉が飛び交った。当時「秋になれば新米が登場して値段も落ち着く」と言われていたが、半年たっても好転の兆しはない。
初の「備蓄米」放出へ
政府は、今後も米の高騰が続くと見られることから、「備蓄米」の放出を決めた。「備蓄米」は、凶作や不作に備えて、一定の量の米を“国として”ストックするもので、1993年(平成5年)に米が不足した、いわゆる「平成の米騒動」をきっかけに始めた。「10年に1度の不作」を想定して、およそ100万トンの米を保存してきている。今回、この「備蓄米」を柔軟に市場に出すことにして、2025年(令和7年)1月末に発表した。初めてとなる“歴史的な方針転換”の背景には、米の価格の高止まりがある。
国がコントロールする米
日本に稲作が伝わったのは、1万3,000年前からの縄文時代と言われる。それ以来、米は日本人の主食となった。その米を守るため、その価格には国が深く関わってきた。米の値段は、古くから“御上(おかみ)”が決めてきたのである。奈良時代には、米を保存する「倉」が日本各地にあって、皇族や貴族が、豊作ならば米を溜めて、凶作ならば米を出して、暮らしを安定させてきた。
パン食によって米に変化
米を取り巻く食生活に変化が現れたのは、戦後である。アメリカなど欧米の文化が入り、日本人にもパンを主食とする人が増えてきた。このため、米が余るようになった。それによって米の価格が暴落することを守るために「食糧管理制度」ができた。1960年代には、米を作り過ぎないようにコントロールする「減反政策」も始まった。しかし、同時に「自主流通米」という、それまでは政府以外には認めていなかった売買を改めた制度も始まり、農家は直接、米を消費者に売ることも可能になった。
農家が自分で値段を決める

この「自主流通米」が、米の価格の長い歴史に風穴を開けた。1990年代に入ると「自主流通米」が増えて、今度は、国が管理する米の割合が減り始めた。そして、1995年(平成7年)に、大きな節目が訪れた。「食糧管理制度」が廃止されて、農家は自由に米を販売できるようになり、その値段も“自由競争”になった。自らの田んぼの横に米の直売所を設けたり、インターネットで販売したり、「自分で自分の米の値段を決めて売る」時代が到来した。
コントロールは継続中
しかし“自由競争”と言っても、現実には国による“管理”は続いた。全国で米の流通の半分を扱うJAなどが、新米の収穫を前に、需要と供給の環境や生産コストを踏まえて「概算金」という価格を決める。言わば「予定価格」である。各地のJAは、それをもとに経費などを踏まえて、生産農家に支払う金額を決める。これが「相対取引価格」言わば「卸し価格」である。この「予定価格」と「卸し価格」によって、米の値段は農林水産省によってコントロールされているのだ。
日本の米に2つの異変

この「卸し価格」に異変が生じたのが、2024年だった。ここ10年ほど大きな変化はなかったが、秋の新米に、前の年よりも5割以上高い値がついた。1俵60キロとしておよそ2万5,000円、最近では4万円超えもお目見えした。理由は2つ考えられる。この2年ほどの猛暑、これによって、米の生育が大きな影響を受けた。もうひとつ、新型コロナ禍が節目を迎えて、インバウンドによる和食人気。国内の“おにぎり店ブーム”も加わって、外食産業が米の販売で優先されて、需要と供給のバランスが崩れた。「新米が出れば、米は十分に出回る」と言われてきたが、業者の間の調達競争もあって、米の値段は“高止まり”している。
農林水産省は、流通の状況を見極めながら「備蓄米」の放出時期や量など調整を進めている。しかし、出し過ぎると米の値段が下がり過ぎて、米農家の反発も必至である。消費者にしっかり米を届けること、同時に、米を作る農家を守ること、この2つのバランスを取る、極めて難しいステージが始まった。日本人の主食として長い歴史を歩んできた米は、今、大きな転換点を迎えている。
【東西南北論説風(555) by CBCマガジン専属ライター・北辻利寿】