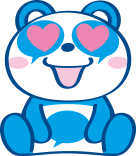本能寺の変から“逃げた”と云われた信長の弟 ~織田有楽斎の人物像


織田信長の弟、織田長益(おだ ながます 1547~1622年)は、茶人有楽斎(うらくさい)として知られている。
皇居の南東、丸の内の南側に位置する「有楽町」。俗説とも云われるが、千代田区のホームページに「『有楽町』の名前は、戦国時代に活躍した武将、織田信長の弟、織田有楽斎(長益)に由来します。茶人としても名をはせた有楽斎は関ヶ原の戦いのあと、徳川家康方に属し、数寄屋橋(すきやばし)御門の周辺に屋敷を拝領しました。その屋敷跡が有楽原と呼ばれていたことから、明治時代に『有楽町』と名付けられたのです」と記されている。
天文16年(1547年)織田信秀の11男として、尾張末森城(現在の名古屋市千種区)に生まれた長益は、13歳違いの兄 信長とともに戦場を往来したのであろうが、その戦歴はあまりはっきりとはしていない。
しかし、本能寺の変から“逃げた男”という不名誉で、後世、長益の名は知られるようになる。
当時、長益は、信長の長男 信忠に仕えており、明智光秀が本能寺に信長を襲ったことを聞いた信忠に従って、二条御所で光秀の攻撃に備えた。信忠の手勢は、ほどなく攻め寄せた光秀軍と奮戦したが力及ばず、信忠は自害したが、そこから長益は脱出、安土城を経て岐阜まで逃れた。
当時、長益が信忠に自害を勧めておきながら自らは脱出したとされ「織田の源五(長益のこと)は人では無いよ、御腹召せ召せ召させておいて、我は安土へ逃ぐるは源五、六月二日(本能寺の変当日)に大水出て織田の原なる名を流す」と京童(きょうわらべ)に嘲笑されたという。

このエピソードは16世紀末頃に成立した本に書かれ、そののち長益は豊臣秀吉に仕えた。関ヶ原の戦いでは東軍として戦い、引き続き豊臣秀頼に仕えたが大坂夏の陣の直前に大坂城を去った。“逃げの有楽” “世渡り上手”とも評されるところだ。
しかし、太平の世になって戦国時代の価値観が激変するなか、数奇な運命に翻弄されながらも「生き抜くことの方が、よほど苦難の道ではなかったか」と、晩年の有楽斎の隠棲地の伝統を受け継ぐ正伝永源院 真神啓仁住職は語る。
現在、愛知県犬山市にある国宝の茶室「如庵(じょあん)」、有楽斎が用いた水指(みずさし、茶に用いる水を入れる器)「緑釉四足壺」(重要文化財 慈照院蔵)、東京国立博物館に所蔵される茶碗「有楽井戸」(重要美術品)、そして自作の茶杓(根津美術館所蔵)、いずれも晩年、有楽斎と名乗った長益の美意識を表す品々である。
それまで「タテ社会」でしかなかった人間関係に、中世末期、自治的・地縁的結合による共同組織、連帯して一揆さえ起こす「ヨコ社会」が生まれた。茶もその一端であり、個人の美意識の表現もこの時代に生まれてくる。秀吉と利休の拮抗もそのせめぎ合いではなかったのではないだろうか。
太平洋戦争でもそうだったように、近代の“機能的な”戦争とされるものは兵士を“単位”として扱い、その個性を顧みない。信長もまたそうであったがゆえに中世を打ち破ったのだ。茶においても信長は、それを美意識の表現とはせず、茶道具は褒賞あるいは権威の表現に過ぎなかった。
長益の“茶”はそうではなかった。戦いのなかの内省であり、心の連帯であったと思う。本能寺の変、関ケ原の戦い、大坂夏の陣… 織田家の一員として、否応なく長益は関わらざるを得なかった。しかし、長益の心はそこに無かったのではないか。
「春秋に義戦無し」という。戦いはすべて自らの利益の拡大のためのもの、そのようなことに命を捨てられぬ、私は“茶”という表現において、この世に生きる喜びや悲しさを味わい、伝えるのだ。有楽斎と名乗った長益の“茶”はそうあったと思う。
“茶”は今日ライフスタイルのように云う“茶道”ではない。当時禁制となりつつあったキリスト教信者のように、命すら賭ける“矜持”だった。

折しも今年は有楽斎没後400年であり、記念の特別展「大名茶人 織田有楽斎」が京都文化博物館で開催されている(6月25日まで、2024年1月31日から東京 サントリー美術館へ巡回)。その会場に展示されている肖像画の有楽斎は、過ぎ去った戦乱の世を遠く見ているように思われる。
同じ会場に有楽斎宛の書状が展示されている伊達政宗は、晩年「馬上少年(ばじょうしょうねん)過ぐ(戦いのうちに若き日は過ぎ去った)」と詩を詠んでいる。その詩に言う。「残躯(ざんく)天の赦(ゆる)す所、楽しまずして是(これ)を如何(いか)にせん(幸いにして得た余生に感謝して、悠々と残日を楽しもうではないか)」
この感慨は政宗のみならず、長益や戦国時代を生き残った武将たちすべてのものであったであろう。
参考文献:
展覧会図録「大名茶人 織田有楽斎」読売新聞社
【by CBCテレビ解説委員・北島徹也】