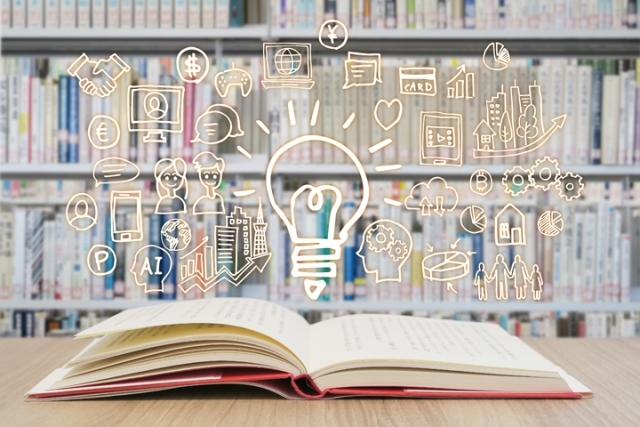深海生物の採取方法は?水の管理は?驚いた餌とは?名古屋港水族館の裏側に迫る

11月24日放送の『CBCラジオ #プラス!』では、名古屋港水族館の坂岡賢さんをゲストに迎え、光山雄一朗アナウンサーと三浦優奈が、水族館の裏側について聞きました。深海生物の採集方法、水槽の素材や温度管理、さらには意外な餌やりまで、水族館の知られざる裏側を紹介です。
関連リンク
この記事をradiko(ラジコ)で聴くルートはどこ?
名古屋港水族館には500種・5万点の生き物が飼育されています。
坂岡さんによると、それらの生き物は近くの海から採取するものから海外からやって来る生物まで、さまざまなルートがあるそうです。
特に深海生物については「深海は宇宙より難しいと言われるほど環境が厳しい」と話し、水圧変化に配慮しながら“ゆっくり引き上げる”ことで生き物を健康なまま展示へ導く工夫があることを明かしました。
水槽の数と素材
光山が「水槽はいくつあるのか」と尋ねると、坂岡さんは「数えきれないほど」と答えました。
来館者が見られるもの以上にバックヤードの水槽が多いとのこと。
新しく迎えた生き物の隔離や、体調不良の生き物の治療など、裏では多くの水槽が稼働し続けているとのことです。
三浦「これだけ水槽があると、じゃあ水の温度はどうやって管理しているのかなっていう」
水族館では家庭用の瞬間湯沸かし器と似た仕組みで温度を調整し、目標の水温を自動で保つようにしていると説明する坂岡さん。
光山「あれだけの水の量を囲っている水槽って、何の素材でできているのかなっていうのも気になるんですが」
実は大きな水槽はガラスではなくアクリル樹脂で作られているんだとか。
アクリルは厚さ40センチ近くにもなる重層構造で、加熱して曲げることも可能。
そのため、トンネル型水槽やアーチ状水槽など、多彩な形が作れるのだそうです。
掃除と餌やり
「水槽の掃除は毎日欠かせない」と坂岡さん。照明を当てることで早ければ30分ほどでコケが生えてしまうため、常に清掃が必要だと話しました。
餌に関しては「全体で何百キロ単位」とのことで、アジやホッケなどの魚類だけでなく、野菜を食べる生き物もいるため意外に種類が多いとのことです。
中でも坂岡さんが驚いたのは“クラゲがクラゲを食べる”という生態。
餌用のクラゲを大量に与えても翌日にはなくなっていることもあり、「クラゲがキノコのように膨らむ姿には驚いた」と振り返りました。
多くの生き物が展示されている名古屋港水族館。
その背景には、スタッフの専門的な作業と、生態の面白さがありました。
(ランチョンマット先輩)
番組紹介
読んで聴く、新しい習慣。番組内容を編集した記事からラジオ番組を聴いていただける”RadiChubu”。名古屋を拠点とするCBCラジオの番組と連動した、中部地方ならではの記事を配信する情報サイトです。