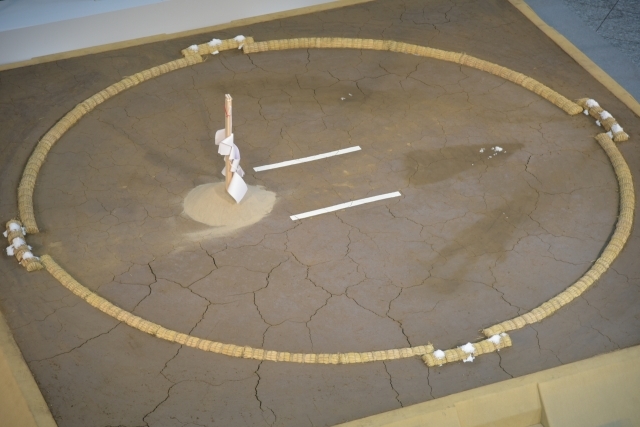「オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」月間が11月になった理由

11月は「オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」月間です。児童虐待の防止のため、どのような取り組みが行われるのでしょうか?11月5日放送のCBCラジオ『つボイノリオの聞けば聞くほど』では、つボイノリオと小高直子アナウンサーが児童虐待防止の取り組みについて紹介します。
関連リンク
この記事をradiko(ラジコ)で聴く「オレンジ色」は明るい未来の象徴
2000年11月、「児童虐待防止法」が施行されたことから、毎年11月が「オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」月間となりました。
オレンジ色はこどもたちの明るい未来を象徴しているそうです。
令和5年度の児童虐待相談件数は、前年度より1万件以上上回るおよそ22万5千件で、過去最多となりました。
つボイ「それぞれに出来る対策というのはどんなもんですかね」
虐待を疑うような出来事があった場合、どうすればよいでしょうか?
小高「どうしましょう?迷いますよね」
そのような場合、電話番号「189」にかけましょうと小高。
「いちはやく」という語呂合わせで覚えるとよいようです。
暴行なのかしつけなのか躊躇うような時、間違っていても本当の虐待を見落とすよりはいい、という考え方で行っているそうです。
サポートチラシを学校で配布
一方で、親にも子育てに余裕のない状態であることが想定されます。
つボイ「なんとかして、親子とも助けてもらえるところにつながってほしい」
また、誰にも相談できないようなお子さんの場合、学校で配られるサポートチラシに書いてある番号に電話したり、手紙を書いたりできるそうです。
さらにスマホをもっている場合は、「子どものSOS」で検索して相談も可能と小高。
小高「まず相談してくださいということなんです」
つボイ「自分ではおかしいな、と気づかないかもしれませんが」
先生でも相談窓口でもいいから話してほしい、とつボイ。
周りの人の配慮や声がけも大切
とりわけ、子育てで息苦しさを感じる人や、「これではダメだ」と子育てで思い詰めてしまう人ほど、黄色信号が出てしまうことがあります。
「通報するよりまず、周りの人が子育て中の人に対して優しい気持ちを持つことや、手を差し伸べてあげることが大切」と小高。
例えば電車にベビーカーで乗り込んだところ、赤ちゃんが泣き叫んでしまい、お母さんが責められるような事例を昨今よく耳にします。
そうした状況では、当事者は精神的にビクビクしてしまうため、周りの人たちには「赤ちゃんだから、いいよいいよ」と声をかけてあげるなど、温かく良心的な対応が求められます。
また、子育て中の生活音が環境問題として取り沙汰されることもしばしば。
それぞれ事情はあるとはいえ、他の家庭の生活音にある程度寛容になることも大事です。
小高「寛容になれるといいですね」
つボイ「虐待につながるようなことを減らせるかもしれません。他人に優しくするには余裕が必要です。皆さんがゆとりを持って生きられるように自治体に対策してもらいたい」
子育て世帯に冷たい日本社会の根本的な病理を指摘するつボイ。
社会が寛容に乏しくなるにつれ、虐待が起こるのかもしれません。
(nachtm)
番組紹介
読んで聴く、新しい習慣。番組内容を編集した記事からラジオ番組を聴いていただける”RadiChubu”。名古屋を拠点とするCBCラジオの番組と連動した、中部地方ならではの記事を配信する情報サイトです。