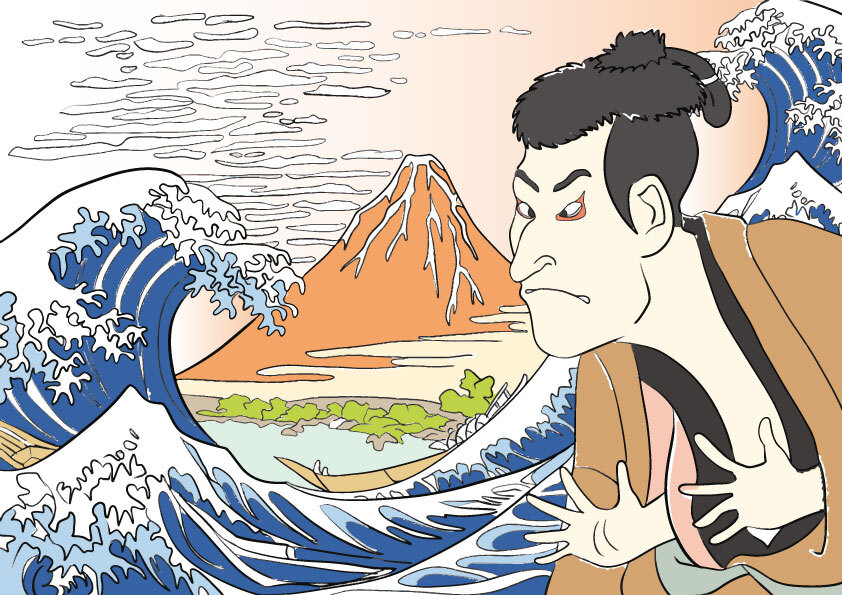歩道橋から国立競技場まで。日本に定着した「ネーミングライツ」

三菱UFJフィナンシャルグループが国立競技場の命名権(ネーミングライツ)を取得したと発表しました。10月20日放送の『CBCラジオ #プラス!』では、身近になったネーミングライツの仕組みと課題について、CBC論説室の石塚元章特別解説委員が解説しました。
関連リンク
この記事をradiko(ラジコ)で聴くネーミングライツとは何か
ネーミングライツとは、スポンサー企業の社名や商品のブランド名をつける権利のことです。そもそも物には名前が必要で、「誰がそれを名づけるのか」という命名権は、古くから重要なテーマとされてきました。
例えば天体の世界では、彗星は原則として発見者や関連の名前が自動的につくというルールがあります。話題のレモン彗星は、発見したアメリカのレモン山天文台の名前が由来です。
一方、小惑星は発見者が自由に名前を決められるため、James Bond(ジェームズ・ボンド)やTakoyaki(たこ焼き)、Hayamiyu(早見優)といったユニークな名前もあるといいます。
話題となっているネーミングライツは、公共施設などに企業がお金を払って名前をつける権利。名前をつける権利を買う側も売る側も、それぞれにメリットがある仕組みです。
売る側のメリット
今回、三菱UFJフィナンシャルグループが発表したのは、国立競技場が「MUFG国立」「MUFGスタジアム」になるということ。ただし「国立競技場」という正式名称は残り、これらの名前はニックネームとしての扱いになります。
売る側である施設側にとっては、まず財源が確保できることが大きなメリットです。
国立競技場の場合、契約は5年間で100億円といわれています。石塚によると、これは日本のネーミングライツ史上最高価格の可能性があるとのことです。
また、名古屋の「IGアリーナ」のように、すでに公共施設の運営権を民間企業グループに任せているケースもあります。
民間企業と協力体制を築くことで、運営面でも民間活力を導入できる可能性があり、地域全体の活性化にもつながることが期待されます。
買う側と地元住民のメリット
買う側の企業にとっては、やはり認知度の向上が最大のメリットです。
会社名や商品名が広く知られるようになり、企業価値の向上も期待できます。これまでネーミングライツに参入していなかった企業にとっては、全く新しい分野への挑戦の機会にもなります。
また、同業他社との差別化を図ることも可能です。物を売るだけでなく、スポーツや文化にも協力できる企業だとアピールできるという側面もあります。
地元住民にとっても、地域の活性化や地元イメージの向上が期待できます。収入によって老朽化した施設の改修や新設がしやすくなるという利点もあります。
デメリットや課題も
福岡出身の光山雄一朗アナウンサーは、福岡ドームがヤフオクドーム、PayPayドームと名前が変わり、現在はみずほPayPayドームという2つの企業名が入っている実例を挙げました。名称が変わるたびに、新しいサービスや企業の存在を知るきっかけになったと振り返ります。
しかし、あまりにも頻繁に名前が変わると混乱を招くこと、地図や道路標識の変更にコストがかかることも課題です。また、ネーミングライツの金額は基準があいまいで、年間数万円から数億円まで幅があるのが現状です。
利用者の立場からは「〇〇図書館でいいのになんで余計な企業の名前が前につくの?」「公共施設が宣伝に使われていいんですか」という批判の声もあるといいます。
さらに2つの企業名が入る場合、一方が不祥事を起こすと、もう一方にも影響が及ぶリスクがあります。
企業の経営状況の変化も課題です。石塚は、横浜の日産スタジアムについて、日産の経営状況を踏まえ次の契約が議題に上がっていると説明しました。
ネーミングライツの歴史
ネーミングライツの起源は19世紀末のアメリカにさかのぼります。富裕層が図書館や美術館に多額の寄付をした際、感謝の意を込めてその人の名前をつけたのが始まりとされています。
寄付者の中には、優しい気持ちで貢献した人もいれば、自分の名前を残すために資金を出した人もいたと石塚は推察します。
日本では、2003年の東京スタジアムが味の素と契約し「味の素スタジアム」となったのが、大規模施設での最初の例です。
最近では大規模施設だけでなく、より身近な場所にもネーミングライツが広がっています。
名古屋市内では歩道橋に企業名が入っているのを見かけます。東京の渋谷区では早くから公衆トイレに企業名やブランドマークが入り、その資金でトイレの整備が行なわれています。
身近に広がるネーミングライツ
ユニークな例では、大学の研究室や談話室にもネーミングライツが導入されています。たとえば東京理科大学の野田キャンパスでは、7号館1階の談話室が「日本総研PLAZA」と名付けられています。
鉄道の駅名にも広がりを見せており、富山の路面電車である富山ライトレールでは、すべての停留所にネーミングライツをつけました。その結果「トヨタモビリティ富山 Gスクエア五福前(五福末広町)」という日本一長い駅名も誕生したのです。
三浦優奈の友人は、約5,000円で小さな星の命名権を買ったそうです。
現代のネーミングライツ
石塚は、物事を識別するために名前が必要であり、その命名権をどう扱うかは重要な問題だと強調しました。権利者が命名権を売却し、購入者が対価を支払って希望の名前をつけるという仕組みが、現在のネーミングライツの基本的な考え方です。
ただし現代のネーミングライツは単に名前をつけるだけではありません。特に大規模施設では、パートナーとして企画や運営にも関わることが求められています。
国立競技場に企業名がつく時代。ネーミングライツは公共施設の新たな財源として、また企業の認知度向上策として、日本でも完全に定着しました。5年間で100億円という今回の契約は、その象徴的な出来事といえそうです。
(minto)
番組紹介
読んで聴く、新しい習慣。番組内容を編集した記事からラジオ番組を聴いていただける”RadiChubu”。名古屋を拠点とするCBCラジオの番組と連動した、中部地方ならではの記事を配信する情報サイトです。