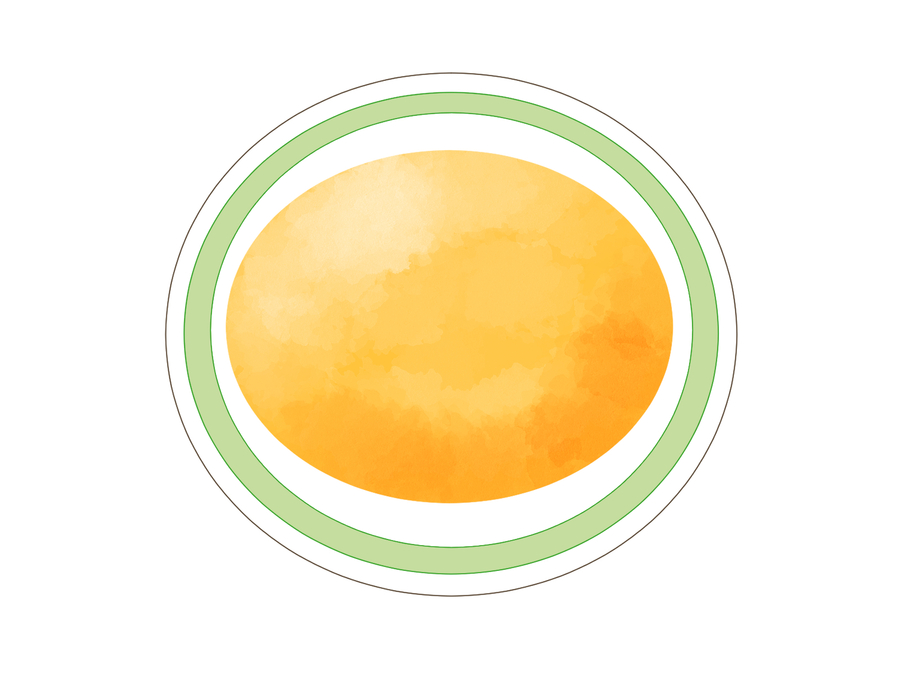実は後付けのネーミングだった?「月見商品」のルーツ

9月に入り、各飲食チェーン店では月見バーガーをはじめとする「月見商品」が続々と登場しています。今でこそ秋の風物詩としてすっかり定着した月見商品ですが、そもそもその始まりはどこにあったのでしょうか?9月2日放送の『CBCラジオ #プラス!』では、山本衿奈が光山雄一朗アナウンサーを相手に、月見商品の歴史について紹介しました。
関連リンク
この記事をradiko(ラジコ)で聴く初めての月見商品は後付けで生まれた!?
大手チェーン店で初めて登場した月見商品は、1991年にマクドナルドから発売された「月見バーガー」です。
意外なことに、当初から「秋=月見」「月見=卵」というイメージで開発されたわけではなかったとのこと。
ハンバーガーに入っていると嬉しい具材を調査した際、多くの声が集まったのが「卵」でした。
卵は秋に最も安定して供給できるという事情もあり、秋に卵入りのハンバーガーを出すことに。その際、「日本らしさを出せないか」というアイデアから、「月見バーガー」と名づけられたとのことです。
この月見バーガーをきっかけに、秋の定番としての月見商品が広がっていったとされます。
月見そばはいつ生まれた?
一方で、山本は「チェーン店の月見商品より、月見うどんや月見そばの方が歴史がありそう」と感じたとのこと。
調べたところによると、明治時代にはすでにそばの上に卵を落とす文化があったとされています。
それ以前は生卵の衛生面への懸念や、卵そのものが高価であったことから、卵を食卓に取り入れる機会は限られていました。
しかし明治時代以降、卵がより身近な食材になったことで、自然と「月見そば」のようなメニューが生まれていったと考えられています。
山本「昔から日本人は、何かに卵をトッピングするのが好きだった、ということなのかな」
卵かけご飯、どうやって作る?
話題は「卵かけご飯」にも及びました。
前日の夜、光山は卵かけご飯を食べていたそうで、山本に質問します。
光山「卵かけご飯、どうやって食べます?」
山本の食べ方は、卵を先にしっかりかき混ぜてから、白ごはんの上にかけ、さらに醤油をたらすという方法。
一方、光山はご飯の上に卵を割り入れて醤油をかけてから混ぜる派とのことです。
さらに光山の妻は、卵をあらかじめかき混ぜ、そこに醤油を入れたあと、ご飯を蓋のように上から乗せる食べ方をしているそう。
初めてこのスタイルを見た光山は「夫婦でも食文化が違う」と感じたと語っていました。
山本は「卵かけご飯ひとつでもいろんな食べ方がありますね」としみじみ。
ちなみに、現在卵の価格は10個入りで300円弱と高騰傾向。
今年の月見商品は、例年以上に贅沢な一品となりそうです。
(ランチョンマット先輩)
番組紹介
読んで聴く、新しい習慣。番組内容を編集した記事からラジオ番組を聴いていただける”RadiChubu”。名古屋を拠点とするCBCラジオの番組と連動した、中部地方ならではの記事を配信する情報サイトです。