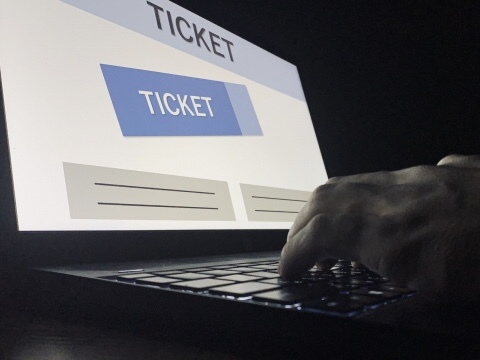海なし県・山梨のアサリ支出額が日本一!その歴史的背景

山梨県といえばブドウなど果物の産地として有名ですが、実は甲府市民のアサリに対する支出金額が全国1位という驚きの統計があります。8月21日放送の『CBCラジオ #プラス!』では、山梨県埋蔵文化財センター所長の森原明廣さんに、江戸時代から続く独特の食文化の歴史的背景を伺いました。
関連リンク
この記事をradiko(ラジコ)で聴く富士川舟運が支えた物流
完全な内陸県である山梨では、歴史的に海産物への憧れが強く、その中でもアサリは特別な存在だといいます。
アサリは魚とは違い、樽に詰めれば海水を満たした状態で海岸から山梨へ生きたまま運ぶことも可能。貴重な海産物のひとつとして珍重され、大事にされてきたという歴史があります。
そこから「アサリ大好き」な県民性が生まれたそうです。
江戸時代から、山梨と駿河湾を結ぶ約70キロの富士川では「富士川舟運」と呼ばれる船の交通が発達していました。幕府への年貢米を運ぶために開かれた水運で、帰路には樽に詰めたアサリが大量に運ばれていました。
富士川は日本三大急流のひとつで、甲府盆地から駿河湾まで流れに乗れば5、6時間で到着できます。
帰路は急流を遡るため、3~4人の船頭が船を引いて3日から5日かかりましたが、アサリはその期間も生きたまま運ぶことができたのです。
アサリの食べ方と寿司文化
森原さんによると、アサリの特別な名物料理があるわけではなく、主にお味噌汁の具として食卓に上がることが多いそうです。
甲府市は人口比でお寿司屋さんの数が日本一多く、これは海への憧れの表れだといいます。お寿司屋さんで出される味噌汁も、ほとんどがアサリの味噌汁。家庭でもお店でも、この食べ方が定着しているのが山梨の特徴です。
干しアジの消費量も全国1位で、江戸時代から海産物として大量に運ばれていました。また、塩も重要な荷物でした。山梨でも少量は取れるものの、海から運ばれてきた塩が大切にされていたといいます。
陶磁器なども船で運ばれ、明治時代末期に鉄道が開通するまで、富士川舟運が山梨の物流の主役を担っていました。
マグロ消費量全国2位の理由
山梨県は、マグロの消費量も全国2位です。
富士川舟運では3~4日かかるため、生のマグロは運べませんでした。しかし、駿河湾で水揚げされたマグロを甲府へ馬で運ぶ別ルートがありました。
富士山西側の涼しい山道を通り、夕方に出発して夜通し歩けば、翌朝には甲府に到着します。約70~80キロの距離を一晩で運ぶことで、江戸時代の甲府の侍たちも新鮮なマグロの刺身を食べることができたのです。
当時、輸送費がかかるマグロは高級品で、裕福な人やお客様へのご馳走として出される贅沢品でした。この歴史が現在まで続き、お客様をもてなす時にはマグロを出すという県民性が培われました。
現代に息づくマグロ文化
山梨では「刺身」といえばマグロのこと。喫茶店のメニューにマグロがあったり、店の外の看板に「マグロあります」と書かれていることも珍しくないそうです。
山梨というと「ほうとう」が有名ですが、森原さんは「山梨ではマグロを食べるのが“通”ですので、ぜひ食べてみてください」と呼びかけました。
海なし県だからこそ育まれた、海への憧れと独特の食文化。その歴史的背景には、江戸時代から続く山梨ならではの物語がありました。
(minto)
番組紹介
読んで聴く、新しい習慣。番組内容を編集した記事からラジオ番組を聴いていただける”RadiChubu”。名古屋を拠点とするCBCラジオの番組と連動した、中部地方ならではの記事を配信する情報サイトです。