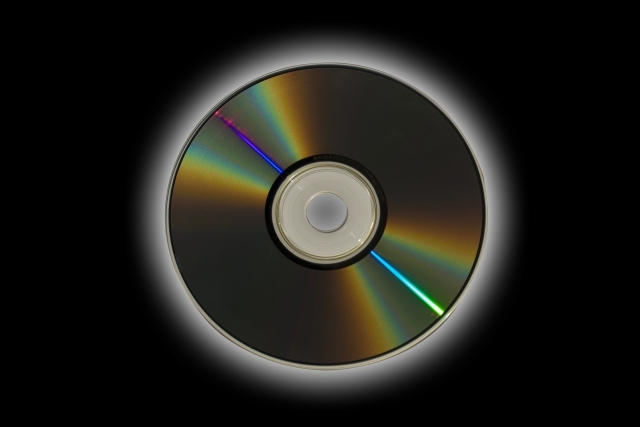立山黒部アルペンルート再開!黒部ダムと水をめぐる人類の歩み

長野県と富山県を結ぶ立山黒部アルペンルートが4月15日に営業再開されます。黒部ダムの建設がきっかけで開発されたこのルートの再開に合わせ、4月14日放送の『CBCラジオ #プラス!』では、CBC論説室の石塚元章特別解説委員が、世界最古のダムから現代の国際問題まで、水を制御する技術の歴史と意義を解説しました。
関連リンク
この記事をradiko(ラジコ)で聴く戦後電力不足解消のための大事業
黒部ダムは戦後の経済復興期に電力不足を解消するため、関西電力が黒部渓谷に建設した大規模発電ダムです。秘境と呼ばれる場所での建設工事は難工事となり、資材運搬のためのトンネル掘削など様々な苦労がありました。
石原裕次郎さんと三船敏郎さんが出演した映画『黒部の太陽』では、黒部ダム建設のためのトンネル掘削工事や地下水が溢れ出す様子など、実際の出来事に基づいた場面が描かれています。
この工事で作られたトンネルなどが、現在の立山黒部アルペンルートの一部として整備され活用されています。
ダム建設のための設備が、観光資源として活かされるケースもあります。静岡の大井川鉄道では、大井ダム建設時に使われていた資材運搬用の鉄道が、今では観光列車として人気を集めています。
世界最古のダムは古代エジプトに
水を溜めるという発想は、古くから存在していました。歴史上最初のダムといわれているのは、古代エジプトに築かれた「サド・エル・カファラダム」で、今からおよそ4000~5000年前のものとされています。
このダムは、ピラミッド建設などで必要とされた多くの労働者たちに飲料水を供給するために作られたといわれています。大勢の労働者が集まる場所では、水の確保が不可欠だったのです。
一方、日本の古いダムとしては農業用のため池があります。大阪の狭山池や香川県の満濃池などは、日本のため池の中でも特に有名です。とくに雨が少ない瀬戸内地方では、水を確保するために多くのため池が作られました。満濃池は弘法大師が開発したという説もあり、今でも使われています。
ダム技術の進化と歴史的転換点
古代ローマでは、火山灰を使った「ローマン・コンクリート」と呼ばれる素材でダムを築いていました。スペインなどの征服地で建設されたダムの中には、現在も残っているものがあります。
そして、近代以降の大きな変化としては、19世紀にイギリスでセメントが発明されたことが挙げられます。これにより、現代的なコンクリートダムの建設が可能になりました。
さらに、1930年代のアメリカでは、大恐慌からの経済復興を目的とした「ニューディール政策」の一環として、当時のフランクリン・ルーズベルト大統領が、テネシー川流域などに約20基のダムを建設しました。これには電力の確保だけでなく、雇用の創出という狙いもありました。
ダムが引き起こす上流と下流の対立
ダムには多くのメリットがありますが、一方で、さまざまな問題や課題を引き起こすこともあります。石塚はその一例として、国境をまたぐ国際河川における水資源の争いを紹介しました。
ナイル川は、エチオピアの高地を源流とし、スーダンやエジプトなど複数の国を流れて、最終的に地中海に注ぐ国際河川です。近年、エチオピアが上流域に「大エチオピア・ルネサンスダム」という巨大なダムを建設し、すでに運用を始めています。これは、経済発展によって急増する電力需要に対応するためのものです。
これに対し、下流に位置するエジプトは強い懸念を示しています。エジプトは国土の大部分が砂漠で、生活用水の約9割をナイル川に依存しています。そのため、上流で水がせき止められると、エジプトに届く水量が減る恐れがあるのです。
こうした状況は、国際的な水資源をめぐる対立の構図にもつながっています。
日本のダム建設と地域対立
日本でも、上流と下流、ダム建設地とその恩恵を受ける地域との間に対立が生じることがあります。代表的な例が、「公共事業の在り方を変えた」ともいわれる「蜂の巣城紛争」です。
1960年代後半、熊本県と大分県の県境付近で「下筌(しもうけ)ダム」の建設が計画されました。当初は賛成していた地元住民のひとり、室原知幸氏が、「水没などの犠牲を強いられるのに、国の対応があまりに不十分だ」として反対運動を開始。その際に築かれたバリケードは、「蜂の巣城」と呼ばれるようになりました。
この紛争をきっかけに、1970年代には「水源地域対策特別措置法」が制定されました。ダム建設で利益を受ける下流地域と、影響を受ける水源地域とのバランスを考えた法整備が進められるようになったのです。
ダムの語源とダムカレー
「ダム」という言葉はオランダ語に由来し、アムステルダムやロッテルダムのように地名にも多く使われています。オランダは海抜より低い土地が多く、堤防やダムなしでは国が成り立たないため、中世オランダ語で堤防を意味する「ダム」が各地の名前に残っているのです。
「ダムカレー」は、ダムにちなんだユニークな料理として人気があります。ご飯とカレーの境目にウインナーなどを配置し、それを持ち上げるとカレーが流れ出すという仕掛けでダムを再現しています。アーチダムやロックフィルダムなど、様々なダム形状を表現したバリエーションも存在します。
実際のダムは単に水をせき止めるだけでなく、適切に水を流す機能も重要です。水が溢れたり構造物が崩れたりしないよう、いかに効果的に水を制御するかという技術が、ダムの奥深さを物語っています。
(minto)
番組紹介
読んで聴く、新しい習慣。番組内容を編集した記事からラジオ番組を聴いていただける”RadiChubu”。名古屋を拠点とするCBCラジオの番組と連動した、中部地方ならではの記事を配信する情報サイトです。