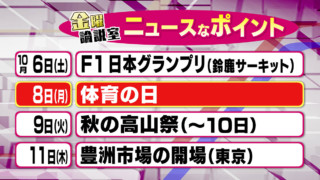平成最後の夏・100回の歴史も戸惑う「甲子園の土」ネット売買の衝撃

平成最後の夏が過ぎて行く。豪雨、台風、そして記録更新の暑さなど自然の猛威を嫌と言うほど味わった日々の中、清風があるとするならば甲子園での熱戦だったであろうか。
夏の全国高校野球大会は100回の記念大会を迎えた。決勝にいたるまでの熱戦譜は今さら振り返るまでもなく、これから長く語り継がれていくであろう。
そんな甲子園で連日の楽しみは100回大会の特別企画「レジェンド始球式」だった。かつて甲子園を沸かせた往年の名選手たち合わせて18人が、日替わりでマウンドに立った。その姿は戦いの歴史を鮮やかに彩り直した。
開会式直後の大会第1試合、真っ先に始球式をつとめたのは松井秀喜さんだった。
驚いたのは、その試合に臨むクジを引き当てたのが、石川県代表で松井さんの母校である星稜高校だったことだ。こんな偶然はなかなかなく、こうなると運命の必然か。さらに先攻か後攻かという最後の選択肢でも星稜が後攻になり、プレイボール時には守備についた。松井さんは母校のユニホーム姿の後輩たちを背負って記念球を投じたのだった。見ているこちらまで感動する場面だった。
準決勝で始球式をつとめたのはPL学園高校で夏の甲子園2回優勝したエース桑田真澄さんだった。この試合には桑田さんが2年生だった時に対戦した秋田県代表の金足農業高校が出場した。金足農業は先攻、このため桑田さんは高校時代と同じ“対戦相手”に一球を投じたのだった。「野球の神様」は甲子園に降臨した。
そんな大会期間中に驚くべきニュースがあった。「甲子園の土」がインターネットのフリーマーケットアプリに出品されて売買されたのである。甲子園の土は球児たちにとって特別な意味を持っている。試合に負けたチームの選手たちが、ゲームセット後のベンチ前で涙を流しながら土を袋に詰める風景は、甲子園の風物詩でもある。自分たちの汗と涙、何より戦いの証しとして土を持ち帰る球児。一方で、再び戻ってくることを誓い、あえて持ち帰らない球児。「甲子園の土」は特別な存在でもある。
それがインターネット上に出品されることに違和感を覚えた人も多いだろう。出品した側に対しては、あの土はそんなに軽いものなのか?と問いたいし、購入した側に対しては、あの土は当事者以外に意味を持つのだろうか?と問いたい。
甲子園100回記念大会の年に幕を閉じる「ドカベン」
100回の記念大会を前にした2018年6月、野球漫画『ドカベン』が46年以上続いた連載の幕を閉じた。名捕手・山田太郎を主役に、ユニークな野球選手たちが活躍するストーリーは多くの人を楽しませ、『ドカベン』の後『大甲子園』などタイトルを変えながら『ドカベン・ドリームトーナメント編』まで続いた。単行本も9月上旬に発売される通算205巻目で締めくくりとなる。
その『ドカベン』第16巻に印象的な場面がある。山田太郎の明訓高校のライバル校、高知県の土佐丸高校の主将に犬飼小次郎という剛球投手がいるが、山田にサヨナラ逆転ホームランを打たれ明訓に敗れた後、ベンチ前で甲子園のグラウンドに土を撒く。持ち帰るのではなく撒くのである。犬飼投手は、自分の青春がこもった高知の土が後に続く大勢の甲子園球児たちを見届けていくのだと語る。名セリフそして名シーンである。
甲子園の土で忘れられないエピソードは、1958年(昭和33年)第40回大会での沖縄・首里高校チームである。ナインは甲子園の土を持ち帰ったが、当時の沖縄は本土復帰前でアメリカの統治下だったため、植物検疫によって「外国の土」と見なされ、船から海に廃棄を余儀なくされた。その後、土ではなく石ならば検疫は問題ないだろうと「甲子園の石」が届けられ、首里高校の記念碑に埋め込まれるという後日談もあるが、当時の時の選手たちの痛みに思いをはせると胸が締めつけられる。
ちょうど60年前のこの歴史の1ページを知っているならば、ネット上で「甲子園の土」を出品そして購入することへの向き合い方も違ったものになると思う。