命脅かす「食道がん」要注意の人は?…「逆流性食道炎」なりやすい行動も!さまざまな「食道」トラブル予防・改善法
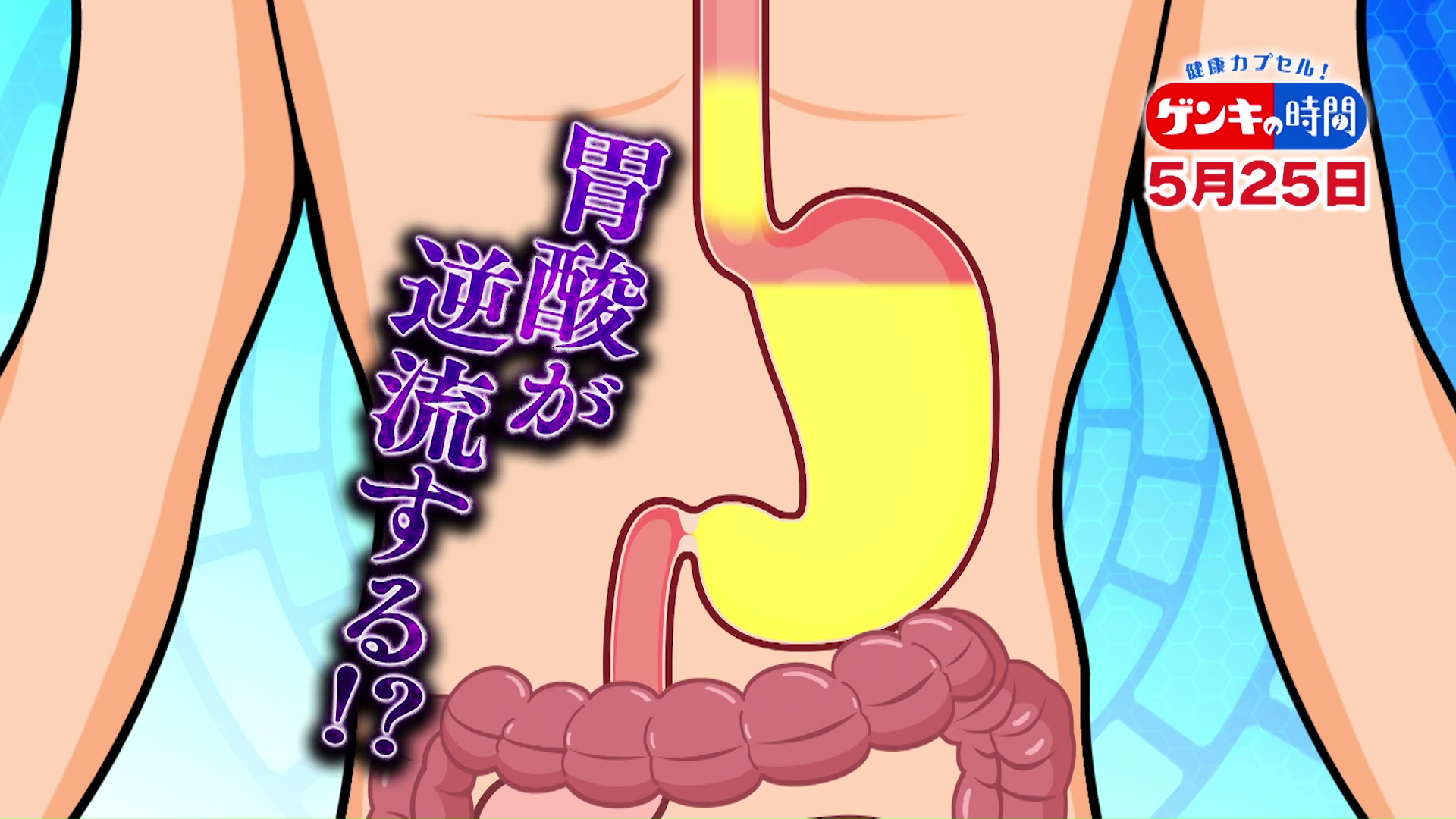
身近な健康問題とその改善法を、様々なテーマで紹介する番組『健康カプセル!ゲンキの時間』。
メインMCに石丸幹二さん、サブMCは坂下千里子さんです。
ドクターは、東邦大学 名誉教授 JCHO船橋中央病院 医学博士 島田英昭先生です。
今回のテーマは「〜胸焼け・胸の痛み・つかえ感〜 その原因『食道』にあり」
食事の後に「胸がむかむかする」「酸っぱいものがこみ上げてくる」「胸の辺りに痛みがある」などの症状がある場合は、食道にトラブルが起きているかもしれません。食道は毎日使うため、トラブルが起きやすい臓器だそうです。なかでも代表的なものが逆流性食道炎。逆流性食道炎は、今や日本人成人の10%~20%が罹患しており新国民病だとも言われているのだとか。そこで今回は、逆流性食道炎から食道がんまでさまざまな食道トラブルについて専門医に教えてもらいました。
食道について

食道とは、口から入った食べ物や飲み物を胃までスムーズに運ぶ臓器。筋肉でできており、太さは約2〜3cm。のどから胃袋の間にあり、筋肉が上から下へ収縮を繰り返すことで胃の中に食べ物を送りこんでいるそうです。
逆流性食道炎とは?
逆流性食道炎とは、胃酸などが食道に逆流して炎症を起こす病気。胃の上部には「噴門」と呼ばれる部分があり、そこが上手く働くことで胃酸などが食道に逆流するのを防いでいます。しかし、逆流性食道炎の患者は何らかの原因で噴門が緩んでいるため、胃酸などが逆流し食道が炎症を起こすのだとか。症状が進むと、食道の粘膜がさらに傷つき「びらん」と呼ばれるただれが出来てしまいます。そのびらんが胸やけ・のどの違和感・痛みの原因となるそうです。
逆流性食道炎の原因
<逆流性食道炎の原因(1)普段の姿勢「猫背」>
猫背で背中が丸まると胃袋に外側から圧がかかります。その圧が逃げていくのは上しかないため、逆流が起きてしまうのだとか。若い人に逆流性食道炎の患者が増えているのも、長時間のスマホやリモートワークなどで猫背になっていることが大きな原因と考えられているそうです。
<逆流性食道炎の原因(2)食べ方・食べる時間「早食い」>
噛む回数が少ないと食べ物が大きいまま胃の中に運ばれるため、消化するための胃酸の分泌量が増加します。また、消化に時間がかかるため胃酸の多い状態が長く続き、逆流のリスクを上げてしまうそうです。先生によると、噛む回数の理想は30回。難しい場合は20回。15回噛むだけでもだいぶ違うのだとか。さらに、辛い刺激物は食道を刺激し、脂質の多い物は消化に時間がかかるため、食べすぎには注意が必要だそうです。
先生オススメ!逆流性食道炎の予防法
まずは姿勢や日々の食生活を見直して、食道トラブルを予防・改善しましょう。
<(1)白湯で血流促進!>
1つ目のポイントは、食事の前に50〜60℃の白湯を飲むこと。血流をはじめ食道や胃の蠕動運動が良くなるそうです。夕食の前には細心の注意を払い、食べる前のウォーミングアップとして白湯で血流を促進しましょう。
<(2)食道を守る ネバネバと乳製品>
先生によると、食道を守るためには粘り気のある食材がオススメ。食道の内側には「プロテオグリカン」という成分があり、食道の粘膜を胃酸から守っています。オクラ・ヤマイモ・モロヘイヤなどのネバネバ食材には、プロテオグリカンが多く含まれているのだとか。また、乳製品には粘膜を守る膜を作り、胃酸による吐き気などを防ぐ働きがあるそうです。
<(3)夕食で消化に良い食材を摂る>
逆流性食道炎を予防する3つ目のポイントは、夕食で消化に良い食材を摂ること。脂質の多い食事をどうしても食べたい場合は朝・昼に食べ、夕食は軽めにすると良いそうです。
逆流性食道炎になりやすい行動一覧

・猫背、早食い
・食べてからすぐ寝ることがよくある
・辛い物をよく食べる
・ベルトなどでお腹を締め付ける服装
・右を下にして寝る
先生によると、辛い物は胃液の分泌量が増えてしまうため逆流のリスクが高くなってしまうとのこと。また、長時間ベルトをきつく締めると腹圧が上がってしまい、逆流のリスクが高まるので締めすぎには要注意だそうです。そして、胃の形は左右非対称で、膨らんでいるところに胃液を溜める機能があります。左を下にすると湾曲した所に胃液を溜めてくれるので逆流しないそうですが、右を下にして寝ると胃が食道より上になるため、胃酸が逆流しやすくなってしまうそうです。
高齢者に増加「食道裂孔ヘルニア」
胃酸の逆流が起きる食道トラブルで、高齢者によく見られるのが「食道裂孔ヘルニア」。食道裂孔ヘルニアは、食道が通過する横隔膜の隙間が加齢とともに緩むことで、食道と胃袋の入り口が開いている状態になり、腹圧がかかると胃袋が持ち上げられて逆流を起こすのだとか。食道裂孔ヘルニアに起因する逆流性食道炎で、生活指導や内科的治療で軽減されない強い症状がある場合には、外科的治療を考慮する場合もあるそうです。
初期症状が出にくい 命を脅かす「食道がん」
<食道がんの特徴>
先生によると、食道がんは初期症状が出にくく、出たとしても逆流性食道炎と似ているため、放置してしまうケースが少なくないとのこと。そして、進行が速いことも食道がんの特徴の1つ。わずか3ヶ月で、水分が食道を通りにくくなるほど進んでしまうこともあるのだとか。食道がんの主な原因と考えられているのは、過度な飲酒・喫煙、暴飲暴食だそうです。
<お酒で顔が赤くなる人は要注意!>
お酒を飲むと、アルコールは血流で肝臓に運ばれ「アセトアルデヒド」という物質になります。アセトアルデヒドは、発がん性物質で通常は酵素によって分解され、体外に排出されます。しかし、分解する能力が低い場合体内に蓄積しやすく、顔の赤み・頭痛・吐き気などの不快な症状が表れるのだとか。分解されなかったアセトアルデヒドが血中を巡り肺へと到達すると、呼気中に含まれて食道粘膜に作用し、食道がんのリスクを高める可能性があるそうです。
<食道がんの手術法「食道亜全摘胃管再建」>
食道がんの代表的な手術は「食道亜全摘胃管再建」。この手術は胸部から腹部の食道を切除し、胃を筒状にして食道の代わりに用いる再建術。経験者のお話によると、胃を引き伸ばしているため今まで通りの食事は難しく、術後は小さくて流し込みやすい食べ物を飲み込むトレーニングから行なったのだとか。(※現在は一般的な量の8割程度を完食できるようになったそうです)。また、食道がんは手術をする選択の際、声を失うリスクもあるそうです。
<早期発見のために内視鏡検査を!>
大切なのは、早期発見。50歳を過ぎたら年に1度は内視鏡検査を受けましょう。50歳以下でも、違和感がある場合は迷わず内視鏡検査を。早期に発見できれば、開胸・開腹手術をすることなく、しっかりと治すことができるそうです。
(2025年5月25日(日)放送 CBCテレビ『健康カプセル!ゲンキの時間』より)
番組紹介
ニッポンの皆様に健康生活を!この言葉をキーワードにすぐに役立つ健康情報をお伝えします。「人」「家族」の未来を創り出す、CBCテレビの健康情報番組。









