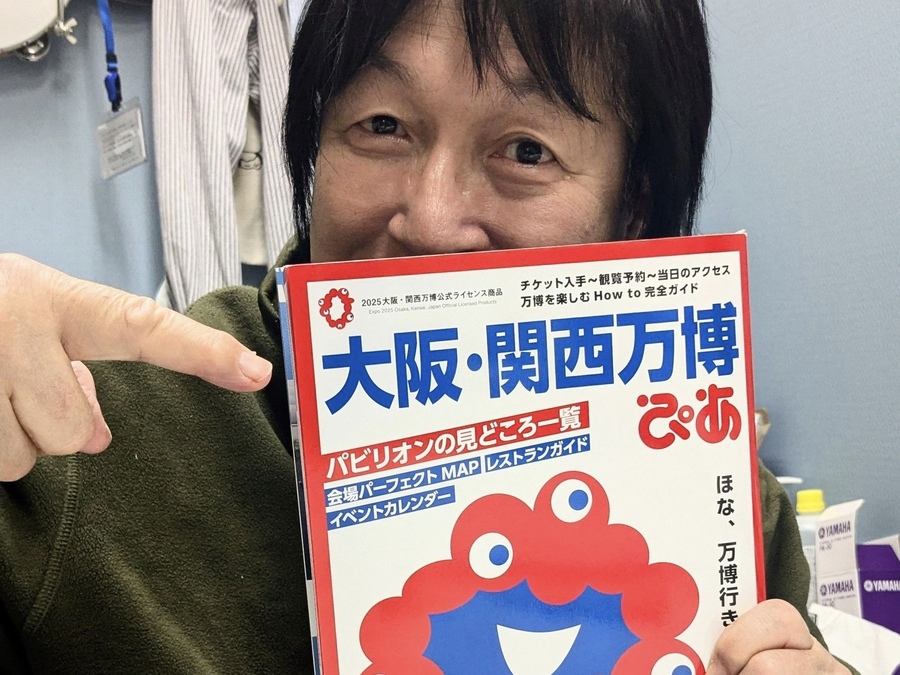アメリカの「禁書週間」。多様性や表現の自由の是非を問う
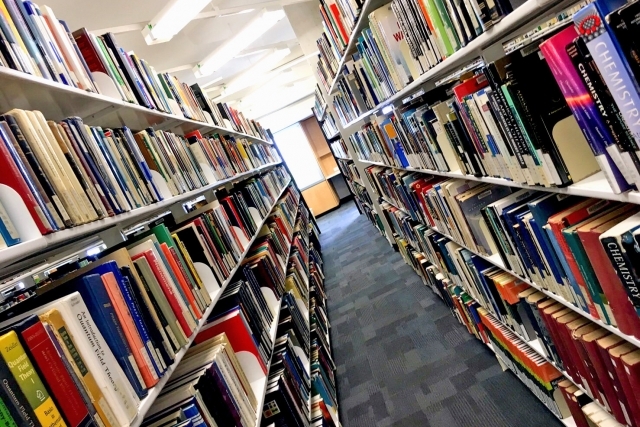
今月5日から11日まで「禁書週間」が行われているアメリカ。どんな本がなぜ禁止されたのかなどを展示し、「禁書」の是非について訴えかけています。10月8日放送のCBCラジオ『つボイノリオの聞けば聞くほど』では、つボイノリオと小高直子アナウンサーがこのニュースについて紹介します。
関連リンク
この記事をradiko(ラジコ)で聴く禁書の主な対象は「多様性」の本
アメリカでは今月5日から11日まで「禁書週間」が行われているそうです。
つボイ「こないだ医者に止められて、禁酒を1週間してましたが」
小高「禁書(笑)。書だから、本」
読書や情報アクセスの自由をテーマにしたイベント「禁書週間」。
米国図書館協会(ALA)をはじめとした連合が支援するこの運動は、1982年に学校や図書館で禁書の申し立てが急増したことを受けて始まったもの。
書店、出版社、ジャーナリスト、教師、読者など本に関わる全ての人々が集まり、「表現の自由」「知る自由」を支援しています。
ちなみに、ここでいう禁書とは「学校や図書館で、こどもの成長過程において悪影響を及ぼす可能性のある本を、学校や公共の図書館から排除する」こと。
発売禁止ではないため、書店では普通に売られています。
つボイ「学校とか図書館にはないけれど、本屋さんで買うことが出来ると。どういう本が対象となるのでしょうか?」
文学と表現の自由の推進団体「ペン・アメリカ」によると、禁書対象の41%は主要登場人物が有色人種、33%がLGBTQ、22%が人種差別を扱っているそうです。
小高の説明に思わず「うーん」と唸るつボイ。
ここ3年で5000冊以上が禁書に
保守的な保護者などから禁書の申し立てがあるのは、性的なもの、中絶、同性愛、人種差別に関わるものが多いそう。
1980年代に禁書の行き過ぎの問題が大きくなったため、「禁書週間」が生まれることになりました。
ところがここ数年、禁書となる本が激増。2022年から2024年で5000冊以上が公共の施設で読めなくなったそうです。
つボイ「面白い物語から歴史を学んだり、自分とは違う人物の気持ちを追体験するのが読書の魅力だと思うんですけども」
小高「本来はこどものために『大人になってからがいいんじゃない?置かないようにしよう』ということでしたが、『ダメ』と言われるジャンルが広がりすぎちゃって。『制限しすぎじゃない?』という問題が起きている」
禁書を巡る背景にはアメリカの政治問題が大きく関わっています。
近年、同性愛婚が認められるなど、LGBTQへの理解が進むアメリカ。
多様性重視の学校に不満を募らせ、伝統を重んじる保守派が多いフロリダ州などで禁書の申し立てが特に多いそうです。
「子供を守る」理念から逸脱?
小高「いったん認められていたけど、『図書館に置かないで』という動きが強くなっている」
つボイ「悪書から子供を守るというのは…残虐な表現とか、過激すぎるものから」
小高「最初はそういう意図だったんですけどね」
つボイ「どうも逸脱して…こどもの思想をコントロールしよう、としているようにもとれますよね」
禁書の歪曲や拡大解釈の危険性を鋭く指摘するつボイ。
本来、公共図書館は本好きで知識を得ようとする人が集まるところ。
「禁書週間」は、どんな本がなぜ禁止されたのかなどを展示し、禁書の是非について訴えかけています。
今年のテーマは「検閲は1984年の話。自分の権利のために読みましょう」。
検閲について描いたジョージ・オーウェルの小説『1984年』にちなんでいるようです。
つボイ「日本でも『はだしのゲン』(原作:中沢啓治)を置くなとか。そんな話ありましたやん」
政治思想が激しくせめぎ合うアメリカの公共図書館。
「本の規制について日本でも考えてみたい」と結ぶ小高でした。
(nachtm)
番組紹介
読んで聴く、新しい習慣。番組内容を編集した記事からラジオ番組を聴いていただける”RadiChubu”。名古屋を拠点とするCBCラジオの番組と連動した、中部地方ならではの記事を配信する情報サイトです。