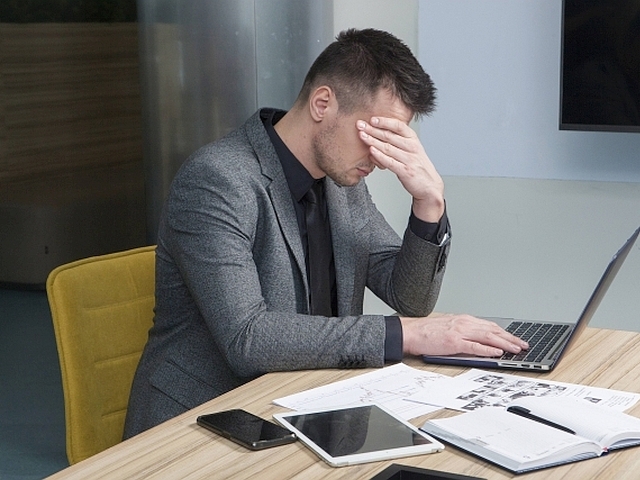えっ、課税の対象になるの?「生前贈与」の注意点
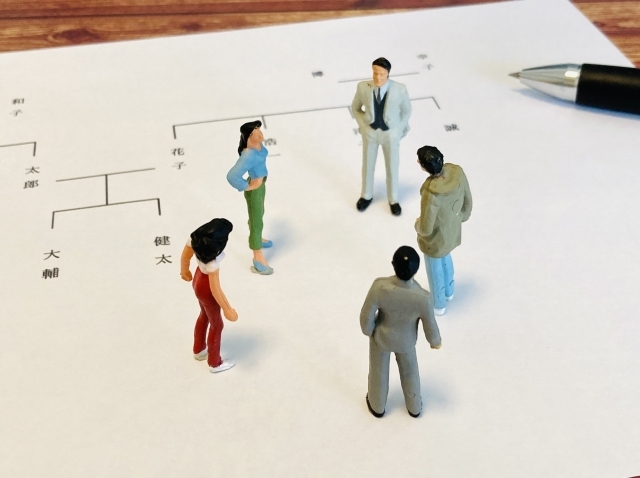
『北野誠のズバリ』(CBCラジオ)の「ズバリマネー相談室」では、小宇佐・針田(こうさ・はりた)FP事務所のファイナンシャルプランナーさんが、お金にまつわる疑問や相談に対し回答しています。4月28日の放送では、「生前贈与に課税されるケースがあると聞いたが本当か?」という質問に対し、徳山誠也さんが回答しました。
関連リンク
この記事をradiko(ラジコ)で聴く契約書を交わしても課税対象に
今回、番組で取りあげた相談は次のとおりです。
「『生前贈与』のことで教えてください。保険屋さんから税金対策のために生前贈与を提案されたので、教えてもらいながら始めました。
母から私に税金がかからない110万円を年1回贈与するという話でした。
その4年後母が亡くなり、遺産相続の話になりました。
すると、相続した分と生前贈与分が課税対象らしく、税金を払いました。
税金対策のための生前贈与だったのに、何だったんだろうと思いながらも、その場は終えました。
何年か過ぎて、最近テレビで生前贈与のことをやっていました。一部を観ただけですが、贈与契約書を作成しないと110万円も課税対象になってしまうという内容だったと思います。
しかしながら、母と私の間で贈与契約書を毎年かわしていましたが、結局課税対象となりました。
そこで相談ですが、『生前贈与』は何をどのようにすれば課税対象外になるのでしょうか?」(Aさん)
相続税の計算ルールが原因
贈与税は年間110万円という基礎控除があるため、年間110万円を超えなければ税金がかからないことはよく知られています。
Aさんの場合は、さらに贈与契約書を交わしていました。
なぜ課税対象となってしまったのでしょうか?
徳山さん「相続開始前3年以内の贈与加算というルールが適用されたから」
これは相続税を計算する際のルールで、亡くなる3年以内に相続人へ贈与した財産は、年間110万円以下であっても、相続財産とみなすというものです。
贈与はして権利は移っているのですが、相続税を計算する場合は計算対象となるという複雑な考えとなっています。
徳山さん「民法と税法の違いというのがあって、相続法という民法では権利が決められていて、相続税法では税の計算が決められているので、食い違いが起きているということですね」
3年ルールが7年に
実は2024年から、この「3年ルール」が7年間に延長されているのです。
ただ、いきなり2017年までさかのぼって課税されるというわけではなく、徐々に期間が延びていって、2031年には完全に7年以内になるということです。
もちろん、人はいつ亡くなるかわからないため、7年以上前から生前贈与しておこうと計画は立てられませんが、徳山さんは「なるべく早く、また贈与税を払ってでも多めに生前贈与した方が良いかもしれない」とアドバイス。
ただ、年120万円ぐらいだとあまり変わりませんが、徳山さんがよく勧めるのは310万円や510万円で、相続するものが多い方はある程度多めにまとめて渡した方が良いそうです。
贈与契約書を作る意味
贈与契約書そのものに節税の効果はありません。
ではなぜ作る必要があるのかというと、税務署や親戚、身内に明らかに行ったことを証明するため。また、定期贈与とみなされないようにするためです。
例えば「100万円を10年間渡す」という約束で贈与してしまうと、税務署は1,000万円を贈与したとみなされ、税金がかかってしまいます。
贈与契約書を毎年交わすと、毎年渡しているということが証明できるというわけです。
(岡本)
番組紹介
読んで聴く、新しい習慣。番組内容を編集した記事からラジオ番組を聴いていただける”RadiChubu”。名古屋を拠点とするCBCラジオの番組と連動した、中部地方ならではの記事を配信する情報サイトです。