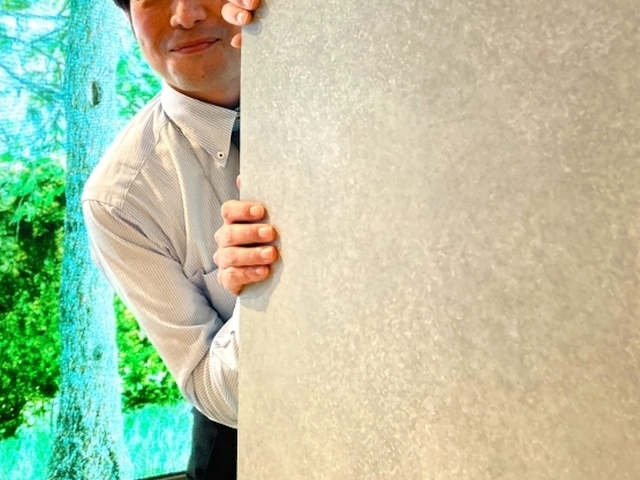まずは現金の確保!自社株の相続時に気をつけること

少子高齢化により、中小企業や小規模事業者の後継者難が大きな経営課題となっています。そして、元気なうちに資産の管理や、次世代へのスムーズな承継について考えていく必要性も高まっています。CBCラジオ『北野誠のズバリ』「シサンのシュウカツにズバリ」では、事業承継と資産承継について専門家をゲストに学んでいきます。1月29日の放送では、非上場のオーナー会社の自社株についての相続事例を北野誠と松岡亜矢子が三井住友信託銀行 財務コンサルタント竹中秀勇輝さんに伺いました。
関連リンク
この記事をradiko(ラジコ)で聴くオーナー社長の自社株への執着
今回竹中さんが紹介するのは、非上場のオーナー会社の株式に関する相続事例。
北野「自社株のやつですね?」
竹中「そうです。法人で事業運営をされている先で、好調な業績から会社の株式評価が高い反面、高齢のお父様が一人で100%の株式を保有されていました」
相続人は妻と子2名の計3名。うち1名の子が後継予定者として事業運営をサポートしていましたが、もう一人の子は社外で勤務していたとのこと。
父親が保有する会社の株式については「生前のうちに後継者へ移転しておくべき」と税理士からもアドバイスがあったそうです。
しかし人が元気だったせいか、頑なに移転をしなかったと竹中さん。
竹中「後継者は社外にいる兄弟と疎遠であっため、将来会社の株式の相続に不安を抱き、お父様へ遺言書の作成をお願いした結果、何とか遺言書を作成いただくことができた」
遺言書の作成により、相続時の株式の承継が円滑に進んだそうです。
自社株の相続は遺言書が必要?
北野「遺言書の作成がなかった場合はどうなっていたんでしょう?」
竹中「会社の株式を含むすべての財産を相続人全員で法定相続分に従って遺産分割することになり、事業に関与しない相続人に会社の株式が承継される可能性が高くなる」
株式が意図しない相続人に承継された場合は、経営に口を出されたりするなど、後継者が経営に専念できなくなる恐れがあると続けます。
北野「自社株を持っているオーナーは遺言書を作成すべき?」
この質問に「するべき」と答える竹中さん。
竹中「株式を後継者へ移転する方法は、生前に移転する『売買』や『贈与』相続後に移転させる『相続』の大きく3つがあります」
今回のように株式のオーナーが高齢の場合、生前に移転をすることに抵抗感を持たれている方もいるので、後継者は決まっているものの株式の移転が進んでいない会社が散見されるのも事実なのだそう。
竹中「このようなケースでは、最後の手段として、遺言書を活用した株式の移転について準備をしておくことをお勧めします」
後継者はどの程度株を保有すべき?
北野「高齢なオーナーほど自社の株式に執着する人が多そう」
竹中「非上場の会社はオーナー自身が社長となっている場合が多い。特に自身が創業された会社など、思い入れの強い会社ほど自社の株式の移転に難色を示される」
それでは後継者の方は、具体的にどの程度自社株を持っていたらよいのでしょうか?
竹中「一般的には会社の株式の3分の2を確保すべきと言われています」
法律上では「特別決議」と呼称されているそうですが、2/3の持分があれば大抵のことを自分で決めることが可能とのこと。
必要な現金を準備する
今回の事例のように、会社の株式承継時に遺言を活用する場合、特に気をつける点はあるのか尋ねる北野。
竹中「いくつかありますが、特に気を付けるべき点は、相続税を納付するための資金の問題」
後継者が会社の株式を相続によって承継した場合、後継者自身で相続税を納付する資金を確保しておく必要があります。
北野「しかも現金でね」
竹中「はい、現金で」
後継者の預金が乏しい場合は、遺言書の中で後継者に対して現金を多めに配分しておくなどの対策が必要となります。
北野「上場株式と違うから、売って現金に換えれるわけでもないですもんね」
もし後から資金が足りないと分かった場合、お金の工面に奔走して本業の仕事に専念するのも難しくなりかねません。
北野「なるほど。自社株をお持ちのオーナーさんは、見直しのタイミングかもしれませんね」
ぜひ、遺言書の内容と税金納付のため現金がどれくらい必要か、見直してほしいと促す北野でした。
(野村)
番組紹介
読んで聴く、新しい習慣。番組内容を編集した記事からラジオ番組を聴いていただける”RadiChubu”。名古屋を拠点とするCBCラジオの番組と連動した、中部地方ならではの記事を配信する情報サイトです。