「LINE(ライン)の交換」って、まるで名刺交換?便利さと同居する違和感に思う
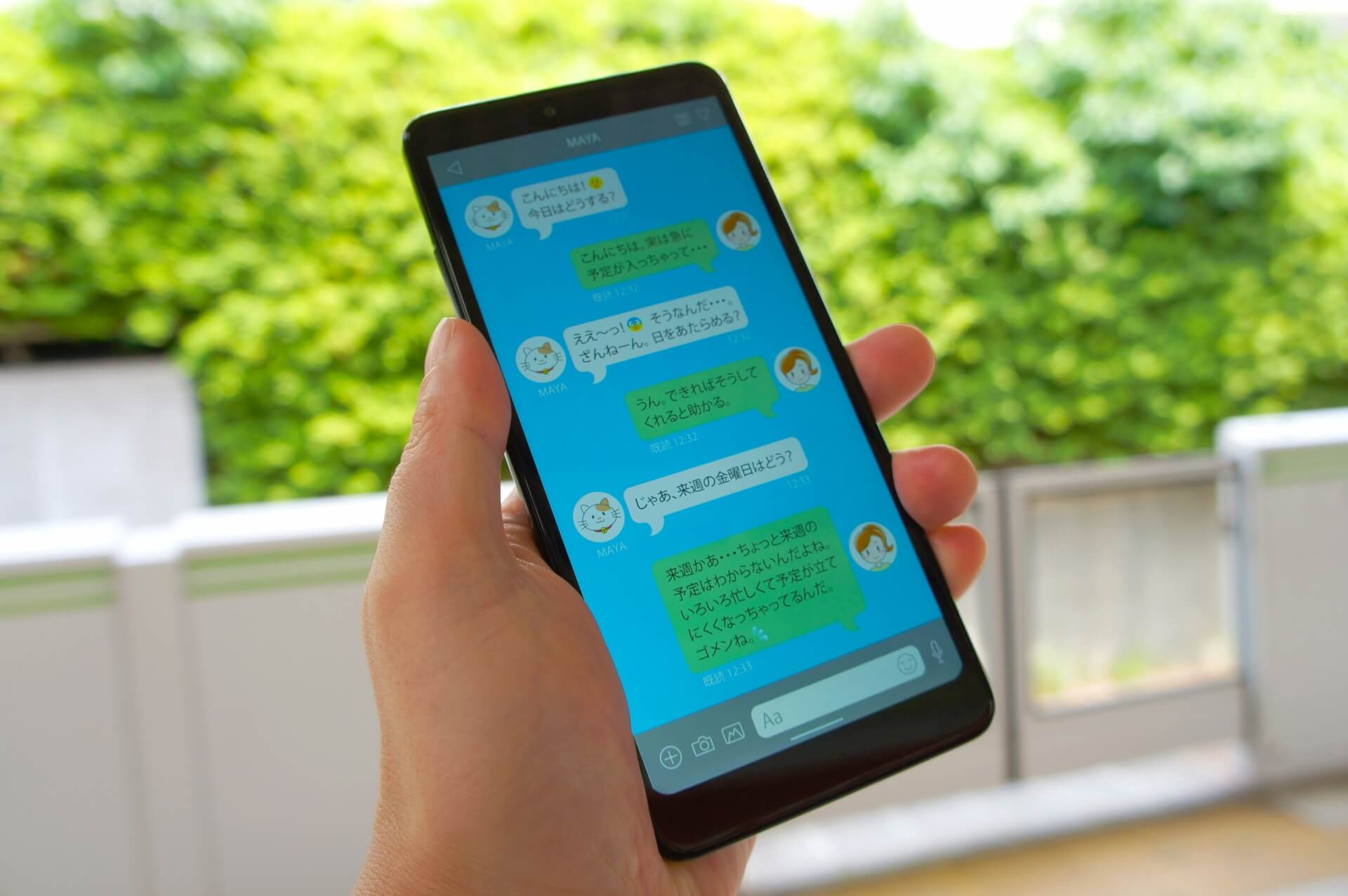
LINE(ライン)を使わない日はほとんどない。今や、大切なコミュニケーションのツールである。ここまで便利な存在になるとは、正直予想もしなかった。少し前に、スマホの機種が古くなって、LINEが使えないトラブルを24時間ほど経験した時は、携帯電話のショートメールに替えるなど、本当に不便だった記憶がある。
LINEの歴史
LINEのアプリサービスは、2011年(平成23年)に始まった。スマートフォンやタブレットなどで利用できるソーシャル・ネットワーク・サービス(SNS)である。メールよりも早く、簡単にネット上でのやり取りができる。グループを作れば、一斉配信によって連絡もし合える。各種スタンプも多く、楽しく使うことができる。音声通話もできる、しかし課金はない。利用者数が拡がって当然である。総務省が2025年(令和7年)6月に発表した調査報告によると、主なSNSの利用率は、LINEが全世代で91.1%と圧倒的な1位だった。
まるで“名刺交換”なの?
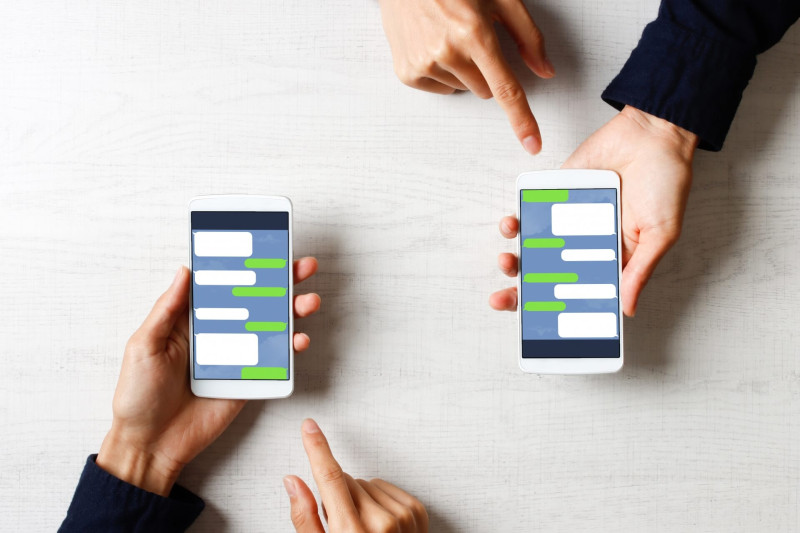
一方で、この拡がりと共に「おや?」と思うことがある。ふと気づくと、LINEの「友だちリスト」の件数がいつの間にか増えている。誰かと会っていて、こんな風に声をかけられる場面も多くなってきた。
「LINEやっていますか?」
「だったらLINEを交換しませんか?」
普段から連絡を取り合っている家族や友人だけでなく、同窓会で会った久しぶりの友人や、仕事で会う初対面の人からも、その場でLINE交換の声がかかる。個人的な感想だが、それはまるで新しい“名刺交換”スタイルのようだ。
なかなか断りづらい悩み
「LINE交換しませんか?」と言われて、断ることへのハードルはとても高い。その相手とは、厳密に言えば“友だち”ほど近しい関係ではない。しかし、その場で面と向かって対峙していて「嫌です」と拒否することは、まるで相手そのものを“拒否”しているようになりかねない。にこやかに応じてしまう自分がいる。ただ、どうしても抵抗があるのは、LINEの持つ“距離感”なのである。携帯電話の番号以上に、個人に近いツールと受け止めているからなのだろう。LINEのリストは「友だちリスト」と言うように、関係性は“友だち”なのである。
増え続ける「友だちリスト」
さらに皮肉なことに、LINEを交換したものの、一瞬だけ戸惑った相手に限って、その後、まったく連絡がないケースが多い。同窓会の会場であらためて“友だち”になった隣のクラスの友人からは、その後、一度たりとも連絡はない。交換したことだけで満足してしまうのだろうか。だったら、もう少し関係が深まってからでいいのではないか。数が増えてしまったスマホの「LINE友だちリスト」を時おり「非表示」へと整理しながら、不思議な思いに駆られることがある。
店からのLINEも増加
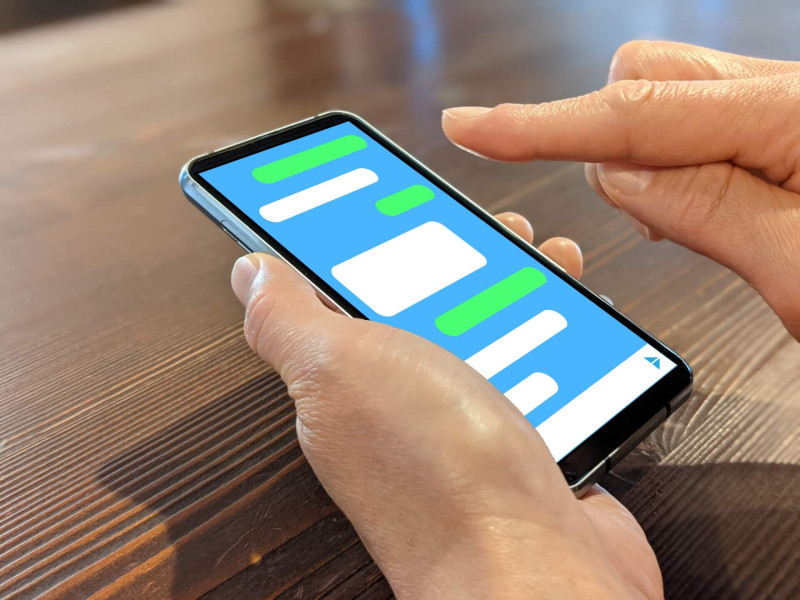
“名刺交換”のようなLINE交換に疑問を感じる中、お店とのLINEは、時として困る場合もある。買い物した時に、ついLINE会員を勧められて入会してしまうと、定期的に連絡が届く。割引の特典は重宝する。よく利用するワインショップならば情報入手にも役立つことも多いが、そんなに度々購入することがない衣料品店や季節用品店などからも、続々とLINEに商品案内が届く。非表示にしても、お店側が、新たな案内を発信すれば「友だちリスト」に“再浮上”してくる。ブロックすることも考えるのだが、ひょっとして有意義な情報があった場合も考えると、それも惜しく、何とも悩ましい。
新たなコミュニケーション・ツールが登場すると、人と人との関係に変化が生じることは当然のことだろう。「友だちを削除する方法」や「相手を傷つけずに削除する方法」などのLINE使用マニュアルも、インターネット上ではいろいろ紹介されている。便利だけれど、その使い方には一考を。そんな“共存”に思いを馳せながら、今日もLINEで連絡を取り合う自分がいる。
【東西南北論説風(641) by CBCマガジン専属ライター・北辻利寿】









