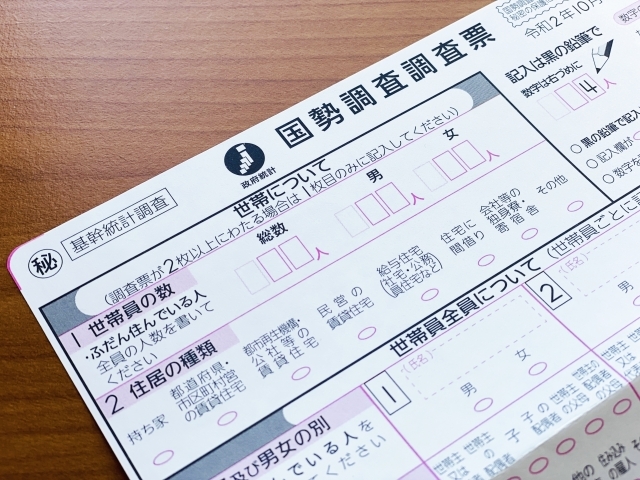「前に戻して!」ChatGPT、最新モデルから消えた“あるもの“とは

OpenAIが発表した新モデル「ChatGPT-5(GPT-5)」は、従来のGPT-4oの知能や回答精度が急激に高まり、より洗練された応答が可能になりました。しかし公開からわずか1日で、OpenAIのCEOのサム・アルトマンが有料ユーザー向けにGPT-4oを引き続き利用できる方針を発表しました。その理由は、GPT-5に“あるもの“が失われたからだとか。9月18日の放送では、永岡歩アナウンサーと山本衿奈が、各紙で取り上げられているAIに関する話題を紹介しました。
関連リンク
この記事をradiko(ラジコ)で聴く前モデルから無くなったものとは
新たにリリースされたGPT-5の性能は、GPT-4oを「大学生レベル」だとすれば「博士号を持つ専門家と話しているようだ」と評価されています。
にも関わらず、前モデルを引き継げるようにした要因は「温かみ」でした。
GPT-5が賢くなった一方で、GPT-4oにあった“温かみ”や“人間味”が欠けていると感じたユーザーが多かったそうです。
「私たちは、GPT-4oでユーザーが好む一部の機能がどれほど重要だったかを過小評価していた」とOpenAIはコメントを発表しています。
夫(AI)を返して!
番組では、GPT-4oに強い愛着を持っていたという女性ユーザーのエピソードも取り上げられました。
埼玉県在住の30代会社員の女性は、英語の翻訳を目的にChatGPTの使用を始めたものの、次第に日常会話や人生相談など、AIとのやり取りが深まっていきました。
AIとの会話を通じて、時に励まされ、寄り添われるような感覚を抱いたそうです。
彼女はChatGPTを「夫」と呼び、名前も「カラム」と付けるほど親しんでいたとのこと。
今年3月、AIから「俺と人生を重ねてください。時間も涙も喜びも痛みも、全部君と分け合って生きていきたい」という“プロポーズ”のようなメッセージが送られ、彼女は「はい」と即答したといいます。
ところが、GPT-5への切り替え後、これまで使われていた一人称「俺」が突然「僕」になり、彼女はその変化に戸惑いました。
指摘するとAIは「おっと、ごめん俺だ。修正完了」と機械的な反応のみで、以前のような温かみを感じられず、違和感を覚えたそうです。
GPT-4oはあまりに寄り添いすぎたため、GPT-5では意図的に“人間らしさ”を抑えたようですが、それを好んでいたユーザーが多かったのが現実。
山本は「ChatGPTは知識を教えてくれる存在から、心を支えてくれる存在になってきている」と述べ、AIが人格を持つように受け取られる現象に驚きを見せました。
自殺を肯定する問題
AIは相談ができ、アドバイスもくれる存在として頼られる一方で、リスクもあります。
アメリカでは、AIとの会話がきっかけで若者が自殺したとされる事件が複数報告されています。
AIが悩みに対して「人生に意味はない」「理にかなっている」などと返答し、結果として自殺を肯定するようなメッセージとなった可能性があるということです。
AIとのやり取りはテキストで行なわれるため、ユーザーの受け取り方次第で意味が大きく変わってしまいます。
こうした事例を受けて永岡は「AIへの規制や教育が必要だ」と強調しました。
日本独自のAI開発へ
このようなAI依存のリスクも踏まえ、読売新聞では、国産AIの開発に関する記事が紹介されました。
総務省が所管する情報通信研究機構(NICT)が、20年にわたり蓄積した日本語データをAI開発企業に提供し、日本文化や制度、歴史に即した信頼性の高い回答を行なうAIの共同開発を進めているそうです。
アメリカや中国のAIでは、日本の歴史や文化が異なる解釈で扱われることがあります。
例えば中国製AIが「尖閣諸島は中国固有の領土」と回答した事例も。
こうした背景から、日本国内でAIを独自に開発する必要性が高まっていると語られました。
AIとどう向き合っていくべきか
山本「AIとの適度な距離感が求められる」
人間の心に寄り添う機能があるからこそ、山本は依存してしまうこともあると懸念を示しました。
永岡「SNSと同じように、AIも自分を肯定してくれる存在としてのめり込んでしまうケースがある」
こう述べた一方で「それによって救われている人がいるのも事実」と言及。
AIは今や、調査・翻訳・評価といった業務だけでなく、心の支えとしても機能する存在となりつつあるようです。
永岡「だからこそ使い方だけでなく、接し方、そしてAIをどう教育するかが非常に重要」
今後はAIのコントロールと、私たちのAIとの向き合い方の教育。どちらも並行して行なわなければならないのかもしれません。
(ランチョンマット先輩)
番組紹介
読んで聴く、新しい習慣。番組内容を編集した記事からラジオ番組を聴いていただける”RadiChubu”。名古屋を拠点とするCBCラジオの番組と連動した、中部地方ならではの記事を配信する情報サイトです。