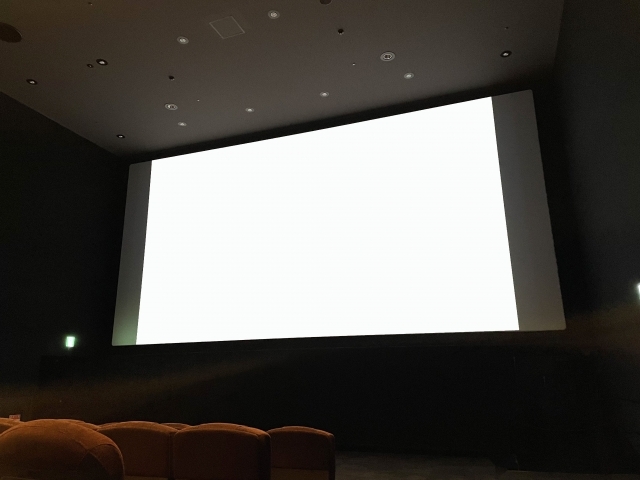400年の歴史を誇る徳島の阿波踊り、鬼滅の刃コラボで新たな挑戦へ

8月11日放送の『CBCラジオ #プラス!』では、阿波踊り未来へつなぐ実行委員会事務局の三船あゆみさんに、徳島の夏の風物詩である阿波踊りの魅力と今年の見どころについて話を伺いました。毎年100万人を超える観光客が訪れる日本を代表する夏祭りの歴史、そして若い世代への継承に向けた新たな取り組みとは。
関連リンク
この記事をradiko(ラジコ)で聴く400年以上続く踊りの起源
毎年8月11日から15日までの5日間、徳島市内には国内外から100万人を超える観光客が訪れ、町全体が熱気に包まれます。
阿波踊りは徳島の人々にとって、単なる夏の踊りではなく、地域の誇りと絆を象徴する特別な存在。その歴史は400年以上に及び、地元の人々の生活や心に深く根付いているとのことです。
阿波踊りの起源には複数の説があります。
天正14年に徳島藩の藩祖・蜂須賀家政が徳島城の築城を記念して、城下の人々に城内での無礼講を許した際に踊られたものが始まりとする「築城起源説」。
そして鎌倉時代の念仏踊りから続く先祖供養の踊りが始まりとする「盆踊り起源説」などが伝わっています。
「同じアホなら踊らにゃソン」の精神
8月12日から15日は市内に有料演舞場3か所、無料演舞場2か所が設けられます。近年はインバウンドの影響もあり、特に台湾や韓国からの観光客が多く訪れています。
阿波踊りには江戸時代から伝わる有名な囃子言葉があります。「踊る阿呆に見る阿呆 同じ阿呆なら踊らにゃソンソン」。三船さんによると、この言葉には「どうせ踊りを楽しむなら、ただ見ているだけじゃなく、自分も一緒に踊って楽しもう」という意味が込められているそうです。
ここでいう「阿呆」とは、お祭りに夢中になって周りの人の目を気にせずに楽しむ人々のこと。踊り手も観客も一緒になり、この掛け声を口にしながら盛り上がります。
この言葉は阿波踊りの精神そのものを表しているとされていて、「お祭りは見るだけでも楽しいものの、体を動かして参加するともっと心に残る体験になる」という思いが、昔からこの掛け声には込められているということでした。
初心者でも楽しめる踊り
阿波踊りは古くから「手をあげて、足をはこべば阿波おどり」と言われるくらい、初めての方にも楽しみやすいのが特徴です。
男踊りは法被または浴衣を着用して腰を低くした体勢で、団扇や提灯を持って踊る自由奔放な動きが魅力。一方、女踊りは編み笠をかぶり浴衣を着た女性が下駄を履いて踊る、上品でしなやかな足の運びが特徴です。
阿波踊りのグループは「連(れん)」と呼ばれ、数十人で構成されています。小さいところだと10人くらい、大きい連だと100人以上になることもあるそうです。
連には様々な種類があります。歴史が長く、卓越した技量で観客を魅了する「有名連」、地元企業が社員や家族で参加する「企業連」、学生中心の「学生連」、そして観光客が飛び入りで参加できる「にわか連」。
それぞれ踊り方のスタイルや掛け声、衣装のデザインも違うため、見比べることも阿波踊りを楽しむひとつの方法だそうです。
『鬼滅の刃』とのコラボレーション
今年の大きな見どころは、8月12日に実施されるアニメ『鬼滅の刃』のキャラクターとともに演舞場に踊り込むイベントです。これは阿波踊り史上初めての試みで、若い世代の参加を後押しして、阿波踊りの時代継承につなげる狙いがあるといいます。
同様に、8月14日にも企画第2弾が予定されています。
初めて訪れる人へのアドバイスとして、「本場徳島の阿波踊りをにわか連で体験することができます。踊ったことない方や初心者の方でも大丈夫です」と三船さん。
有名連のレッスンとリハーサルの後、演舞場へ踊り込むことができ、自由な服装で事前の申し込みや料金も不要とのことです。
400年以上の歴史を持つ阿波踊りは、伝統を守りながらも新たな挑戦を続け、次世代へと受け継がれていきます。
(minto)
番組紹介
読んで聴く、新しい習慣。番組内容を編集した記事からラジオ番組を聴いていただける”RadiChubu”。名古屋を拠点とするCBCラジオの番組と連動した、中部地方ならではの記事を配信する情報サイトです。