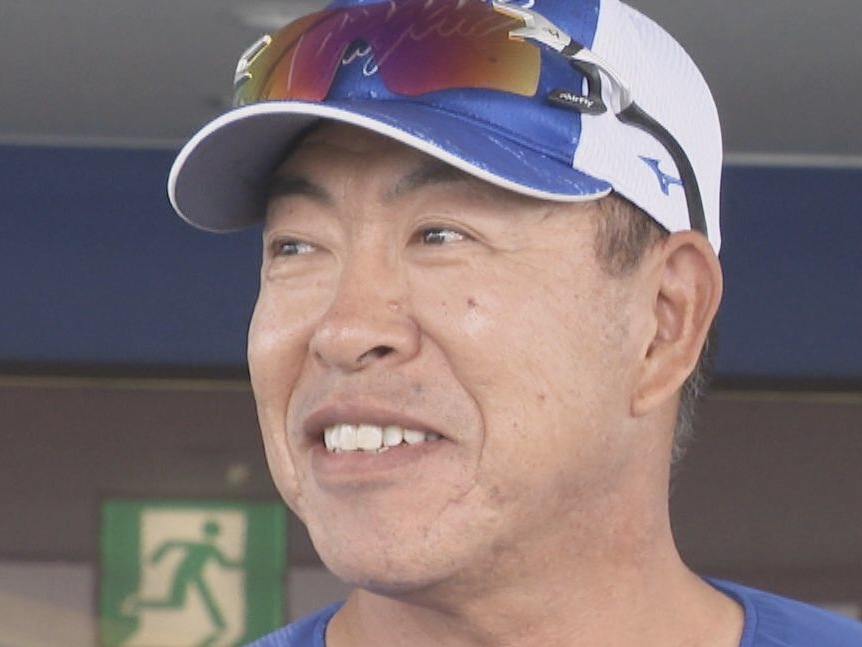道路陥没で不安広がる…日本のインフラは今どうなっている?

1月28日に埼玉県八潮市で発生した大規模な道路陥没事故。下水道の老朽化による破損が原因と見られていますが、その後も各地で道路陥没や水道管の破裂など、インフラの老朽化や維持管理の問題による事故が発生しています。老朽化のスピードに対策が追いついていないという現状ですが、日本のインフラはいまどのような問題に直面しているのでしょうか?2月26日放送『CBCラジオ #プラス!』では、日本のインフラ老朽化という深刻な問題について、ジャーナリストの北辻利寿さんが解説しました。聞き手は永岡歩アナウンサーと三浦優奈です。
関連リンク
この記事をradiko(ラジコ)で聴くインフラの耐用年数はどれぐらい?
インフラの老朽化が特に問題視されるようになった事故のひとつが、2012年(平成24年)に中央自動車道で起きた笹子トンネルの天井板落下事故。
この事故により、9名もの方々が亡くなられましたが、そこで浮かび上がったのが高度経済成長期に一気に社会インフラが整備されたことによる問題です。
1955年(昭和30年)から20年間ほどで急激に整備されたため、多くのインフラが集中的に耐用年数の限界を迎えることになってしまうわけです。
空気中の二酸化炭素がコンクリートに徐々に入り込むことで弱くなり、国土交通省は50年を施設の耐用年数の目安としています。
また、今回事故のあった下水道は42年を経たものとなっています。
50年を超えた下水道管が少なくない
下水道は日本全国で総延長が約49万kmとされていますが、そのうちで50年を超えているものは約3万kmと、現時点では1割にも満たない状況。
ところが10年後には9万km、20年後には20万kmにまで増えてしまうため、このまま放っておくと全体の4割が耐用年数を超えることになってしまいます。
実は下水道が原因の陥没事故は、2022年度に全国でなんと2,600件あまりも発生しています。
もちろん、今回の八潮市のような大規模な事故が何百件、何千件も起きているわけではありませんが、報道されないほどの小さな道路の凹みなどは毎日全国各地で起きているということになります。
例えば名古屋市では下水道管による道路の陥没事故は年間平均で130件ほど起きていて、50年を経過した下水道管は全体の4分の1ほどあるそうです。
今回の事故で恐ろしさとインフラ整備の重要性の両方をあらためて知ることとなりました。
インフラの補修にかかる費用
国土交通省の試算によりますと、破損が起きた後に補修していく費用は20年後ですと全国で約12兆3千億円もかかるそうです。
しかし、事前に予防的に新しいものに取り替えるなど対応すると、約6兆5千億円で済むそうです。
そのため、北辻さんは「とにかく予防的に先へ先へとメンテナンスを進めることが、実は結果的には事故も防ぐし費用もかからないということになるということですよね」と語りました。
先程紹介しました笹子トンネルの事故をきっかけに、国は5年に1度定期点検をするようルールを策定しましたが、下水道については管理者の地方自治体に任せているため、費用面で厳しいという面もあります。
国は今まで新しい道路や施設を作ることに大きな予算を投入してきましたが、予算の使い方をあらためて考え直す時期に来ていると言えそうです。
(岡本)
番組紹介
読んで聴く、新しい習慣。番組内容を編集した記事からラジオ番組を聴いていただける”RadiChubu”。名古屋を拠点とするCBCラジオの番組と連動した、中部地方ならではの記事を配信する情報サイトです。