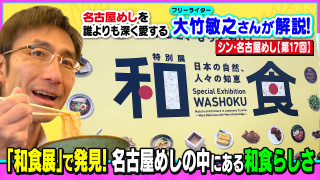端午の節句限定の隠れ名古屋めし「黄飯(きいはん)」を知っていますか?~大竹敏之のシン・名古屋めし

何十年とつくっているお店も知らないその由来
「そろそろ黄飯(きいはん)をつくる(買う)頃だね」
こどもの日が間近に迫ったこの時期、こんな言葉が交わされるのは、生粋の名古屋(尾張)人の家庭。端午の節句に、子どもの健康を願って黄色いおこわを食べる習慣がこの地域にはあるのです。
「くちなし由来の着色料でもち米を蒸し、黒豆を上にのせます。5月5日のこどもの日には200~300パックは出ますね」とは昭和2年(1927)創業の山田餅本店(名古屋市瑞穂区)3代目の山田克哉さん。端午の節句に合わせて古くから当たり前のようにつくり続けている黄飯ですが、由来については判然としないといいます。
「私が店に立つようになった30~40年前は、白・黄2食のおこわの詰め合わせで白黄飯として売っていたんです。そのうち、黄飯だけでいいんじゃないか?と黄色だけになった。小豆を使う赤飯は贅沢なのでくちなしで代用したという説もあるようですが、黒豆だって高いですから、理由としては信ぴょう性が乏しい気がします」と山田さん。さらに「昔は商売としてつくって売るものじゃなく、主に家庭でつくられていたと思います。民間の風習は記録もないので、いつから、なぜ、というのは分からないものが多いですよね。つくっているこっちが教えてもらいたいくらいです」といいます。
全国各地で見られる黄色いおこわ
近年は同店のようないわゆる餅屋系の和菓子店でつくられることが多いよう。一方で、江戸時代創業の仕出し専門店、八百彦本店(名古屋市西区)でも取り扱いはあるといいます。
「弊社では『おうはん』と呼んでいて、端午の節句のご注文のうちわずかな数ですが、昨年実績では合わせて35個をつくりました。ご注文先は名古屋市内および近郊の稲沢市や一宮市など。古い記録がないのではっきりとは分かりませんが、つくるようになったのは昭和からだと思われます」(同社担当者)
この証言からも、黄飯が食べられているのは名古屋および尾張地方、そして昭和より以前は家庭でつくられることが多かったと推測されます。
ちなみに知多半島出身の筆者は、黄飯の存在を知りませんでした。名古屋で家庭を持って男の子が生まれた後も、知多と三河出身の私たち夫婦は黄飯を知らず、息子に食べさせたこともありません。今回、山田餅の黄飯を初めて食べましたが、おこわ自体はもち米のほのかな甘みが感じられるシンプルな味わい。黒豆にはやや塩味がつけてあり、アクセントになっています。レンジや蒸し器でほんのちょっと温めると、もち米のもっちり感がよみがえっておいしく食べられます。
黄飯に類似する料理は他地域でも見られます。しかし、由来や食され方はそれぞれ異なります。大分県臼杵市の「黄飯(おうはん)」は黒豆が入っておらず、出されるのは大晦日や祝いの席。スペインのパエリアを模したとの説もあります。静岡県の「染飯(そめいい)」も黄飯同様くちなしで黄色く炊いたおこわですが、黒豆ではなく黒ごまをちらしてあり、季節を問わず祭りやお祝いの行事に合わせて食べられるそうです。
食べて守りたい「絶滅危惧名古屋めし」

2025年は5月6日まで販売
山田餅本店では4月24日から売り出し、今年の販売は5月6日まで。
「昔はもっと早い時期から売っていたんですが、認知している人が減ってきて、それに合わせて販売期間も短くなってきました。最近は、親から子、子から孫へと受け継がれてきたものがだんだん途切れてきてしまっています。黄飯だけじゃなく、地域に伝わるものをもっとPRして伝えていかないといけませんね」と山田さん。
「名古屋めし」という言葉が生まれるはるか以前に、名古屋周辺で親しまれてきた郷土料理は、他にふな味噌、いなまんじゅう、かしわのひきずりなどがあります。しかし、これらは今では提供する店もほとんどなく、「隠れ名古屋めし」とさえ呼べない「絶滅危惧名古屋めし」になっています。黄飯はまだ和菓子店の商品になっている分、食べるまでのハードルは低く、私たちが食べることで途絶えてしまう危機を回避させられます。GWのささやかな楽しみのひとつとして、貴重な隠れ名古屋めし・黄飯を多くの家庭で味わってもらいたいものです。
※記事内容は配信時点の情報です
#名古屋めしデララバ
番組紹介
東海地方の皆が知っているつもりである「ド定番」のスポット・話題・人などの知られざるポイントを太田光が独自の目線で徹底深掘り!深い情報を知り尽くしたマニアたちと共に知られざる魅力と驚きの事実を徹底取材で掘り起こしていく地元が大好きになる1時間!毎週水曜午後7:00~放送。