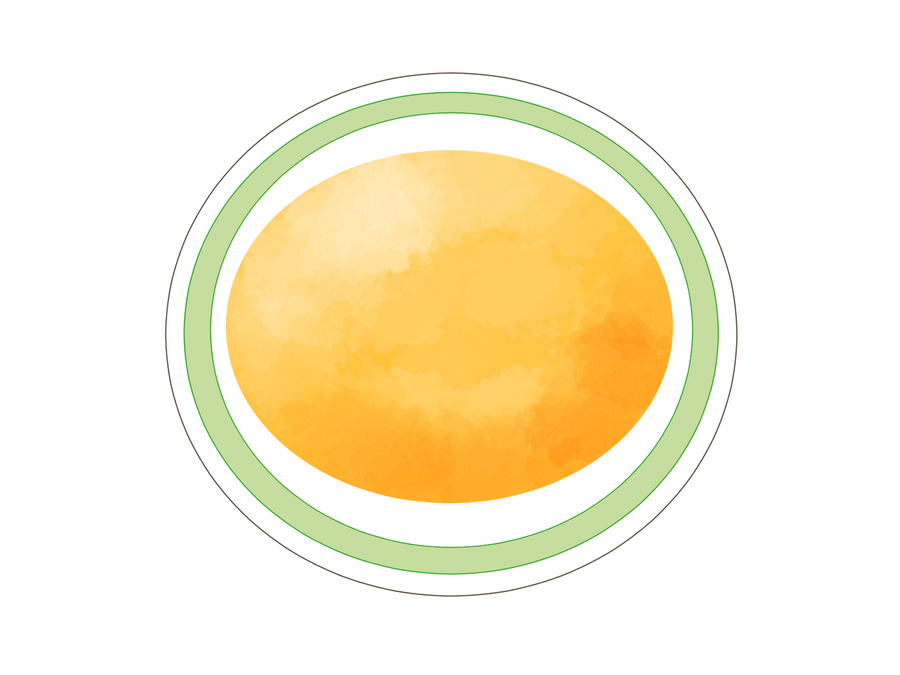イケてるタヌキを選ぶ!?「イケタヌ総選挙」が滋賀・甲賀市で開催

『CBCラジオ #プラス!』の「日本全国にプラス!」コーナーでは、全国各地から地元にまつわる話題を紹介しています。9月10日の放送で取り上げた話題は、滋賀県甲賀市で開催されているというイケてる陶芸作品のタヌキを選ぶイベント、その名も「イケタヌ総選挙」。甲賀市信楽町といえば信楽焼が有名で、信楽焼といえばやっぱりタヌキ。2019年度にはNHKの朝ドラで題材となりました。にわかに別の選挙が話題となっていますが、こちらはどんな総選挙なのでしょうか?信楽町観光協会の松田晃余さんに、永岡歩アナウンサーと三浦優奈が話を伺いました。
関連リンク
この記事をradiko(ラジコ)で聴く11月8日は信楽たぬきの日
イケタヌ総選挙の投票日は、今年は11月1日から12月14日までですが、その間にある11月8日は信楽たぬきの日。
これは「いいハチの日」という語呂合わせから来ていて、信楽焼のタヌキには八相縁起という8つの縁起が表されているため。
お店の前などにも信楽焼のタヌキが置かれているのは縁起が良いためですが、お店のために毎日立ってがんばっているタヌキたちを労おうと、2012年から記念日が制定されています。
そのため、11月はいつにも増して信楽にはタヌキがお出迎えするイベントがあり、そのひとつがイケタヌ総選挙というわけです。
9月に一般公募から書類選考による1次審査が行なわれ、2次審査に進んだ10体が投票の対象となります。
タヌキのイメージが強くなった理由
ここでそもそもの話になりますが、なぜ信楽焼はタヌキが有名になったのでしょうか?
タヌキの置物は信楽に限らず、江戸時代後期から他の場所でも作られていたと考えられています。
そのような中で特に信楽が有名になったのにはいくつかの説がありますが、最も有力なのは昭和天皇がきっかけで有名になったというもの。
1951年(昭和26年)に昭和天皇が信楽に行幸された際、地元ではタヌキの手に国旗を持たせてお迎えをしたそうです。
実は昭和天皇は幼少の頃からタヌキコレクターで、「おさなとき あつめしからに なつかしも 信楽焼の 狸を見れば」という歌を詠まれたほど。
このことが全国に報道され、「信楽焼=タヌキ」というイメージが強く印象づけられたようです。
信楽焼の特徴
もちろんタヌキだけではなく、信楽焼そのものにも焼き物としての特徴があります。
今の信楽焼は使いやすいようにうわぐすりを用いていますが、伝統的な作り方としては基本的にうわぐすりを施さず、穴窯や登窯といった薪窯を使って高温で焼成し、生地をギュッと固く焼き締める焼き締め陶器というものが特徴。
自然ならではの色やざっくりとした風合いが景色として出てくるのが特徴とのことです。
ところで今、大阪で万博が開催されていますが、55年前にも大阪で開催された万博のシンボルといえば太陽の塔。
太陽の塔は顔が3つあり、背面に過去を表す黒い顔がありますが、この顔は実は信楽焼。
制作者の芸術家・岡本太郎さんも信楽に足を運んだそうです。
9月末まで募集中
話を総選挙に戻しまして、募集は9月末まで行なわれていて、自分のタヌキも応募したいという方は今でもエントリーできます。
応募条件ですが、タヌキの陶芸作品であることはもちろんですが、信楽焼には限定しないため、瀬戸焼や常滑焼などでもOK。
大きさは10cm以上50cm未満、オリジナリティにあふれている作品とのことです。
発表は12月25日とのことですが、どのようなイケタヌが選ばれるのでしょうか?
(岡本)
番組紹介
読んで聴く、新しい習慣。番組内容を編集した記事からラジオ番組を聴いていただける”RadiChubu”。名古屋を拠点とするCBCラジオの番組と連動した、中部地方ならではの記事を配信する情報サイトです。