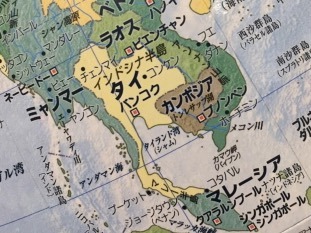絶滅危機から190羽まで回復!中央アルプスの「ライチョウ復活プロジェクト」

長野県の中央アルプス(木曽山脈)で、国の天然記念物で絶滅の恐れがあるライチョウの生息数を増やす取り組みが行なわれています。環境省は今月、中央アルプスで83組のつがいを確認し、繁殖数も前年の1.5倍となる約190羽に達したと発表しました。7月24日放送の『CBCラジオ #プラス!』では、環境省信越自然環境事務所 生息地保護連携専門官の福田真さんに、50年前に絶滅した地域での復活プロジェクトの詳細について伺いました。
関連リンク
この記事をradiko(ラジコ)で聴く人間活動が招いた絶滅の危機
ライチョウはハトくらいの大きさの鳥で、自然環境に合わせて年3回羽が生え変わります。冬には真っ白な姿が知られていますが、オスとメスは目の上の黒い筋の有無で見分けることができます。黒い筋があるのがオス、ないのがメスです。
福田さんによると、ライチョウが絶滅の危機に瀕している最大の原因は、里山の動物が高山帯に進出してきたことにあります。キツネやテンといった捕食者が高山帯に上がってきて、ライチョウを直接食べてしまうことが最も大きな問題となっています。
この背景には人間活動の影響があります。福田さんは「山小屋で食べ物を残してしまうことなどが原因になっている」と指摘しました。
山小屋の残飯を狙ってキツネやテンが高山帯に上がってきて、そこに定着。その後ライチョウも捕食するようになったということです。
1羽のメスから始まったプロジェクト
信州大学の調査によると、1980年代には北アルプス、南アルプス、新潟県の火打山を中心に約3,000羽いたライチョウが、2000年代にはわずか1,700羽まで減少。たった20年で半分近くまで激減しました。
この危機的状況を受けて、環境省は国の予算を使った保護増殖事業を開始。最も減少率が高かった南アルプスで「ケージ保護事業」を行ない、一部地域では生息数を約4倍まで回復させることに成功しました。
現在行なわれている「復活プロジェクト」は、50年前に絶滅した中央アルプスに1羽のメスが飛来したことがきっかけでスタートしたものです。
6~7年前に北アルプス方面からやってきた1羽のメスを登山者が確認。関係省の調査で、オスがいなくても卵を産んで温める行動を繰り返していたことがわかり、そこで有精卵を差し替えて入れることから、このプロジェクトが始まったと福田さんは振り返ります。
慎重な移住計画と定着への工夫
このプロジェクトでは、他の山から家族単位でライチョウを移住させる取り組みも実施しました。ただし、単純に移動させるだけではうまくいきません。捕獲時に緊張させないよう配慮し、現地に慣らしながら慎重に進める必要がありました。
さらに「ケージ保護」の技術を使い、現地の山でヒナが死なないよう地道な保護活動を続けてきたそうです。
こうした努力の結果、現在では中央アルプスのほぼ全域で約190羽のライチョウが生息するまでになりました。絶滅していた地域が、今では「ライチョウが見やすい山のひとつ」になったのです。
人を恐れない神の鳥
今年9月には動物園で増やした約30羽を山に戻す作業を最後に行ない、その後はモニタリングを続け、定着状況を確認していくとのことです。
環境省は2029年までにライチョウのレッドリストランク(絶滅危惧ランク)を1ランク下げ、国の予算を使う保護増殖事業の完了を目指しているそうです。
ライチョウの最大の特徴は「人を恐れない」ことだと福田さん。
日本では古くから山岳信仰があり、山岳地帯を神の領域として大切にしてきたため、ライチョウを捕獲することがなかったという歴史的背景があります。そのため季節によっては登山道に出てくることもあり、比較的見やすい鳥だということです。
人間活動が原因で絶滅の危機に瀕したライチョウ。関係者の地道な努力により絶滅地域での復活を実現しました。私たちも山でのマナーを守り、この貴重な鳥を未来に残していきたいものです。
(minto)
番組紹介
読んで聴く、新しい習慣。番組内容を編集した記事からラジオ番組を聴いていただける”RadiChubu”。名古屋を拠点とするCBCラジオの番組と連動した、中部地方ならではの記事を配信する情報サイトです。