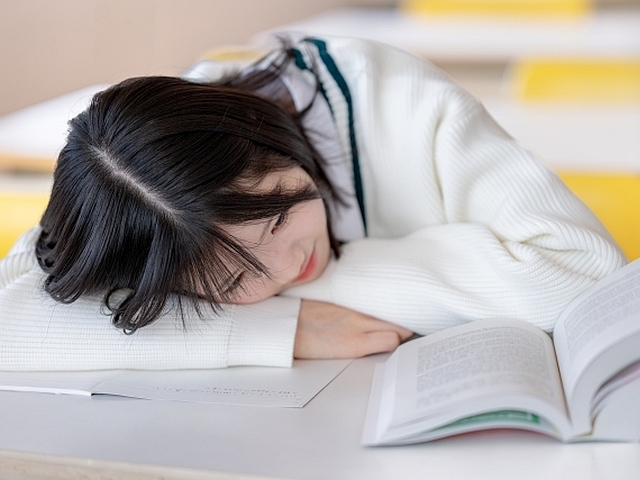東大寺の大仏の左側も見て欲しい。虚空蔵菩薩の魅力

毎週木曜日の『ドラ魂キング』では、パーソナリティの佐藤楠大が仏像に関するトピックを紹介します。4月17日の放送で紹介したのは、東大寺の大仏の左にいる虚空蔵菩薩を紹介しました。一体どんな仏像なのでしょうか?
関連リンク
この記事をradiko(ラジコ)で聴く大仏のマネージャー
東大寺の盧舎那仏像を正面に見て、左側が虚空蔵菩薩坐像。右側が如意輪観音坐像。
「左右に控える仏像を脇侍といい、真ん中にいる仏の補佐役であり、布教役でもあるマネージャー的な存在です」と言う佐藤。
佐藤が今回紹介したのが虚空蔵菩薩。
仏像のタイプは如来、菩薩、明王、天の4つ。これは菩薩に当たるので、中央の盧舎那仏よりも位的には下。
菩薩とは、悟りを開いた状態である如来を目指す途中の姿。
佐藤「なので、ブッダが修行中は王族だったので、王族らしい華やかな装飾をしているのが菩薩なんです」
虚空蔵菩薩の力を得よう
虚空とは広大な世界を意味する言葉。虚空蔵菩薩は、無量の知恵を持っている菩薩で、人々にこれを与えて救ってくれる仏様なんだそうです。
そのため平安時代以降は学業成就の神様的に扱われることが多かったとか。
佐藤「この虚空蔵菩薩で面白いポイントが、虚空蔵菩薩を本尊とする修行があるんです」
虚空蔵求聞持法という虚空蔵菩薩の力を授かるための修行があるそうです。求聞持法は、静かな場所で、虚空蔵菩薩の仏像や絵を掲げて、息の続く限り、陀羅尼という呪文を唱えるというもの。
佐藤「『ノウボウ・アキャシャ・キャラバヤ・オン・アリキャ・マリボリ・ソワカ』。割と長いでしょ。これを1日1万回。100日かけて100万回唱えなきゃいけない」
厳しい修行に耐えた人
1日1万回×100で何でも暗記でき、広大な知恵を得られる能力が手に入るとしても、途中でやめたくなりそうですが…
佐藤「途中でやめられないものなんですよ。諸説あるんですけど、眠たくなってもダメ。途中で数がわからなくなったらやり直して1万回数える。トータル100万回数える精神力が必要なんです」
人によっては刀を近くに置いて、修行に失敗した瞬間に腹を切るほどの覚悟で向き合った人もいたとの伝説も。
この修行を乗り越えて虚空蔵菩薩の教えを授けられた人が、かの有名な空海。
佐藤「この虚空蔵菩薩を見たら、知恵を与えてくれる広大な方なんだなと思ってください」
壮大さを感じて欲しい
佐藤「東大寺の虚空蔵菩薩、注目して欲しいポイントが2点あります。その1、中央の盧舎那仏とは製作の時期が違います」
主役の盧舎那仏が作られ、大仏殿が作られ、大仏開眼供養会が行なわれたのが752年。
虚空蔵菩薩はその1000年後、江戸時代、1752年に作られたそうです。
佐藤「だから仏像界で言うと入社3年目の私のようにピチピチ。ベテランの塩見啓一アナウンサーが盧舎那仏だとしたら、虚空蔵菩薩は若手アナウンサーです」
虚空蔵菩薩は絵で描かれることが多く、仏像として作られても小柄なものが多いんだそうです。しかし東大寺の虚空蔵菩薩は全長7メートル以上の大きさ。
佐藤「18メートルぐらいの大仏の横にいて、その半分ぐらいだから、ああと思うんですけど、虚空蔵菩薩という部類で見たらものすごく大きい。その壮大さも感じて欲しい」
特別な見た目
佐藤が注目して欲しいもうひとつのポイントは、虚空蔵菩薩の手。
一般的には右手に剣、左手に宝珠を持った姿で描かれたり作られたりすることが多いそうです。しかし東大寺の虚空蔵菩薩は何も持っていないんだとか。
右手は手のひらを上に向けて膝の上。左手は手のひらをこちらに向けたポーズ。
佐藤「何となく仏像といったら、こんな感じのポーズというのをしてくれてるんですよ」
東大寺の虚空蔵菩薩は一般的なものとちょっと違う見た目も魅力。
佐藤「東大寺、中央ばかりじゃなく左側をチラッと見て下さい。勉強とか試験とかに備えて、無限の知識が欲しい人、行ってみてはいかがでしょうか」
(尾関)
番組紹介
読んで聴く、新しい習慣。番組内容を編集した記事からラジオ番組を聴いていただける”RadiChubu”。名古屋を拠点とするCBCラジオの番組と連動した、中部地方ならではの記事を配信する情報サイトです。