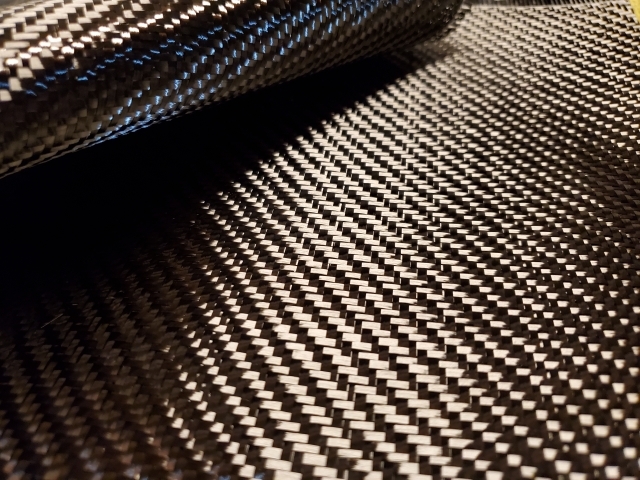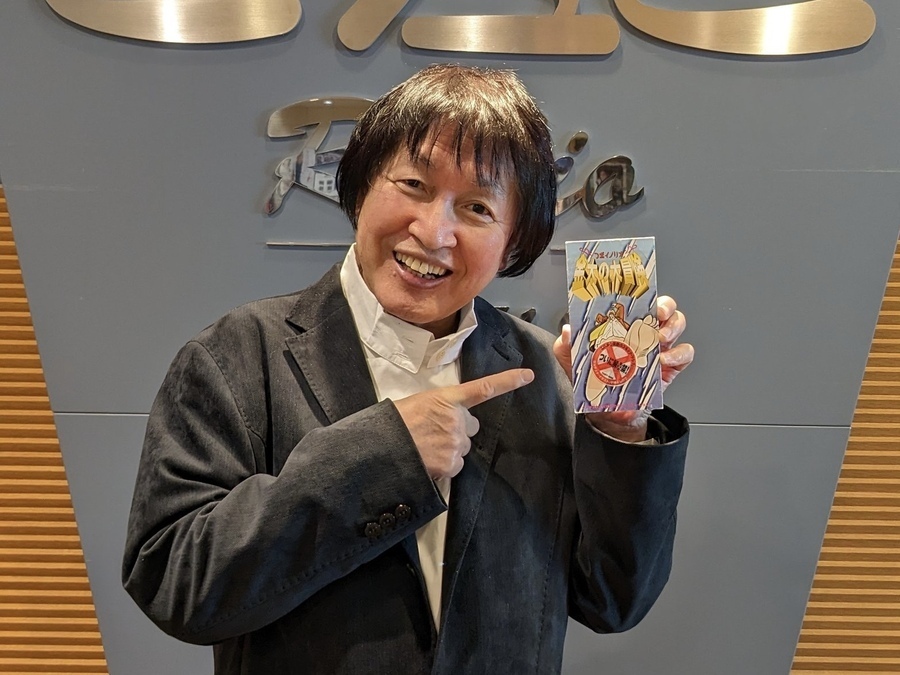いずれは漫才の相方に?「相槌AI」の可能性

4月8日に中日新聞が報じたところによれば、名古屋大大学院情報学研究科の東中竜一郎教授らのグループが、人間のように相槌を打ったり、言葉をかぶせたりしながら話すAI「J-Moshi」を開発したことが報じられました。11日放送のCBCラジオ『つボイノリオの聞けば聞くほど』では、このAIについて、つボイノリオと小高直子アナウンサーが考える「理想の相槌AI」について語り合いました。
関連リンク
この記事をradiko(ラジコ)で聴くAIのモデルはCBCアナ?
東中教授が「なんか最近太っちゃって」と話しかけると、開発されたAI「J-Moshi」は「あーそうなんですか。なんかお食事とかはちゃんと気を付けてるとかですか?」と返答。
教授が「気を付けてないから太っちゃった感じです」と答えると「あーそっかそっか、それで太っちゃったっていうのは確かにそうですよね。フフフ」と相槌を打ちながら笑いまで加えるという、まるで人間同士の会話のようなやり取りが可能になったとのことです。
このニュースを見たリスナーAさんは、ふと気付いたことがあったようです。
「『フフフ』というのは、榊原(悠介)アナがモデルになったんじゃないでしょうか。そのうちに、やかましい相槌の永岡(歩)アナバージョンや、下ネタをさらっと流す小高アナバージョンができるのではないでしょうか」(Aさん)
CBCアナウンサーの個性豊かな相槌が、実はAI研究の原点だったのかもしれません?
かぶせで変わる会話
人間同士の会話のように言葉をかぶせながら話すというのもこのAIの大きな特徴ですが、小高はかぶせ方のマナーが気になったようです。
小高「よく言うじゃないですか。『人がしゃべり終わるまで、しゃべらないの』っていう(笑)。あまりかぶせすぎると、なんか嫌な感じってなっちゃうかもしれないし」
この匙加減は確かに難しいところ。
小高「『この間、あそこのお店に行ったけど、あんまりおいしくなかったよね』って言おうと思ったのに、『そうそうそうそう!おいしかった!』って言われたら、何も(笑)」
つボイ「『俺の言いたいことと違うやん!』。でも、それも人間の会話のありようのひとつやから」
小高「それが人間らしいと言えば、人間らしいんだけど。ちょっとイラっとする時とか、それがうれしい時とか。なかなか複雑じゃないですか」
会話が予想外の方向に向かうこともあるというのは、皮肉にも人間らしい対話といえるのかもしれません。
昭和のいる・こいる風AI?
自分が話を進めたい方向と違う否定をされると、会話のストレスにもなりかねません。そこでつボイが思いついたのは「のいる・こいるAI」です。
つボイ「『いやー僕ねーこの頃ねー旅行が好きでね』『そうそうそう、旅行旅行旅行』『やっぱり日光が…』『日光日光日光、日光がいいです』。「のいる・こいるAI」というやつが一番、これは間違いはない」
小高「それ、何の役に立つAIなんですか?面白いけど(笑)」
レジェンド漫才コンビ「昭和のいる・こいる」独特の、否定しないやりとりをAIにするというつボイの提案に、小高は少々困惑気味。
つボイ「ええやん。ボタンで調節して『のいる・こいるバージョン』ってやると…、『僕ね、昨日ね、ご飯…』『ご飯ご飯ご飯』『美味しかった』『美味しかった美味しかった』。こういう風にやればいいんですよ」
会話をただ否定せず、オウム返しで盛り上げる「のいる・こいるAI」。その実用性はさておき、昭和の笑いを彩った名コンビをモデルにしたAIという発想はなんともユニークです。
反抗期の子風AI?
小高「いろんなバージョンができそうですね」
つボイ「教授が近くにいらっしゃるんで。アイディア持っていこうか?これ聴いてる名大の人がおったら、先生にお伝えいただきたいと思いますけどね」
小高「反抗期の子AIとかどうですか。何言っても『別に』『知らん』」
つボイ「そんなもん作らんでも、いくらでも家庭におるやん。のいる・こいるはそうおらへんやろ?」
人間らしいAIの可能性を、笑いとともに探るふたり。技術の未来は、意外と私たちの日常の会話の中にヒントがあるのかもしれません?
(minto)
番組紹介
読んで聴く、新しい習慣。番組内容を編集した記事からラジオ番組を聴いていただける”RadiChubu”。名古屋を拠点とするCBCラジオの番組と連動した、中部地方ならではの記事を配信する情報サイトです。