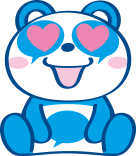マヨネーズはじめて物語~この味を日本の人たちに!夢を食卓に届けた誕生秘話

舞台はスペインの東、地中海のメノルカ島。18世紀半ばにこの島をフランス軍が攻めた。その時に指揮を取った公爵は、島の港町のレストランで、肉料理にかかっていたソースに出会った。こってりとした酸味があって、とても美味しい。公爵はパリに帰ってから、島の港町で食べたソースを母国の人たちに紹介した。港町の名前はマオン。マオンのソース、マオンネーズ、そこから、このソースは「マヨネーズ」と呼ばれ、それはやがて海を越えて、米国にも伝わっていった。

時は流れて、もうひとつの出会いがあった。1883年(明治16年)に愛知県幡豆郡(現・西尾市)で生まれた中島董一郎(なかしま・とういちろう)さん。缶詰会社で働いていた中島さんは、29歳の時に缶詰の研究のために米国へ。そこで、ポテトサラダに使われていた「マヨネーズ」に出合った。アメリカ人の体格がいいのは、このように栄養価の高いものを食べているからなのか、と感激した中島さんは、夢と共に帰国した。「日本の人たちにも、このソースを食べてもらいたい」。
中島さんは、1919年(大正8年)創業のソース類や缶詰の製造会社「食品工業株式会社」の役員のひとりとして加わり、マヨネーズ作りをスタートした。米国で味わったものとは異なり、卵黄を多く使用した「卵黄タイプ」にすることで、栄養価の高いマヨネーズを開発した。それは日本人の体格向上を願ってのことだった。中島さんのマヨネーズにかける思いは、何よりも強かった。

こうして中島さんが心血を注いだ、国産の「マヨネーズ」が完成し、1925年(大正14年)に商品化された。その名前は、洋風のイメージがあり親しまれていたキューピー人形をヒントにした。「キューピーちゃんのような人気者になってほしい」という思いを込めて、シンボルマークにすると共に、自らのマヨネーズに「キユーピーマヨネーズ」と名づけた。しかし、当時の日本では、まだまだマヨネーズという存在は広く知られておらず、瓶に入れて販売されているマヨネーズを、整髪料のポマードと間違える人もいたという。そんなこともあり、1年目に売れたのは、わずか120箱だけだった。
菜種油と大豆油を独自にブレンドするなど、味の改良は進んだ。さらに、当時の日本には味の決め手となる洋風の酢がなかったため、ドイツから機械を購入して自前の酢も作った。卵黄タイプのコクと旨味は和食にも合い、日本人の味覚にもぴったりだった。1941年(昭和16年)には年間の出荷量は、10万箱に増えていた。しかし、太平洋戦争によって油など原料の入手が難しくなると、中島さんはマヨネーズの生産を中止した。「よい原料がなければ、よいマヨネーズを作ることはできない」。「マヨネーズ」への愛とこだわりだった。現在も、最も大切な原料の1つである植物油は「キユーピースペック」と呼ばれる、独自の厳しい品質基準で、しっかりと精製されている。

容器も進化した。ブランドだった「キユーピー」を社名にして「キユーピー株式会社」とした翌年、1958年(昭和33年)には、ポリボトルの容器に入れて発売した。これによって使いやすさが増して、マヨネーズは食卓で人気の調味料になった。酸化を防ぐため、ポリエチレンには酸素を遮断する素材を使用し、今も研究が続く。絞り出し口のキャップには「☆型」も登場し、デコレーションしてかけることができるようになった。350グラムの容量のマヨネーズには、まんべんなく塗ることができる「3つ穴キャップ」も導入するなど、使いやすさも増した。

小袋に入った少量のスティックタイプも発売されて、学校や職場へのお弁当やハイキングなどでも、気軽に使われるようになった。カロリーオフ、血圧が高い人向けのアマニ油マヨネーズ、さらに、ゆで卵にぴったりの燻製マヨネーズなど、味の進化も続いている。

マヨネーズ、そのどこか懐かしく深みのある味は、ニッポンの“食”に美味しさを広げた。「マヨネーズはじめて物語」のページでは、日本の食文化の歩み、その確かな1ページが“愛情たっぷりに”食卓を彩っている。
【東西南北論説風(407) by CBCテレビ特別解説委員・北辻利寿】
※CBCラジオ『多田しげおの気分爽快!!~朝からP・O・N』内のコーナー「北辻利寿の日本はじめて物語」(毎週水曜日)で紹介したテーマをコラムとして執筆しました。