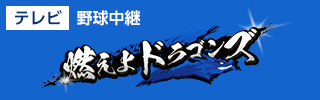王と長嶋の無敵巨人を倒した!その優勝の大いなる価値~ドラゴンズ1970年代~

球団創設84年目を迎えた中日ドラゴンズの2020年シーズンは、新型コロナウイルスの影響によって開幕を迎えることができない日々が続いている。そんな球団の歴史と熱戦譜を年代別にふり返ってみた。今回は「70年代」(1970~1979年)へ旅をする。(敬称略)
70年代の幕を開けたのは谷沢健一
20年ぶりのリーグ優勝という“頂点”があったドラゴンズの1970年代は、投の星野仙一、打の高木守道という2人に象徴されるが、もうひとり、忘れてならないのが谷沢健一である。東京六大学のスターであり、左打ちのスラッガー。歳月が経って球団史をふり返ってみると、この谷沢の入団によって、やがて来る優勝への舞台の幕が開いたと思えてならない。1970年、日本中が「人類の進歩と調和」をテーマとした日本万国博覧会に沸いていた春、ルーキー谷沢は開幕の讀賣ジャイアンツ戦に7番レフトでスタメン出場し、いきなりの2安打。前の年に同じ東京六大学から星野仙一が入団していたが、ファンは明るい“谷沢スマイル”と共に、彼の巧打にも熱い拍手を送っていた。谷沢は新人王を獲得。
1961年の権藤博以来、ドラゴンズからは2人目の受賞だった。
巨人キラー稲葉光雄ここにあり
もうひとり、優勝へのプレリュード(前奏曲)を奏でた選手を挙げるならば、投手の稲葉光雄であろう。背番号「18」。銀縁のメガネをかけたその姿はインテリ風だったが、その闘志たるや熱いものがあった。谷沢に遅れること1年、1970年ドラフト2位で社会人から入団すると、ルーキー年にいきなり先発陣に加わり、そして2年目の1972年に堂々の20勝を挙げた。何よりもジャイアンツに強く、王貞治や長嶋茂雄らを抑え「巨人キラー」とも呼ばれた。この20勝の内、ジャイアンツから6勝、それだけでも竜党としては大満足だったし、王者・巨人へのコンプレックスを見事に払拭していった投球だった。
巨人を倒した優勝の重き価値
9年連続のリーグ優勝、それどころか日本シリーズでも必ず勝って9年連続の日本一。
破竹の進撃を続けていたジャイアンツの10連覇の夢を砕いたのがドラゴンズだった。
1974年の優勝は、単に名古屋の1球団が20年ぶりに優勝したということに留まらず、プロ野球史上でも価値の高いものだと自負したい。それほどに、巨人というチームは強かった。優勝したと言っても、2位のジャイアンツとはゲーム差なしで、勝率はわずか1厘差。勝ち星はドラゴンズの70勝に対して、ジャイアンツは71勝と実はひとつ上回っていたのだから、本当によくぞ勝ち切ったものだ。
20年ぶり優勝の興奮と歓喜
この年に登場した“魂の応援歌”『燃えよドラゴンズ!』の歌詞そのままに、高木守道、谷沢健一、木俣達彦、井上弘昭、島谷金二、大島康徳、トーマス・マーチンらが打ち、星野仙一、松本幸行、三沢淳、稲葉光雄、竹田和史、鈴木孝政らが投げ、栄冠への道を突き進んだ。
そして迎えた1974年10月12日の土曜日、午後8時9分の歓喜の瞬間。この優勝をリアルタイムで味わったドラゴンズファンの脳裏には今も鮮明に焼きついているはずだ。最後の打者のライナーをサード島谷がキャッチし、マウンドの星野仙一が帽子を投げ捨ててキャッチャーの木俣と抱き合い、そして選手だけでなくグラウンドになだれ込んできたファンまでも参加した与那嶺要監督の胴上げを・・・。
退任監督を送る粋な花道
1970年代ドラゴンズを代表する指揮官だった与那嶺要。監督として6年間ドラゴンズを率いて、1977年シーズンを最後に退任した。この年も3位、チームに20年ぶりの優勝をもたらし、さらにBクラスはわずか1回で残りはすべてAクラスという見事な戦績を残してのお別れとなった。アメリカンフットボールで培った闘争心を、野球のグラウンドでも存分に発揮した名選手でもあり名監督だった。
退団が決まってのラストゲームは、1977年10月18日、大洋ホエールズとのダブルヘッダー第2戦だった。星野仙一や高木守道らが申し出て、1974年の優勝メンバーが守備につき、その花道を飾った。この心温まるラストシーンを数多くの竜党の胸に残して、ハワイ出身のウォーリー・ヨナミネは愛してやまなかったドラゴンズを去った。歴史は激動の80年代へと歩みを進める。
【CBCテレビ特別解説委員・北辻利寿】
※中日ドラゴンズ検定1級公式認定者の筆者が“ファン目線”で執筆するドラゴンズ論説です。著書に『愛しのドラゴンズ!ファンとして歩んだ半世紀』『竜の逆襲 愛しのドラゴンズ!2』(ともに、ゆいぽおと刊)ほか。