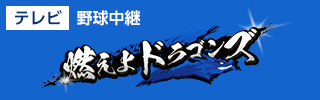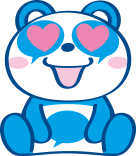星野と高木“竜の至宝”2人の監督が熱く輝いた日々~ドラゴンズ1990年代~

球団創設84年目を迎えた中日ドラゴンズの2020年シーズンは、新型コロナウイルスの影響によって開幕を迎えることができない日々が続いている。そんな球団の歴史と熱戦譜を年代別にふり返ってみた。今回は「90年代」(1990~1999年)へ旅をする。(敬称略)
名選手がチームを率いた90年代
王貞治と長嶋茂雄というプロ野球界のスーパースターを擁した讀賣ジャイアンツの10連覇にストップをかけて、ドラゴンズが20年ぶりにリーグ制覇を果たした1974年。この優勝の立て役者は、投の星野仙一、打の高木守道だった。この年、もし王貞治が2年連続の三冠王になっていなければ、どちらかがシーズンMVPに選ばれていたはずである。そんな2人の名選手が交互にチームの指揮を取ったのが1990年代だった。そしてそれぞれにドラゴンズ球団史に残る大きな見せ場を演出した。
落合が打ち与田が投げた!
実に波乱万丈なシーズンだった。1990年である。星野監督体制4年目を迎えていた。
同じくセ・リーグで4年目を迎えた主砲・落合博満は、ホームラン王と打点王の二冠を獲得。この時点での両リーグ本塁打王は“史上初”という快挙だったが、過去3度の三冠王に輝いている強打者だけに、ファンの間では「二冠では物足らない」贅沢な気持ちもあった。チームに大いなる活力を与えたのはルーキーの与田剛投手だった。開幕戦でいきなりリリーフとして初登板すると150キロを超す剛球を披露して一気に“抑えの切り札”となった。新外国人バンスローのいかにも大リーグ選手らしい活躍、山本昌と今中慎二両左腕が10勝を挙げるなど、これでなぜ4位に沈んだかが分からないシーズンだった。すでに翌年の星野監督退任への予兆が始まっていたのであろうか。
伝説の「10・8決戦」を戦った高木
5年間チームを率いてリーグ優勝も成し遂げた星野監督からバトンを引き継いだのは、二代目「ミスター・ドラゴンズ」高木守道だった。しかし監督1年目の1992年はいきなり最下位。1980年の中利夫監督以来12年ぶりの最下位で、くしくも「中・高木」というかつての名物1・2番コンビが、指揮官として辛酸をなめたことになった。高木がプロ野球史に監督としてその名を残したのが、監督3年目となった1994年だった。世に言う「10・8決戦」、シーズン最終戦で長嶋ジャイアンツと優勝を争った。「国民的行事」と名づけ、次々とエース級投手をつぎ込んだ長嶋采配の前に、高木ドラゴンズは敗れ去った。決戦においてもオーソドックスだった采配の是非もファンの間では語られたが、それが“高木野球”、勝負師としてペナントを勝ち取る道だと信じていたことは間違いない。
翌年6月に途中休養した高木からシーズン後にバトンを受け取ったのは、再登板となる星野仙一だった。
星野の監督力とマネージメント力
監督としての高木が「10・8決戦」によって球団史に名前を刻んだのならば、監督2期目の星野仙一は、ナゴヤ球場のラストゲームと新しい本拠地ナゴヤドームでのスタートという、時代の大きな節目によって印象づけられる。かつて1対4のトレードによって、“三冠男”落合博満を獲得して世間をあっと言わせた“星野マジック”はさらに大胆になり、広いナゴヤドームでの戦いに合わせて、選手の入れ替えを敢行する。韓国からは、リリーフ投手の宣銅烈、スピードスターの李鐘範らを入団させて、球界をあっと言わせた。同時に、川上憲伸、井端弘和、福留孝介、そして岩瀬仁紀ら、のちに2000年代に入っての“黄金時代”を支える主力選手を次々とドラフトで獲得したことは、さすがと言う他はない。フロント的なマネージメント力のある監督だった。その星野監督は、90年代最後の年、1999年に開幕11連勝を飾り、チーム5度目のリーグ優勝を果たした。
星野仙一と高木守道、ドラゴンズの宝物と言っても過言ではない2人が監督として駆け抜けた1990年代。この10年に培われた選手の力は、2000年代に入って大きく花開くことになる。そんな2人だったが、2018年1月に星野、2年後の2020年1月に高木、相次いで鬼籍に入ってしまった。この間チームはBクラスの長き低迷が続いている。
星野と高木、選手としても監督としてもドラゴンズを愛し、そして率いた2人への供養はAクラスでは済まない。優勝しかないと思っているファンは多い。
【CBCテレビ特別解説委員・北辻利寿】
※中日ドラゴンズ検定1級公式認定者の筆者が“ファン目線”で執筆するドラゴンズ論説です。著書に『愛しのドラゴンズ!ファンとして歩んだ半世紀』『竜の逆襲 愛しのドラゴンズ!2』(ともに、ゆいぽおと刊)ほか。