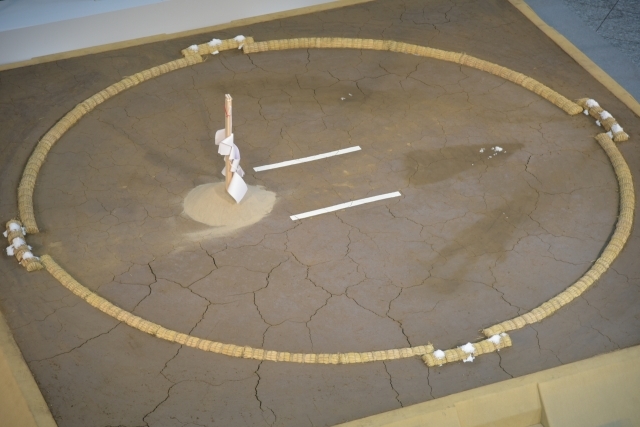「悲しき○○」「涙の○○」洋楽邦題ブームの記憶

11月7日放送のCBCラジオ『つボイノリオの聞けば聞くほど』。音楽を起点にニュースや情報を届ける「トーマスの箱」のコーナーでは、リスナーから寄せられた懐かしの洋楽エピソードを紹介しました。ザ・ビートルズの「涙の乗車券」に乗せて、日本の邦題文化が生んだ「涙」「悲しき」シリーズについて、つボイノリオと小高直子アナウンサーが語ります。
関連リンク
この記事をradiko(ラジコ)で聴く「涙の乗車券」の謎
つボイノリオは日本に洋楽が入ってきた時代、邦題をつける文化があったことを振り返ります。「悲しき〇〇」「涙の〇〇」という曲がヒットすると、その後も同じようなタイトルがたくさん付けられていたのです。
先日の特集で話題になったこれらの邦題に関連して、リスナーから反響の投稿が寄せられました。
「涙の乗車券」は原題が「Ticket to Ride」。タイトルに涙はどこにも入っていませんが、なぜか邦題は「涙」から始まっていました。
「『涙のバースデイ・パーティ』は私も聞きます。涙がつく曲は多いですね」(Aさん)
レスリー・ゴーアの「涙のバースデイ・パーティ」は、1963年6月にビルボード第1位になった曲。当時の価格で330円だったそうです。
カバーがオリジナルを超える
「私は柳ジョージさんのカバーで『悲しき街角』を知りまして、後からオリジナルを聞いた口です。洋楽好きの皆さんには申し訳ないですが、やっぱり柳ジョージのカバーの方が好きです」(Bさん)
つボイ「これが力ですよ。オリジナルを超えてしまうほど、カバーでがっと歌い込めるというのはすごいもんやな」
「『悲しき少年兵』がいいです。1961年、明るいけどどこか切ない感じがいいですよね。初めて聞いたのはFM大阪だったのかな。細川俊之さんの番組でした」(Cさん)
「悲しき天使」と「悲しき悪魔」
「悲しきシリーズの話。エルビスの『悲しき悪魔』というヒット曲が出なかったので、メールしようと思ったらつボイさんが歌ってくれました」(Dさん)
「私の家にも『悲しき天使』のレコードがありますよ。小学校2年生の頃から歌っていましたが、言葉がわからず、曲がいいなと思って聞いていました。曲がいいはずです。ポール・マッカートニーのプロデュースで、メリー・ホプキンが歌っていました」(Eさん)
「悲しき天使」は、1968年のヒット曲でした。
「悲しき」ブームの元祖
「つボイさんは『悲しき少年兵』が先だと言っていましたが、それよりもジョニー・プレストンの『悲しきインディアン』の方が先ではないでしょうか」(Fさん)
「悲しきインディアン」は1959年の曲です。
「『悲しき鉄道員』の話で、昔は『悲しき〇〇』という洋楽があったねと、つボイさん語ってましたね」(Gさん)
小高「1個が流行ると、その後の邦題の付け方が『とりあえず悲しきをつけとこ』となる」
つボイ「あやかっちゃうんですね。きっとまたいい曲だろうと思って買ってしまうんですよね」
「悲しき金太」で大ヒット?
Gさんは、この邦題文化についてある提案をします。
「だったら、つボイさんも『悲しき金太』『悲しきお万』『悲しき松陰』『悲しき黒頭巾』だったら、もっとヒットするんじゃないでしょうか」(Gさん)
つボイ「聞いてみても全然悲しくないから」
小高「今の洋楽も、聞いたら全然悲しくないもんね」
「涙とか悲しきもありますが、『恋の○○』という曲も随分ありました」(Hさん)
つボイ「『恋のバカンス』とかね、『恋のフナ』とかね。フナに恋する話です」
冗談めかして言うつボイに、小高が即座に反応します。
小高「そんなのあるんですか(笑)魚や、それは」
つボイ「みんなやっぱりいろんな思い出があって、私が語る以上に、皆さん方も思い出を語っていただきました」
洋楽に独自の邦題をつける文化は、懐かしい昭和の風物詩。リスナーの投稿から、当時の音楽シーンが生き生きとよみがえりました。
(minto)
番組紹介
読んで聴く、新しい習慣。番組内容を編集した記事からラジオ番組を聴いていただける”RadiChubu”。名古屋を拠点とするCBCラジオの番組と連動した、中部地方ならではの記事を配信する情報サイトです。