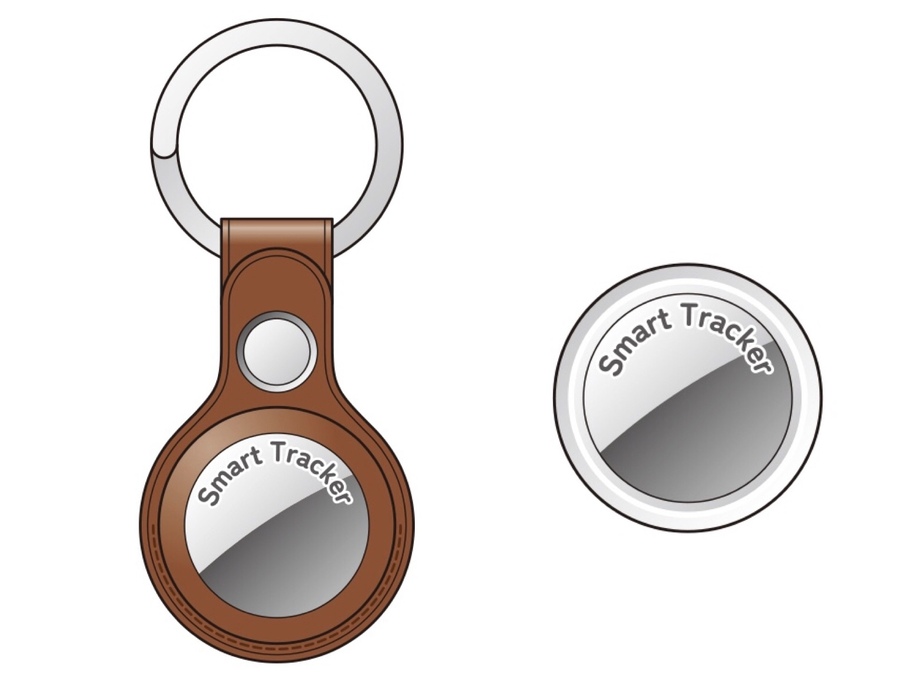森林伐採でアマゾンに地表が露出。自然が開発されていく現状

11月3日付の読売新聞によると、世界最大の熱帯雨林アマゾンで違法伐採が後を絶たず、COP30(国連気候変動枠組み条約第30回締約国会議)の議長国であるブラジルは、日本の人工衛星データも活用して摘発を強化するものの、被害は根絶できていないとのこと。7日放送の『CBCラジオ #プラス!』では、竹地祐治アナウンサーが、この記事を基に北海道やアマゾンで進む環境破壊や「自然との共生」をテーマに語りました。聞き手は石坂美咲です。
関連リンク
この記事をradiko(ラジコ)で聴く自然を資源として見ている?
竹地は番組冒頭で「大人が自然との間に壁を作ってしまったのでは」と切り出しました。
北海道では大規模なメガソーラー開発や、観光施設建設のための無許可伐採が進んでいます。そのことから竹地は、「自然を保護し一緒に生きるという視点が失われている」と指摘しました。
また、「自然を“利益を生む資源”としか見なくなっているのは、視野狭窄のようなもの」と語り、人間中心の社会構造が環境破壊を助長しているのではないかと問題提起します。
アマゾン熱帯雨林に地表が露出
竹地は読売新聞の記事を引用し、南米アマゾンでも違法伐採により森林が急速に失われている現状を紹介しました。
竹地「アマゾンって、川はちょっと見えるけれども、それを覆い尽くすようなすごい緑が南米大陸全体広がってるみたいなオアシス。そこの中に入っただけで加湿器いらないなっていうね」
しかし人工衛星による監視で、アマゾンには地表が露出するエリアが急増していることが明らかになっているそうです。
かつて「地球の肺」と呼ばれたアマゾン。
二酸化炭素を吸収する巨大な貯蔵庫であり、多様な生物の宝庫でもありました。
しかし今や「命の水」とも言える熱帯雨林が地べたと化し、未来の医薬品の源ともなる貴重な生態系が失われつつあります。
竹地は「自然を破壊し、自らの命をも遠ざけている」と警鐘を鳴らします。
自然との共生を考えよう
1980年代に建築家の黒川紀章さんが提唱した「共生の思想」にも言及する竹地。
都市と自然、過去と未来といった二項対立を超え、「共に生きる」という理念が当時は社会に広がっていたといいます。
しかし今、その「共生」の感覚が薄れつつあると武地は語り、自然との距離感を見誤っているのは企業や一部の人だけではなく、自分たちも含めてではないかと自省しました。
こどもたちに身近な『ジャポニカ学習帳』(ショウワノート)では、表紙が写真からイラストに切り替わり、「共生」をテーマに新シリーズが展開されていることを紹介。
自然を遠ざけるのではなく、理解し共に生きる感覚をこどもたちに伝えていくことが大切」と語りました。
石坂「親としては、自然を大切にする感覚は身につけてほしいなっていう風に思いますし、そういった道を親としては作ってあげたいなと」
自然を資源として追う現代社会。一人ひとりが改めて「共生」の意味を考えるべき時が来ているようです。
(ランチョンマット先輩)
番組紹介
読んで聴く、新しい習慣。番組内容を編集した記事からラジオ番組を聴いていただける”RadiChubu”。名古屋を拠点とするCBCラジオの番組と連動した、中部地方ならではの記事を配信する情報サイトです。