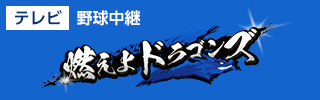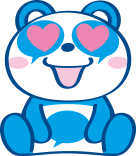来季の「中日」は「ソフトバンク」に勝てるのか?~日本シリーズ2020異聞~

「強い!」このひと言に集約される。2020年プロ野球日本シリーズは福岡ソフトバンクホークスが讀賣ジャイアンツを圧倒し、4勝0敗で日本一の座についた。前年に続く巨人4タテで4年連続のシリーズ優勝である。中日ドラゴンズファンとして、両リーグの覇者対決を見守った思いを記す。
ホークスならベンチに入れるか?
2018年秋に就任した与田剛監督が、初めてユニホームに身を包んで選手たちに問いかけた言葉が今も忘れられない。
「自分が今のカープに入ったとき、レギュラーになれるのか」
リーグ優勝した広島東洋カープを例に挙げての、問いかけだった。これからチームを率いる指揮官の、静かな、しかし重い意味を持つ言葉だった印象がある。そのカープもホークスに敗れて日本一には成れなかった。
当時の弊コラムでは「今のソフトバンクホークスに入ったとき、レギュラーになれるのかという思いで練習してほしい」と檄を飛ばした。
あれから2年、ホークスの圧倒的な強さを目の当たりにした今ならこう書くだろう。
「今のソフトバンクホークスに入ったとき、ベンチに入れるか」。
控え選手たち別次元の“熱量”
今回の日本シリーズで最も印象に残ったことは、ホークスベンチの異様な“熱”だった。
ひとりひとりの選手が、とにかくギラギラしていた。グラウンドでの出番に飢えていた。見せ場を待っていた。
リリーフ投手陣はきっちりと抑えた。代打陣は次々とヒットを重ねた。テレビに時おり映し出されるホークスベンチの熱量は、画面を完全に突き破って届いていた。
何といっても印象的だったのは、シリーズ第3戦、2死満塁で代打として登場した長谷川勇也選手だった。ライト前に抜けるかと思われたゴロをセカンドに捕られると、1塁にヘッドスライディング。間一髪アウトになったが、両手で地面を叩いて悔しがった。高校球児ではない、35歳のベテラン選手である。控えの選手たちの熱き執念を見た。
監督采配も火花を散らした
リーグ制覇した両監督の采配にも注目していた。
勝敗の結果を受けて、パ・リーグとの実力差とか、工藤公康監督の采配の厳しさとか、勝者がクローズアップされているが、2020年シーズン公式戦でのジャイアンツ原辰徳監督の采配は、ドラゴンズファンから見ても見事だった。
かつての巨人は豊富な資金力で次々と他球団から有名な選手を集める体質が指摘されていたが、今季セ・リーグで最も育成に力を入れて、最も若い戦力を起用したチーム、それは原ジャイアンツだった。選手起用だけではない。元木大介ヘッドコーチが虫垂炎の手術のため休むと、2軍の阿部慎之助監督を「ヘッドコーチ代理」として1軍ベンチに招いたことにも驚いた。若手選手は張り切っただろう。
ただ、短期決戦はシーズンとは違う。リーグ優勝してもなかなか日本一になれなかったドラゴンズを長年応援してきたファンには身に染みて理解できる。やはり、豊富な選手層、選手個々の力、何より勝利への熱量においてホークスが勝っていたのだろう。
伝説の“完全試合”へ記憶の旅
シリーズの采配と言うと、ドラゴンズファンとしては思い出さざるを得ない。2007年の日本シリーズ第5戦、ドラゴンズが北海道日本ハムファイターズを下して、53年ぶりの日本一になった試合である。
今回の日本シリーズ第3戦で、7回までノーヒットノーランを続けていたマット・ムーア投手を交代させた工藤采配。その決断、さらに、継投でもノーヒットノーランとなればドラゴンズの優勝試合に次いでシリーズ史上2回目という快挙なるかと注目が集まった。
記録というものは歴史に再びスポットライトを当てる。山井大介投手から岩瀬仁紀投手への「完全試合」リレーを、13年ぶりに懐かしんだ人は、ドラゴンズファンだけではなかっただろう。
「どうしても勝ちたかったから代えました。すみません」
勝利監督インタビューで語る工藤監督の笑みを見ながら、「完全試合」をめぐる賛否両論の議論の中で、当時は沈黙を通した落合博満監督に思いを馳せた。きっと2人の監督の価値観は同じだったはずだ。何としても「勝つ」、その1点。13年の歳月を飛び越えて、この指揮官2人が激突したら、どんな戦いになったのだろうか。日本シリーズに出場できなかった竜党はしばし見果てぬ夢に浸った。
覚悟はあるか?ドラゴンズ
2021年シーズン、ドラゴンズが日本シリーズの舞台に立つためには、Aクラスと言いながら8.5ゲームという大差をつけられたジャイアンツを破ること。さらに日本一になるには、5連覇をめざすソフトバンクホークスに勝つこと。今回の日本シリーズでの王者らしい鷹の戦いぶりに、竜党として眩暈すら覚えてしまった。勝てるのか?
しかし、野球を生業(なりわい)としているチームは日本に12しかない、その1チーム対1チーム。道は険しくも遠くもない。十分戦いになるはずだ。ただし、そのために戦力補強、新戦力の起用、さらに猛練習など現状に甘んじない“よほどの覚悟”が必要である。そして何より、ヘッドスライディング間一髪アウトで思い切り悔しがる“勝利への執念”を、ひとりひとりの選手がドラゴンズブルーのユニホームの胸に刻み込むことだろう。
当コラムのタイトルには基本「ドラゴンズ」を使うが、今回はあえて「中日」とした。ユニホーム姿のベンチだけでなく、親会社もフロントも一体となって日本一の「ソフトバンク」に立ち向かってほしい。そんな願いを込めてみた。
原点にするべき新たな年がまもなくやって来る。球団創設85周年が、3年目の与田ドラゴンズを待っている。
【CBCテレビ特別解説委員・北辻利寿】