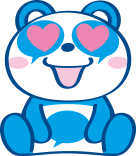★ビートルズが世界を変えた7つの偉業(No.6)歴史が動いたライブ・コンサート

2020年は、ジョン・レノン生誕80年&没後40年。アルバム『Let It Be』発売50年の年でした。2022年は、ビートルズ・デビュー60年・・・を迎えようとしています。
2021年・・・改めて今、1960年代の音楽、カルチャー、社会の既成概念に果敢にチャレンジし、自由にふるまい、大人たちの常識を変えていった、ビートルズのさまざまな偉業について、記憶をたどり整理してみたいと思います。
ジョン・レノン、ポール・マッカートニー、ジョージ・ハリスン、リンゴ・スター・・・いずれも未来を変革する大きなエネルギーを内に秘めた非凡で魅力的な若者たち。4人のチームワークと強烈な個性の化学反応によって、世界はどう変わったのでしょうか?
トラックの荷台から始まった!
ビートルズの歴史の出発点ともいえる重要なライブステージは風変わりな場所でした。1957年6月、ジョン16歳。通っていた学校「クオリー・バンク・グラマースクール」の名にちなんだ「クオリーメン」というバンドを友人たちと組んで学校のダンスパーティーなどで演奏していましたが、地元リバプールのセント・ピーターズ教会で開かれるチャリティー・イベントへの出演が決まりました。そのイベントで「クオリーメン」が演奏をしたステージ・・・それは、街をパレードするトラックの荷台の上でした。教会の関係者たちの手作りイベントらしい微笑ましい光景。しかし、この日のチャリティー・ライブこそ、ビートルズ誕生を決定づける歴史的なライブとなったのです。
この日、クオリーメンの演奏をステージの傍らで熱心に見守っていた一人の若者がいました。ポールでした。ポールは友人に誘われてセント・ピーターズ教会のチャリティー・イベントにやってきました。この友人は元クオリーメンのメンバーだったことから、ポールはジョンに紹介されます。ジョンから見るとポールは2つ年下の14歳。子どもに見えました。「This is Paul.」「This is John.」・・・初めはよそよそしかった二人でしたが、ポールがギターを弾けることと、ジョンが苦手だった弦のチューニングもできることがわかると、ジョンは心を開き二人の会話は弾みました。さらに、ポールが流行のロックンロール・ナンバーの歌詞をたくさん知っていたことから、ジョンとポールは意気投合。ポールがバンドに加わることに。ほどなくしてポールは「ぼくの学校の後輩でギターがうまいやつがいるんだ。メンバーに入れたらどうかな」とジョンに提案。それがジョージでした。ジョン、ポール、ジョージ・・・ビートルズの主軸となる3人がそろったのでした。
そして1962年、ドラマーにリンゴが加わってロンドンに進出し、レコード・デビューを果たすと、ビートルズ旋風はまたたく間に英国全土に爆発的に広がっていきました。ライブ・コンサートは英国内にとどまらずヨーロッパ各地で開催され、ビートルズはハードスケジュールに追われるようになります。
アメリカで新しい歴史が創られた
英国で大成功を収めたビートルズは、1964年、いよいよアメリカへ上陸。アメリカの人気テレビ番組「エド・サリバン・ショー」に出演して「All My Loving」「I Want To Hold Your Hand」「She Loves You」「I Saw Her Standing There」などのヒット曲を披露すると、番組視聴率は60%という驚異的な数字を記録。前年、J.F.ケネディ暗殺で意気消沈していたアメリカ社会にエネルギッシュで明るいニュースをもたらしました。アメリアでもビートルズのライブ・コンサート・ツアーが次々と組まれ、ビートルズはファンにもみくちゃになりながら全米各地を巡回します。どの会場でもチケットはあっという間に売り切れとなり、膨大な数の聴衆を収容できる大規模な会場の確保が求められるようになっていきます。そこで・・・。
ビートルズは世界初となる野球場でのライブ・コンサートを挙行。1965年8月15日の日曜日、歴史的ライブが開催されます。会場は、ニューヨークメッツのホームグラウンド「シェア・スタジアム」。観客動員数は、5万5000人。当時の音楽コンサートとしては過去最大の規模でした。現在では、ドーム球場でのライブ・コンサートは珍しいことではなくなり、多くのミュージシャンが開催するようになりましたが、当時としては全く新しい画期的な企画でした。
日本の歴史を塗り替えた!

ビートルズは日本でもライブ・コンサートの歴史を動かします。ビートルズを日本に招聘した中部日本放送は、当時としては最大規模の観客を動員できるコンサート会場として日本武道館に照準を絞り関係者との交渉を進めました。日本の武道の殿堂である日本武道館を音楽コンサートに使うという発案は前代未聞でした。当初さまざまな抵抗がありましたが、最終的にはビジネスとして決着し、1966年6月30日から3日間にわたるビートルズ武道館公演が実現しました。
その後、ビートルズがライブを行った歴史的な場所となった日本武道館は、日本の多くのミュージシャンたちが競って“武道館ライブ”を敢行する憧れの場所となりました。今では、日本武道館は武道の殿堂であると同時に、ライブ・コンサート会場としてもプレミアムな価値を誇る存在となっています。ビートルズが武道館の新たな歴史を創り出したのでした。
時代を先取り!?“ライブ配信”の先駆者
新型コロナ感染症によって“リモート・ライブ”を配信するミュージシャンが増えていますよね。ところが、今をさかのぼること54年前。1967年6月25日。ビートルズは、当時の最新通信技術だった人工衛星を使った宇宙中継による世界同時生放送のテレビ番組に出演。まだレコードが発売される前の新曲「All You Need Is Love」をライブで歌い、世界に向けて発表したのでした。新曲を“ライブ配信”によって先行リリースするという現代のスタイルを、ビートルズはすでに54年前に先取りしていたというわけです。
「All You NeedIs Love」はリリースされるとまたたく間にヒットチャートの第1位となりました。ベトナム戦争の泥沼化を憂う世界の人々の心に響き、「Love & Peace」の合い言葉と共に平和を訴えるムーブメントを共感の輪でつなぐシンボル曲として広まり、社会に大きな影響力を及ぼしました。
ビルの屋上からオフィス街に大音響・・・

ロンドンの大英博物館に近い中心街に、紳士服の高級仕立て店が立ち並ぶ通りがあります。日本語の「背広」の語源とも言われている「サヴィル・ロウ(Savile Row)」通り。この一角に、かつてビートルズのレコード・レーベル「アップル」の本社ビルだった建物があります。現在は人手に渡って子供服ブランド企業のオフィスになっていますが、レンガ造りのビルの外観は当時のままです。
1969年1月30日、このビルの屋上で歴史に残るライブ・コンサートが行われました。ロンドンは寒い曇り空。お昼のランチタイムでした。ビルの屋上から大音響が鳴り響き始めました。「Get Back」「Don’t’ Let Me Down」「I’ve Got A feeling」「One After 909」「Dig A Pony」・・・ビートルズの生演奏がおよそ40分間続きました。予告無しのサプライズ・ライブでした。1966年以来ライブ・コンサートから遠ざかっていたビートルズの久しぶりの生演奏です。少しでも間近で聴こうとアップル・ビルの周辺には大勢のオフィス・ワーカーが集まりはじめ、ランチタイムのサヴィル・ロウ通りはたちまち黒山の人だかりとなりました。
ビートルズ解散へと向かう冷え切った空気の中で撮影が始まった映画『Let It Be』。ライブ・コンサート史上かつてない意表を突くサプライズの屋上ライブは、映画の最終盤を飾るクライマックス・シーンとしてお膳立てされたものでした。映画の前半は、メンバーの心がバラバラで、けだるく悲壮感さえ漂うシーンの連続でしたが、屋上ライブで演奏する4人の表情は実に楽しそうです。ビートルズの原点はライブ・バンドだったんだ!と改めて認識させられ、このクライマックス・シーンは感動的でもありました。
この屋上ライブの最後の一曲に彼らが演奏した曲が「Get Back」でした。戻ろう!戻ろう!かつて一緒にいたところへ・・・と歌います。解散はもはや避けられない流れだと気づいているジョン、ポール、ジョージ、リンゴの4人は、どのような想いでこの「Get Back 」を演奏したのでしょうか?歌い終えてみんなが屋上から立ち去ろうとしたその時、ジョンだけが振り返ってマイクの前に戻りユーモア混じりの挨拶をしたのでした。「われわれのグループを代表して皆様に御礼を申し上げます。そして、今日のオーディションにどうか合格しますように願うばかりです!」・・・アップル・ビルの屋上に笑い声があふれました。4人そろったビートルズが、ライブ演奏を人々に聴かせたのは、これが最後となりました。
* * * * * * *
常識を打ち破り、新しいことにチャレンジする好奇心とパイオニア精神。これがまさにビートルズ・スピリット・・・50年余り過ぎてもなお、私たちを元気づけてくれるエネルギーの源泉なのです。