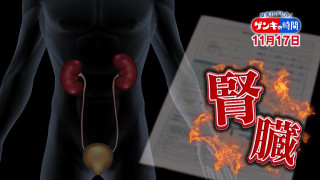医学界の「今年の健康漢字」は?…7人の名医・研究者が一筆!今年の健康漢字2024

身近な健康問題とその改善法を、様々なテーマで紹介する番組『健康カプセル!ゲンキの時間』。
メインMCに石丸幹二さん、サブMCは坂下千里子さんです。
ドクターは、
昭和大学 医学部 内科学講座
糖尿病・代謝・内分泌内科学部門
教授 医学博士 山岸晶一先生
国立国際医療研究センター
医学博士 和田耕治先生
東京医科大学病院 内視鏡センター
部長 主任教授
医学博士 河合隆先生
の三名です。
今回のテーマは「〜医学界の流行は?〜今年の健康漢字2024」
今回のテーマは医学界の「今年の健康漢字」。今年番組に出演してくれた7人の名医・研究者たちが今年の漢字を一筆。その文字を深掘りしながら、最新の医学情報や私たちの健康を守るお得な知識など、今知っておくべき健康トピックを教えてもらいました。
健康漢字 糖尿病の名医は「笑」

糖尿病が専門の山岸昌一先生が書いた今年の健康漢字は「笑」。高齢社会を迎え、大切なのは健康的に老いを迎えること。それに欠かせないのが「笑い」との事。そして、「笑い」は老化物質AGEsとも関係があるそうです。
<老化物質AGEsとは?>
AGEsとは、日本語で「終末糖化産物」。AGEsは、身体に多く蓄積することで老化を早め、さまざまな病気の原因にもなるそうです。そんなAGEsは、食事などで過剰に摂取した糖と体内のたんぱく質が結びつき生まれます。筋肉や骨・臓器・皮膚・爪など身体は主にたんぱく質で作られていますが、AGEsが過剰に溜まると、それらのたんぱく質を劣化させ身体を破壊。やがて糖尿病や、脳・心臓などの血管の疾患、認知症などを引き起こす可能性もあるのだとか。さらに、骨粗しょう症の原因にもなるそうです。
<笑うと老化物質AGEsの蓄積が減少>
これまでの研究で「運動」「適切な食事」「睡眠」でAGEsの蓄積が減少する事が分かっていたそうです。そして、最近になってよく笑う人もAGEsの蓄積が抑えられている事が分かってきたのだとか。先生によると、笑顔の頻度を「月に3回未満」「月に3回以上 毎日未満」「毎日」のグループに分けて比較したところ、毎日笑う人のAGEsの蓄積が最も少なかったそうです。そのため、会話をしたりお笑い番組を見たりなどして、1日1回は笑うようにしましょう。大切なのは、よく笑いリラックスすることだそうです。
<笑うと免疫力も上がる!?>
緊張して交感神経が活性化しているとAGEsが溜まり、リラックスするとAGEsが生まれにくいそうです。笑うと免疫力が上がると言われていますが、笑うと白血球数やNK細胞活性が有意に増加し、免疫機能が改善するというデータがあるそうです。
健康漢字 腎臓病の名医は「寿」
腎臓病が専門の横尾隆先生が選んだ今年の健康漢字は「寿」。人生100年時代と言われているなかで、大事なのは脳梗塞・心筋梗塞・認知症なく健康寿命を延ばす事。そのためには、腎臓の寿命を延ばす事が大切だそうです。
<腎臓を守ることが健康長寿に>
腎臓は、重さ120〜150gと人体の中では比較的小さな臓器。しかし、その機能が落ちると心筋梗塞や脳卒中などの心血管病が起こるリスクが高まるだけでなく、認知症の発症にもつながるのだとか。先生によると、腎臓を守るためには減塩を心がけること。さらに、有酸素運動を行いしっかり栄養を摂る事も大切だそうです。そして、定期的に腎臓の検査を受けることも忘れないようにしましょう。
健康漢字 腸内細菌の研究者は「易」
免疫と腸内細菌研究のエキスパート國澤純先生が選んだ健康漢字は「易」。易とは、古代中国で吉凶を占う術の一つ。先生によると、腸内細菌は私たちの健康を占う(左右する)事ができるとの事。そして、腸内細菌を検出するには通常1〜2か月かかり費用も高額ですが、先生は腸内細菌を簡単に検出する技術を開発しており、安く早く簡単(容易)に腸内細菌を検出できるキットの開発を進めているそうです。
<腸内細菌について>
腸内には、約1000種類の細菌がいます。そのなかには、健康に役立つ「ビフィズス菌」や「乳酸菌」、肥満を抑える「やせ菌」など様々な細菌がいます。そんな腸内細菌は善玉菌と悪玉菌などのバランスを整えることが大事だそうです。
<健康に役立つ腸内細菌の例>
・ビフィズス菌→悪玉菌の増殖を抑制する
・乳酸菌→腸内細菌のバランスを整える
・やせ菌(ブラウティア)→脂肪の蓄積を抑制し腸内環境を整える
<未来の技術 腸内細菌検出キットの実用化に期待!>
腸内細菌が簡単に検出できると、腸内環境の見える化が可能になると考えられるそうです。例えば、腸内にビフィズス菌が足りない事が分かれば、ビフィズス菌入りのヨーグルトを買って摂取するなどして健康管理ができます。さらに、栄養を意識して食べたものが本当に自分にとって効果的だったのかを検証したり、気になる効能を持つとされる菌を意識的に増やしたりする事もできるそうです。
健康漢字 感染症の名医は「備」

感染症が専門の和田耕治先生が選んだ今年の健康漢字は「備」。歴史的に見ると新しい感染症の流行は繰り返し起こっており、感染症については誤った情報もあるので知識の備えが必要との事。さらに、この時期は風邪などが特に流行しやすいので感染症への備えが大切だそうです。
<よくある風邪の予防・対処法>
よく聞く風邪の予防・対処法には「ビタミンCを摂る」「部屋を加湿する」「とにかく汗をかく」などがありますが、先生によると、これらの多くは風邪の予防対策としては間違っているとの事。ビタミンCについては、2012年に過去の全ての研究データを解析し風邪予防の効果はないと結論が出たそうです(※風邪の治療には効果があるという研究結果があります)。
<正しい風邪の予防・対処法>
先生によると、感染症対策の基本は手洗いをしっかりすること。風邪の予防には「ビタミンD」が良いと言われているそうです。ビタミンDは、日光に含まれる紫外線を浴びると体内で作られます。すると、身体の免疫細胞が活性化し、ウイルスの増殖を抑える効果が期待できるのだとか。そのため、1日30分を目安に日光を浴びるようにしましょう(※体調が悪い場合は控えたり寒さに気をつけたりして行なってください)(※日焼け止めを使用した場合、日光浴によるビタミンDの生成効果は大幅に減少します)。部屋の加湿については、冬は特に乾燥しているため加湿の効果があまり期待できないと言います。そのため、加湿よりは空気を入れ替える「換気」の方が効果的。汗をかく事に関しては、結果的に汗が出るのは良いですが、積極的に汗をかこうとするのは良くないそうです。
<糖尿病患者は特に注意>
糖尿病患者の死因の2位が風邪などによる感染症だそうです。そのため、冬場は風邪をこじらせないように特に注意しましょう。
健康漢字 整形外科の名医は「股」
整形外科が専門の高平尚伸先生が選ぶ今年の健康漢字は「股」。上半身と下半身をつなぐ最も大きな関節「股関節」は、とても大切な関節。股関節が外傷を受けたり重症化したりすると、歩けなくなるなど日常生活に支障が出ます。そんな股関節の治療法が近年進化したそうです。
<大切な股関節を守る治療法>
股関節の手術のなかでも、歩けないなど重症化した場合の根治治療が「人工股関節置換手術」。手術は、骨盤を削って受け皿を入れ、大腿骨の頭を取り除いて器具を埋め込み、骨盤の受け皿に器具をはめるというもの。先生によると、近年ロボットを利用した人工股関節置換術が開発され、人工関節を設置するときの設置精度が非常に高くなり安全性も向上しているとの事。そんな人工股関節置換手術は20年で4倍に増加。手術をすることで症状の改善が期待できるそうです。とはいえ、股関節の痛みや歩きづらいなどの異変を感じたら、早めに病院を受診しましょう。
今年の漢字 認知症の名医は「認」
認知症が専門の小野賢二郎先生が選んだ今年の健康漢字は「認」。認知症のなかで最も多いアルツハイマー型認知症の新しい治療薬が認められたことと、認知症が根治に向かう可能性があることからこの漢字を選んだそうです。
<進化した認知症の医療>
アルツハイマー型認知症は、脳内にアミロイドβなどのたんぱく質が溜まり、神経細胞がダメージを受け脳の中でも記憶を司る海馬などが萎縮することで発症します。その薬として、2023年12月から病院で使用されているのが「レカネマブ」。レカネマブは、アルツハイマー型認知症の原因物質に直接働きかけ進行を抑える薬。完全に進行を止めることはできないものの、約3割進行を緩やかにできるのだとか。それにより、自分らしい日常生活を長く続けられる効果が期待できるそうです。さらに、2024年11月26日には国内2例目となる新薬「ドナネマブ」も発売。今後治験や研究が進めば、さらなる新薬によって、認知症が根治に向かう可能性もあるそうです。
今年の健康漢字 消化器疾患の名医は「非」
消化器疾患が専門の河合隆先生が選んだ今年の健康漢字は「非」。胃がんの主な原因といえば「ピロリ菌」ですが、ピロリ菌以外の菌(非ピロリ菌)も胃がんの原因になることが新たに分かったそうです。
<胃がんの新たな原因とは?>
胃がんの主な原因であるピロリ菌は胃粘膜を攻撃します。すると、傷ついた胃粘膜が長い時間をかけ、がん化する事があるのだとか。ところが、ピロリ菌除去後20年経ってから胃がんになった患者がいる事から、ピロリ菌以外の口腔内細菌なども胃がんの原因になる事が最近になって分かったそうです。
<来年発表!胃がんを抑える食べ物>
先生によると、研究の結果「納豆」が口腔内細菌の感染を抑えることが分かったのだとか。そのため、少なくとも1日1回は納豆を食べるのがオススメだそうです(※ワルファリンカリウムを含む抗凝固剤を服用中の人は納豆を控えてください)。
(2024年12月29日(日)放送 CBCテレビ『健康カプセル!ゲンキの時間』より)
番組紹介
ニッポンの皆様に健康生活を!この言葉をキーワードにすぐに役立つ健康情報をお伝えします。「人」「家族」の未来を創り出す、CBCテレビの健康情報番組。