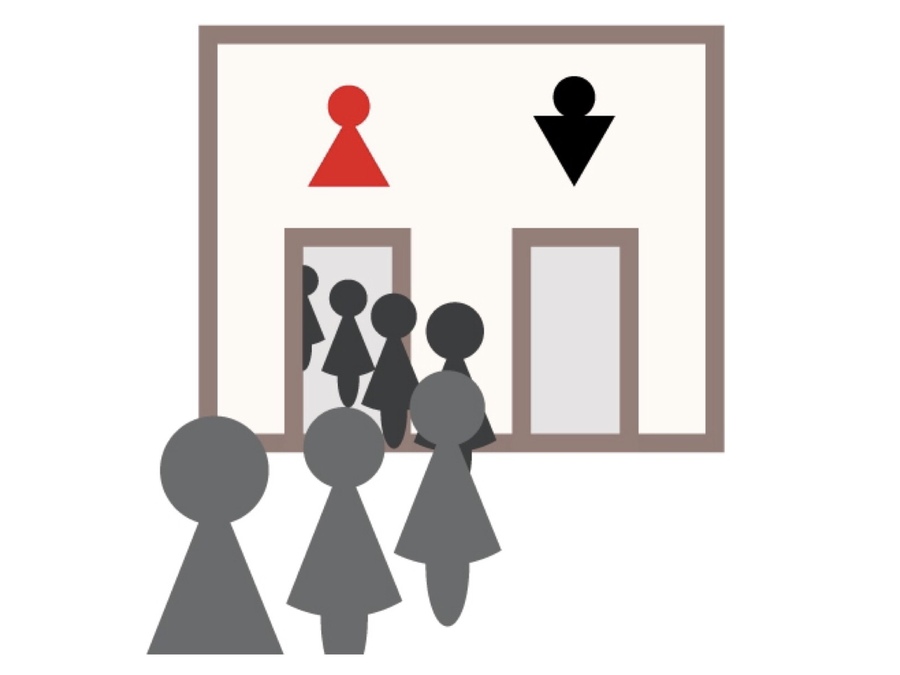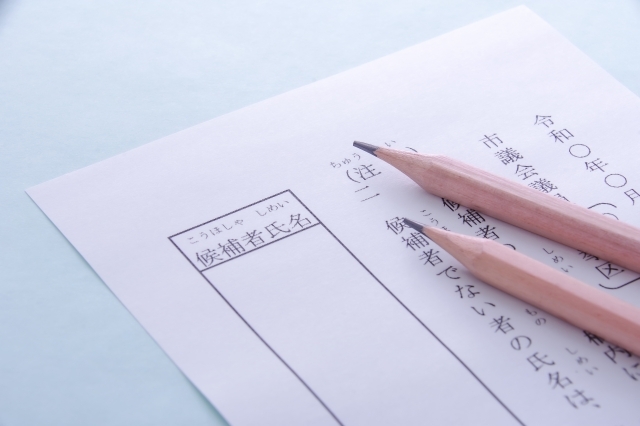YouTube誕生20年! 出会い系から世界を変えた動画プラットフォームへ

Google社が運営する世界最大の動画共有サービスYouTubeが、2月15日で開設から20年を迎えます。今やスマートフォンで誰もが日常的に利用するYouTubeは、どのような背景で誕生し、これほどの人気を獲得したのでしょうか?2月13日放送の『CBCラジオ #プラス!』では、CBC論説室の石塚元章特別解説委員が、YouTubeの歴史と人気の背景、そして社会に与えた影響について解説しました。
関連リンク
この記事をradiko(ラジコ)で聴くYouTubeの誕生と進化
YouTubeは、インターネット上で誰もが自由に動画を共有できるサービス。投稿者は無料で動画を公開でき、視聴者も無料で好きなコンテンツを楽しむことができます。
2005年に設立され、翌2006年にはインターネット業界の大手であるGoogleによって買収されました。
現在の利用者数は驚くべき規模に達しており、世界では月間25億人、日本国内でも人口の半数以上にあたる7000万人が利用しています。
永岡歩アナウンサーは、娘が赤ちゃんの頃から音楽コンテンツを活用していると話します。「泣き止む音楽をYouTubeでループ再生していました」と、子育ての場面でも身近なツールとして活用されている実態を紹介しました。
きっかけは「胸ポロリ事件」
YouTubeの誕生には興味深い背景があります。
創業者となる3人は、大手決済サービス会社「PayPal(ペイパル)」の元社員でした。2004年、この3人は「一緒にベンチャー企業を立ち上げないか」と意気投合してPayPalを退社。YouTube設立の1年前のことでした。
そして2004年、YouTubeの構想に大きな影響を与えた2つの出来事が起こります。そのひとつが、アメリカンフットボールの最高峰の大会「スーパーボウル」でのハプニングです。
高視聴率を記録したハーフタイムショーで、歌手のジャネット・ジャクソンによる「胸ポロリ事件」が発生します。パフォーマンス中に衣装の一部が外れ、インナーも一緒に取れてしまうというハプニングが生中継で放送されました。
この出来事をきっかけに、放送を見逃した人々が映像を探し求める現象が起きました。
当時は録画機能が存在したものの、見たい映像を簡単に共有する手段がなく、多くの人々が動画を探し回ることになりました。
インド洋大津波の映像衝撃
もうひとつの重要な出来事は、2004年末に発生したインド洋大津波です。
観光客たちが、携帯電話やビデオカメラで襲来する津波の様子を撮影した映像は、既存のサービスを通じて共有され始め、多くの人々の関心を集めたのです。
スーパーボウルとインド洋大津波という2つの出来事が、創業者の3人に「動画共有サービスには大きな可能性がある」という大きなヒントを与えました。
誰もが自由に動画を共有し、視聴できるプラットフォームを作ろうと考え、YouTubeの立ち上げを決意したのです。
YouTubeで最初に公開された動画は、創業者のひとりが動物園で撮影した18秒の映像でした。
ゾウの檻の前に立ち、背後のゾウを指して「こいつ、鼻が長くていいだろう」とコメントする何気ない内容が、後の巨大プラットフォームの第一歩となったのです。
意外な原点は出会い系サイト?
興味深いことに、YouTubeの創業者たちは当初、このプラットフォームを「出会い系サービス」として構想していました。
ところが実際に運営を始めると、ユーザーたちは思いもよらない使い方を見せます。ペット動画や流行の紹介、料理の手順など、現在のYouTubeの使用方法に近い投稿が続々と集まったのです。
創業者たちはここで重要な気づきを得ます。
「恋人探しに限定する必要はない。むしろ、どんな動画でも自由に投稿できる場所にした方が、ビジネスとして成功するのではないか?」
この決断が、現在のYouTubeの基盤となりました。
偵察の敵陣営を「サル」
サービスが軌道に乗り始めると、YouTubeは社会に大きな影響を与え始めます。その代表例のひとつは、選挙への影響力でした。
2006年、アメリカの中間選挙で衝撃的な出来事が起きます。
共和党の重鎮で、州知事も務め、大統領候補としても有力視されていたジョージ・アレン上院議員(当時)。現職で圧倒的な優位が予想された選挙でしたが、思わぬ形で落選することになります。
落選の決定的な要因となったのは、選挙運動中のアレン氏が発したひと言。
相手陣営から偵察に来ていたインド系のスタッフに対し、「見ろよ。あそこにサルがいるぞ」という差別的な発言をしたのです。
そのスタッフは、持っていたビデオカメラでこの差別発言の一部始終を撮影。そして、この動画はすぐさまYouTubeにアップロードされました。
アレン氏の発言は、その場にいた支持者たちの受けを狙ったものでした。その場では支持者たちの笑いを誘った発言でしたが、YouTubeで広く拡散されると、差別発言への批判が巻き起こります。
当選確実と思われた大物議員を落選へと追い込んだこの事例は、YouTubeが武器となり政治を動かすこともある、という象徴的な出来事となりました。
「シティポップ」の火付け役
最近のケースでは、日本の「シティポップ」が世界で再評価されるきっかけとなったのも、やはりYouTubeでした。
竹内まりやさんが1984年に発表した楽曲「プラスティック・ラブ」が、2017年になって突如注目を集めたことがありました。
リリース当時はそれほどのヒットではなかったこの曲が、アメリカの学生が投稿した非公式の動画をきっかけに、世界中で「クール」と評価され、広く知られるようになりました。
さらに2020年には、YouTuberとして活動するインドネシアの女性シンガーが、松原みきさんの「真夜中のドア~Stay With Me」を日本語でカバーし、これも大きな反響を呼びました。
過去の名曲が「発掘」され、新たな価値を見出された「シティポップ」のリバイバルは、YouTubeという世界中の人々がアクセスできるプラットフォームだからこそ起こったのです。
「アルゴリズム」の影響
世界に日本の「シティポップ」が広がった背景には、YouTubeの「アルゴリズム」の影響も大きかったといえます。
視聴者の好みを分析し、関連する動画を「レコメンド(おすすめ)」として表示するシステムにより、「プラスティック・ラブ」を聴いた人に次々と同じようなシティポップの楽曲が紹介され、ジャンル全体の人気につながっていったのです。
興味深いのは、当初広まっていた非公式の動画に対する権利者側の対応。
楽曲の人気の高まりを受けて、竹内まりやさんの陣営は2020年に新たな公式ミュージックビデオを制作。この新しい映像作品もまた、多くの視聴者から好評を博しています。
新時代に求められる倫理観
YouTubeはひとつのきっかけから大きな可能性を生み出し、20年後の現在では社会に欠かせないプラットフォームへと成長しました。
しかし、誰もが簡単に情報を発信・拡散できるようになった一方、使用する側にも新たな倫理観が求められています。
特に広告収入が高額化する中で、暴露系コンテンツや迷惑行為、私人逮捕といった、視聴者や対象者に悪影響を及ぼす可能性のある投稿も増加し、社会問題化しています。
プラットフォームの可能性を活かしながら、いかに倫理的なバランスを保っていくかが、今後の重要な課題となっています。
(minto)
番組紹介
読んで聴く、新しい習慣。番組内容を編集した記事からラジオ番組を聴いていただける”RadiChubu”。名古屋を拠点とするCBCラジオの番組と連動した、中部地方ならではの記事を配信する情報サイトです。