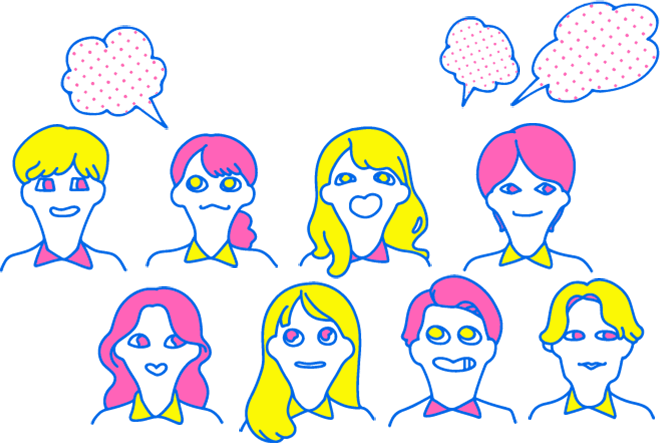
-
CBCテレビを選んだ理由は?
-
 H.T さん
H.T さん選考を通じて、CBCテレビの「一人一人を大切にする」雰囲気が凄く伝わってきたためです。
グループディスカッションが終わった後に「どうだった?」「普段の自分と一緒だった?」と聞いてくれるのが、本来の自分を見つめてくれている気がして凄く嬉しかったことをよく覚えています。
面接を通して自分の得意なところも苦手なところも知ることができて、毎回選考が楽しくて仕方なかったし、ここで働きたいという気持ちが強くなりました。 K.H さん
K.H さんCBCテレビでは「全国規模の番組も、東海エリアに密着した番組も制作できる」という自分のやりたいことを実現できる環境があると感じたからです。
また、選考の時にお会いした社員の方々の空気感もよく、自分が働きたいと思える雰囲気だったこともCBCテレビを選んだ理由の1つです。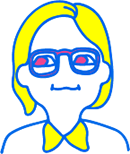 T.S さん
T.S さんインターンや選考を通して、自分が自分らしくいられそうな会社だなと感じたからです。
就職活動当初から"ありのままの自分で選考に臨む!"と心に決めていたのですが、己の言動や考え方含め、一番違和感なくフィットした感覚がありました。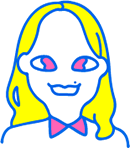 F.Y さん
F.Y さん報道において、小さな問題のタネを見逃さず、徹底的に取材し続ける粘り強さに衝撃を受けたからです。
そしてドキュメンタリーの、障がい者と健常者の壁を作らない構成と言葉選びが凄く心に刺さるものだったからです。
全国・地方両方に情報を発信することができ、万人受けもニッチな部分も含めて、自分のやりたい様々なことを実現できる場所だと思いました。
-
CBCテレビの印象は?
-
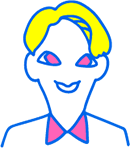 T.M さん
T.M さん個性が強く様々なタイプの方が働いている印象です。
いくつかの研修で現場に行きましたが、とにかく熱意を持って仕事をしている方が多く、かっこいいなと心から感じました。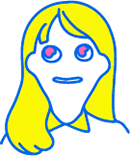 A.N さん
A.N さん『ゴゴスマ』『アガルアニメ』等、在名局ながら全国規模の大きな仕事ができるチャンスに溢れているという印象です。
私は地元が大阪なのですが、テレビ局志望の理由の一つに「自分の作ったものを届けることで大切な人たちを支えたい」という想いがあります。
名古屋から大阪に自分の作ったものを届けられる可能性があるのは非常に魅力的なことだと思っています。 T.T さん
T.T さん「人」を大切にすることです!
取材先の方々、視聴者、局員、そして内定者…人々の人柄を本当によく見ているなと多くの研修を通して感じました。
私もそんな先輩方のもとでこれから出会う方々一人一人を大切に、テレビを通して東海地方を盛り上げたいです!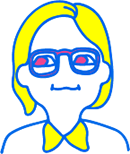 T.S さん
T.S さん"バランスが良い"です。
これまで関わった方々皆さんとても親切でフレンドリーだったのですが、それと同時に少しシビアだったり真面目なお話をする際のバランス感覚が非常に優れているなと感じました。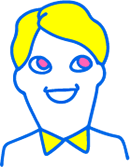 T.M さん
T.M さん元々ラジオが好きなこともあり、CBCエリア外でもその名前は知っていました。
報道、スポーツ、バラエティ、ドラマ、舞台と思った以上に作れるコンテンツの幅が広いことに驚きます。
全国ネットの単発特番もあり、全国の人にCBCテレビの番組を見てもらえる機会があります。
日本初の民間放送局ということで伝統を重んじる社風かと思いきや、YouTubeのコンテンツを筆頭に「何か面白いことをやろう」という空気を感じ取れました。
-
就職活動でやっておいて
良かったこと! -
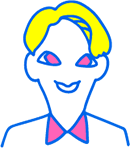 T.M さん
T.M さん日常生活で少しでも興味を持ったこと、面白いなと感じたことはすぐにメモをするようにしてました。
テレビ局の面接は幅広い質問が多いので、それに対応できるように模擬面接も常に行っていました。 A.O さん
A.O さん自己紹介で使えるキャッチコピーを作ることです。
そのおかげで、一次面接のときから目をかけてくれた社員さんもいました。
自分の歴史を振り返り、インパクトのあるものを作ってみてください! H.T さん
H.T さん初歩的なことですが、因果関係が分かりやすい文章を面接でもESでも用いることを意識していました。
どうしてこの経験がこのスキルに繋がっているのか、どうしてこの生い立ちがこの志望理由に繋がるのか、どうして”今”テレビ局で働きたいのか…などです。
理由と結果をセットにして伝えると、分かりやすいだけでなく、ストーリーがドラマチックになっておすすめです。 K.H さん
K.H さん沢山あるので、特にやっておいて良かったと思うことを3つ挙げます。
①「面接での想定質問集を作り、予めどんなことを話したいかを考えておくこと」です。
質問集は企業ごとにワード10ページ以上作って印刷し、面接前の電車内で見返すようにしていました。
そうすることで、「これだけ準備したから、どんな質問をされても私は焦らないぞ!」と思うことができました。
②「面接では何を質問され、どんな回答をしたのか」を面接後にメモしておくことです。
そうすることで、選考を受ける中で自分の回答をブラッシュアップすることができます。
また、どんな質問がされやすいのかという傾向も知ることができました。
③「自分にしか話せないエピソードを探すこと」です。
何も思い浮かばなかったら、今から新しいことを始めるのも良いと思います。
私は名古屋にある実家から京都の大学まで新幹線通学をしていたので、このエピソードを地元愛と結びつけて話していました(笑)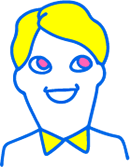 T.M さん
T.M さん(1)志望動機、自己PRなど、面接でしゃべるネタの徹底した深掘り。
表面的な薄っぺらな話ではなく、自分の生き様や人生とリンクさせると面接官は面白がってくれるはず。
(2)自己紹介をキャッチ―にすること。
「○○の子」と面接官に思わせることで、何百人という受験者の中でも埋もれないようになるはず。
(3)広く薄くではなく狭く深く。
「私が注力したことは3点あります。」などと言うよりも、一つのネタを局所的に喋った方が、人となりが伝わりやすいはず。
テレビの面接は10分程度しかないので、いかに短時間で「差別化」し「人となりを伝えるか」という戦略を徹底的に意識した方がいいと思います!
-
就活生へ応援メッセージ!
-
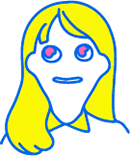 A.N さん
A.N さん私はテレビ局しか受けてこなかったので早くに就活が始まり、CBCから内定をもらえるまで本当に長く、不安だらけの就活でしたが、同じくテレビ局で働くことを目指した友人ができました。
2人揃って何度も落ちたけど、違う土地ながら4月から同じ系列局で働くことになりました。
テレビを受ける人たちは全員ライバルで全員仲間なんだなと本当に実感しています。
その会社に縁があってもなくても別の財産もたくさん得られるような後悔のない就活をしてください! A.O さん
A.O さん面接前、ガチガチに緊張していた私ですが、内定者の声の「CBCでお待ちしております」というメッセージを見て、社員の方の笑顔を想像し、面接室の扉を開ける『勇気』を持てました。
私も笑顔で待っているので、安心して一歩踏み出してみてください! T.T さん
T.T さん実際に企業に行って他の就活生を見ると、不安になり周りの人がすごく見えることがあります。
でも大丈夫です!
周りもあなたと同じだけ不安で、あなたのことをすごいって思っているはずです!
そんな会話を内定出たあと、同期のみんなと話したので間違いありません!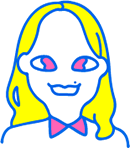 F.Y さん
F.Y さん就職活動が思い通りに行かず、その上手くいかないギャップに苦しんだ時、色んな不安が重なって心が押し潰されそうになる瞬間が何度もあると思います。
最後の最後まで努力し続けて、内定した友人を何人も見てきました。
諦めなければ夢は叶う...わけでは無いかもしれませんが、夢を叶えた人は必ず、諦めないで努力した人だと思います。頑張ってください!

